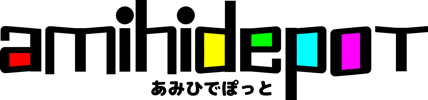[font]
甘い匂いに包まれた、ある秋の、不思議な出会いとほのかな恋の話。
***
彼は高校3年生だった。大学受験を目の前に控えた、忙しい時期。暑さが落ち着き始めた10月。
その日、毎日のように通り過ぎていたとある家の前で、彼は自転車を止めた。なんのことはない、ただ、甘ったるく鼻奥をくすぐる匂いが、彼の意識を引き留めた。
彼は塀の向こうに、一人の少女を見た。否、少女というにはどうも大人びていて、けれど女性と呼ぶにはあどけなさがあった。
なぜか気になったその少女を見つめていると、少女は長い波打った茶髪を揺らしてこちらを振り向いた。彼は慌てて、その場から立ち去った。それが、彼と少女の、最初の出会い。
翌日も、甘ったるい匂いが、彼の鼻奥をくすぐった。そうして昨日と同じように、視線の先には少女がいた。
「何かご用?」
少女ははっきりと、優しく、されど明るい声で、彼に語りかけた。
もちろん彼は驚いて、けれど話しかけられたからには逃げることもできず、「こんにちは」とあいさつを返した。
「そんなところに立っていないで、こちらへどうぞ?」
少女はにっこり笑って、彼を手招いた。
彼は少女に招かれて、家の、庭へと踏み入れる。そうして気付いた。庭の真ん中に緑色の丸テーブルが1つ。イスは2つ。家は寂れて人気がないのに、少女は1人きり、庭の真ん中のテーブルで、お茶をしていた。
そうしてもう一つ気付いたのは、庭を囲うように育った垣根に、無数のオレンジ色の小さな花が咲いていたこと。庭いっぱいにあの甘ったるい匂いが広がっていて、少女からも、それは香った。
「私の名前はカネキ。お兄さん、お名前は?」
「杉原です」
「杉原くん。下のお名前は?」
「…幸平です」
下の名前まで聞かれると思っていなかった彼、幸平は驚いた。フェアではないと思った。カネキさんは、きっと名ではなく姓だろうから。けれど尋ね返すことは出来なかった。
「幸平くん」カネキさんはふわりと微笑んで、手元にあったティーカップへ紅茶を注いだ。「お茶、いかがかしら?」
それから毎日、学校帰り、カネキさんのいる庭に立ち寄るのが、幸平の日課になった。
カネキさんの話では、どうもこの家は9月にご主人を亡くして、今はカネキさん一人らしい。カネキさんはご主人に育てられたそうだが、娘ではないらしい。毎年この時期は、ご主人と二人でお茶をしていたらしい。
カネキさんから出されるお茶は、いつも甘い香りがした。庭いっぱいに広がる匂いと同じ。でも、口に広がるのは紅茶のソレ。不思議な感じがした。
カネキさんからも、いつも甘い香りがした。これまた庭いっぱいに広がる匂いと同じ。そして妙なことに、日に日に会うたび、髪の色は暗くなっていた。
2週間経ったある日、幸平は気付いた。庭いっぱいに広がっていたあの甘ったるい匂いが、薄くなっていることに。そうしてもう一つ気付いた。カネキさんが淹れてくれる紅茶の香りが、薄くなっていることに。…そして、カネキさんからの香りも、薄くなっていることに。
「今年で最後なの」その日、カネキさんは笑って言った。
「主人のばあさまが亡くなってしまったから、毎年恒例のお茶は、今年で最後。でも、寂しくなかったのよ」
カネキさんは、垣根から枝を一本手折って、幸平に渡した。
「最後に、あなたが私を見つけてくれてよかった」「覚えていて。この香りは、この花の名前は、」「金木犀というの」
翌日、幸平がいつものように庭を訪ねると、その家は取り壊されていた。
なんでも、一人暮らしの女性が9月に亡くなって、息子夫婦がすぐに取り壊すことを決めていたらしい。10月末には取り壊すのだと、近隣の人たちも知っていたらしい。
少女など、その家には住んでいなかった。
ただ、近隣の人たちが口を揃えて言うには、「あのお宅の、金木犀の垣根は毎年立派に咲いて、10月の訪れを教えてくれていた」と。
幸平は、カネキさんから受け取った金木犀を、鉢に植えて育てた。翌年には、ほんの少し花が咲いた。ふわりと甘ったるい匂いが鼻奥をくすぐるたび、あの日を思い出した。
そうして時が過ぎて、幸平は大学生をへて、社会人になった。鉢に植えた金木犀は、幸平の胸辺りまで伸びていた。
10月。今年もそろそろ、鉢に植えた金木犀が花を咲かせる頃。いつものように横を通り過ぎていた空き地の前で、幸平は足を止めた。空き地だったそこには、小さな家が建っていた。
表札には、「金木」の二文字。はてと玄関を見つめていると、宿主であろう人影が扉から出てきた。そうして、その人影はこちらに気付いて、ふわりと笑みを浮かべた。
「――こんにちは、お兄さん。」「今日から越してきた、カネキ、ヒジリです。」
幸平は、その顔に覚えがあった。そうして何より、その香りに覚えがあった。だから、そんなはずはないと思っても――あの出会いさえも非現実的なものであったから――ソレが嘘ではないと、わかってしまった。
人影、否、少女は、幸平の表情の理由に気付いて、小さく吹き出す。そうして、首を横に振って、にっこりと笑った。
「ううん。そう、違うわね」「――ただいま、幸平くん」
[/font]