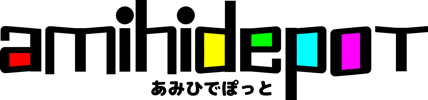[font]
――21世紀初頭、2001年。
発展を続けると思われていた文明は、膨大なエネルギーの衝突により、または膨大な情報の衝突により、一瞬にして消滅した。その原因の詳細は100年の歳月を以てしても明らかになることはなかったが、事実として、世界中の都市が一瞬にして崩壊・崩落し、地上からその姿を消したのだった。
地上から消えた都市の多くは、地下に面影を残したまま忘れ去られ、地上には新たな文明が築かれた。と同時に、火力・水力・風力などに取って代わる超次元の動力源“メタエネルギー”が発見された。それは、電力と酷似した性質を持っていたが、奇妙にも“使い手”の意思に合わせて――石油を思わせる液体や、黒曜石を思わせる固体といった姿に――変容する性質を持っていた。保有するエネルギー量も見た目の質量をはるかに上回り、いつしかそれは、一種の魔力を秘めた結晶として人々に認識されるようになった。そしてその本質は、世界中の都市が崩壊とともに失った技術・知識・情報などの“ロストテクノロジー”が結晶という形に凝縮され、顕現した姿だった。
メタエネルギーは、保有するエネルギーを消費するたびに蒸気を生んだ。そのため、メタエネルギーの存在する場所には常に蒸気が立ち込めていた。そしてメタエネルギーのほとんどは、地下に埋もれた都市“ロストシティ”で発見された。人々は、メタエネルギーを求めて地下へと赴いたが、生きて戻ってこれる者はごくわずかだった。というのも、そこはすでに人智を超えた空間と化していたのだ。メタエネルギーを取り込んだ物質は膨大なエネルギーを持ち、それは擬似的な生命を得た状態になり、意思を持ったもののようにうごめき、命あるものを襲い、食らった。人々は、メタエネルギーの核を持った地下の生命体を“ゴースト”と呼んだ。
ゴーストに対して力をふるえる者は、そう多くなかった。地上に残された人々の中から戦闘能力に長けた者が集められ、討伐のためにロストシティへと派遣されたが、それでも危険を伴った。たとえ力があって命が助かっても、体の一部を、ともすれば心の一部を失うことさえあった。それでも、人々は新たな文明によって生まれた利便性を手放すことはできず、メタエネルギーを求め続けた。
――22世紀末、2190年。
メタエネルギーの普及により、一度崩壊した世界は、19世紀初頭を思わせる活気を取り戻すまでに成長した。世界各地に、人口が集中した大都市“メガシティ”が生まれ、メガシティ同士は鉄路・航路・空路によって結ばれた。メガシティ間の人々の往来により、異文化交流は前世紀より盛んになった。そして、かつて英語と呼ばれたそれが世界の公共語として浸透していき、言語による異文化間の障壁は減っていった。
地上の文明が発展し変容していく一方で、地下に埋もれたロストシティは、世界の崩壊から200年近くの時を経てもなお、人智を超えた危険な空間のままだった。そのため、ロストシティからメタエネルギーを恒久的に回収するべく、世界各地で、大都市を統制する政府が指揮を執り、特別な訓練を受けた人による専門の治安部隊を構成するようになった。その部隊は、かつて戦闘のために訓練された組織を意味する“軍”と呼ばれた。
軍は、大都市を統制する政府直属の部隊として、メタエネルギーの回収のほか、ロストシティ内のゴースト討伐、ロストシティに残された古代遺産の保護、不法侵入者の監視など、さまざまな任務を任されることとなった。各地域の自警団と協力し、メガシティの治安維持も行うようになった。
同時に、政府の指揮のもとに動く治安部隊を良しとしない、“レジスタンス”も誕生した。レジスタンスの多くは、政府主導のもとにメタエネルギーが回収されることを容認せず、独自に回収する組織だった。その行為から“盗賊”とも呼ばれたが、そこに所属するメンバーのほとんどは一般市民であり、ともすれば、貧困層が生活するためには欠かせない義賊のような存在でもあった。そのため、政府もある程度はその活動を黙認していた。
――23世紀初頭、2201年。
この年、優秀な青年が一人、メガシティ「トーキョー」政府直属の軍に入隊した。名前はカイン・オルティス。表情と口数の少ない、いかにも真面目な雰囲気をまとった青年だった。そして、身にまとう雰囲気に反して、紫色の髪は頬や首筋にかかるくらい無造作に伸び、透き通るような金色の瞳は気だるげに伏せられた瞼でわずかに隠れていた。何より、右半身――メタエネルギーを内蔵した義手と義足が目を引く青年だった。
入隊試験の成績を買われたカインは、入隊直後から、ロストシティ内のゴースト討伐部隊に配属される。そして彼は、その期待通り、確実に任務をこなしていった。入隊から2年後の、討伐任務を遂行するまで。
[/font]