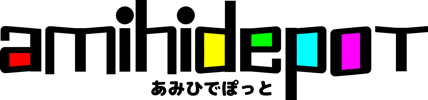[font]
とっつきにくそうなギャルに見える女子、望月 亜澄(もちづき あずみ)と、軽そうでバカっぽい男子、河野 宗馬(こうの そうま)の、席が隣になったことがきっかけで始まる話。
***
このクラスでは2ヶ月に1回席替えをするのが恒例行事になっている。そうして今日は11月になって最初の月曜日。席替えの日だ。
(――可愛い子が隣だといいなぁ……)
俺はそんな事を思いながら、クジによって決められた席番号を確認する。手に持っている紙切れに書かれている文字は「A6」――窓際の一番後ろの席だ。悪くない、そう思うと、少し頬が緩んだ。
では、隣の席――「B6」を引いたのは誰だろう。可愛い女の子だなんて高望みはしないから、せめて楽しく話せる人がいい。黒板に書かれた「B6」の2文字をじっと見つめた後、席に着こうと振り返る。自分の隣になる人物は既に席へ着いていて、俺はその顔を確認した瞬間、最悪だと思った。
(――望月じゃねーか……!)
望月亜澄。彼女はクラスの中で一番の成績で、男女共に受けの良さそうな可愛くもかっこいい、わりと中性的な外見をしていた。しかし、彼女には決定的な問題点があった。とてつもなく毒舌なのだ。これでは楽しく話せるわけがない。何か話を振る度に辛辣な言葉で返されるのは御免だ。
俺は期待を一気に打ちのめされた気持ちになって、深くため息を吐く。なってしまったものは仕方ない。せめて彼女の機嫌を損なって、イヤミを言われるような事だけはないようにしよう。そう思った。
席に着きながら、チラと望月の方を見遣る。頬杖を着きながら読書をする彼女の横顔は綺麗だ。綺麗だがしかし、毒舌なのだ。やはり楽しい2ヶ月を過ごすのは難しいだろう。
「……ちょっと。人の顔見て溜息吐くのやめてくれない?」
「へっ?」
いつの間にか俯いていた顔を上げ、声のした方へ振り向く。望月が横目で睨んできていた。呆けた俺の顔を確認して、話にならないとでも言うように首を振りながらため息を吐いた。
「『へっ?』じゃないわよ。あんた、自分の事でしょ」
「あ……と。俺、溜息吐いてたか……?」
「……自覚ないの?」
有り得ない、と言うように望月は眉を潜める。眉間に皺が寄っているというのに、綺麗な顔が崩れる事はなかった。
「はぁ……最悪。あんたみたいな馬鹿が隣の席だなんて」
「なっ……?!いきなりそりゃねーだろ!」
「でも事実でしょ」
「…………」
反論出来ない。けれどしかし、もっと穏便にことを進める事をこいつは知らないのだろうかと思わされる。可愛げがない。女子ならもっと可愛げがあるべきだ。
いよいよ隣の席である事が嫌になってきた。相も変わらず、望月は読書をしている。何を読んでいたって構いはしないのだけれど、少し気になって、中を覗き見てみる。ふと、見覚えのある文字列に目を瞬かせた。
「……なぁ、それって『今年、夏祭りの後で』だろ?」
「え……?」
「あ、やっぱり?」
『今年、夏祭りの後で』というのは、最近流行りの携帯小説が書籍化したもののひとつで、若干サスペンスホラーが混ざっている普通の恋愛小説だ。タイトルを当てたことに驚いたのか、それとも俺が読書をしている事実に驚いたのかは定かでないが、望月は少しばかり驚いた表情を俺へ向けた。俺はしめたと思い、ここぞとばかりに話を振ってみる。
「俺さ、それ予約までして読んだんだ。面白いからあっさり最後まで読んじゃってさー。望月はまだ読み始めたばっかり?」
「……ええ。夏休み前に階段転倒事件が起きた所」
「あー、そこな。やっとサスペンスっぽくなってくるとこでドキドキするよな?」
「……あたしは親友が犯人だと思う」
「へぇー。望月って推理ものは推理しながら読んでくタイプ? 俺全然わかんねーから、そのまま読み進めるんだけど」
「サスペンスは推理してこそでしょ。その醍醐味を楽しまなくてどこで楽しむっていうの」
「え。人間関係とかすっげー見てて面白くね?」
「…………、……そうね。そうかも」
そう言って、望月は本へ視線を戻す。少し考えるように、右手を口元へ遣った。そんな望月の様子を見て、俺は内心ガッツポーズをした。これだけ会話が出来ただけでも上出来だ。それどころか、望月に僅かながらも頷かせることができたのだ。これはとても大きな進歩かもしれない。
そうこうしている内に、先生が教室へ入ってきた。教室のザワつきが次第に収まっていく。間もなくして、朝礼の号令がかかった。
あたしはチャラチャラした男が嫌いだった。ましてや勉強のできないような馬鹿な奴は大嫌いだった。故に、11月の席替えで隣になったのが河野くんだった時、嫌な奴が隣になったと本気で思った。
(――早く3学期にならないかしら)
席替え当日に、既に次の席替えの事を考えていたほどだ。馬鹿な奴とは話が合わない。今までそうだったのだから、これからだってそうに決まっている。
「――それって、『今年、夏祭りの後で』だろ?」
「え……?」
だから。だから、河野くんが本のタイトルを口にした時、あたしは心底驚いた。本の表紙はブックカバーで隠れている。分かるとすれば、中の文章しかない。中の文章を読んで分かるということは、少なくともその場面を読了しているということだ。つまり、河野くんが読書をしているということだ。
「俺さ、それ予約までして読んだんだ」
「…………」
正直、どんな内容であれ「読書」というものをする人だとは思っていなかっただけに、読書をしている事実に驚かされたし、何より、中の文章をきちんと覚えていたことに驚かされた。
あの一件から、あたしの河野くんへの見る目は変わったと言っていい。最初こそ互いに抵抗があったものの、話してみれば意外と気が合う仲で、サスペンスものの小説が好きだったり、漫画では王道バトルファンタジーものが好きだったり、ドラマでは割とベタな刑事ものが好きだったりと、話題が絶えなかった。
「――よって、ここで方程式を使うんだが……」
数学の授業中、俺と望月はノートの端の余白を使い、筆談をしていた。決まった話題があるわけではなかったが、この後お昼ご飯をどこで食べようという話になった。
『食堂で食べたい』
『行くの面倒じゃね?』
『今日弁当持ってきてない』
『何食う?』
『焼きそば』
『女子力ねぇwwwwww』
『煩い。河野くんは何食べるの』
『じゃあ俺も焼きそばで』
『ええ…』
『デザートにパフェ食うわ』
『女子力たかい』
『(・`∀´・)』
俺が顔文字を書いたところで、二人同時に吹き出す。我慢しようとするもしきれずに、クスクスと笑いがこぼれた。
「この4つの方程式の内のひとつを使って解ける。河野、どれを使う」
「!」
「……!!」
俺と望月は筆談していた手を同時に止める。バタバタと慌ててノートを閉じたり消しゴムで消したりしてしまった。名指しされた俺は、よろよろと立つ。
「え、えっと……」
俺は数学が苦手科目だった。黒板を見ても、何が書いてあるのか理解できない。どうしようかと視線を望月の方へと遣る。すると、望月がノートの端に何か書いているのが見えた。「3」と書いてある。
「あー……3番、です」
「3番。正解だ、座っていいぞ」
大きなため息と共に腰を下ろす。望月がニヤニヤした表情で「おつかれ」と口を動かした。今まで筆談中に俺が当てられることは何度もあったが、今回の様に助けられたのは初めてだったたから、若干驚いていた。
(――こいつ、バカには興味ないって言って、冷たい顔してるけど。案外優しい奴……?)
初めての事に驚きを隠せないまま望月をじっと見つめていると、望月は俺を横目で睨んだ。
「……何」
「えっ、あ。いや……」
一瞬言葉に詰まるも、はぐらかす理由もないから、素直に笑って答える。
「その。さっきはありがとな」
「っ……別に」
望月は俺から目を逸らして、そのままノートへと視線を落とす。
(――あれ……?)
そんな望月を見て、胸の奥に若干の違和感を覚えた。
(――今の望月。……なんか、可愛かった……?)
食堂で昼食を取りながら、ふと思い出したように望月が口を開いた。
「そういえばさぁ。遠藤くんがマンガ持ってきてたの知ってる?」
「ん?先生に没収されたとかいうアレか?」
「そう。それがさぁ」
もったいぶってなのか、ずいっと身を乗り出して望月は話を続ける。
「遠藤くん、あんな図体でキッツイ性格してんのに、読んでたマンガが少女マンガだって。あのドキドキ☆プリティウィッチとかいうやつ」
「え、」
「ありえないわ……」と言う望月を目の前に、俺は戸惑う。戸惑うが、しかし黙ってはいられなかった。
「望月。あれは良作だ」
「……はぁ?」
今度は望月が戸惑う番だった。
「は?何言ってんの河野くん。あれは幼稚園児向けのマンガでしょ?」
「確かにあれは幼稚園児でも解るように構成されてるけど!友愛、家族愛、師弟愛、恋愛、いろんな人間関係を詳しく解りやすくどの世代にも通じるように作られた傑作なんだって!」
「愛についてあんなもので語られてたまるか!!」
バンッとテーブルに両手を着いて、望月が勢いよく立ち上がる。一瞬、望月が俺を見下ろす形になったが、すぐに俺も立ち上がり、いつもの目線になった。
「『あんなもの』って言うなよ!主人公のキララちゃんほど純粋で可愛い女の子なんていねーんだから!!」
「あんなぶりっ子ロリが現実にいるわけないでしょ!何、あんたあんなのが好みなわけ?!悪趣味!」
「はぁあ!? 悪趣味じゃねーよ! 男子なら誰だって憧れんだぞ!!」
「ハッ! あれが男の憧れとか世の中終わってるわ!」
お昼時の食堂はいつもわりと騒がしいのだが、二人の良い争いにひとり、ふたり、足を止める人が増えて行き、気が付けば周囲は静かになっていた。
「どこがだよ! お前みてーな女に憧れる方がよっぽど世の中終わっとるわ!」
「うっさい! あんたみたいなヘタレ野郎に憧れる女子だってどーせ居ないでしょ?!」
「うっせーよ! じゃあなんだ? 理想の男性像とかあんのかよ!」
「あるわよ! あんたみたいなヘタレじゃなくて! 頭脳明晰運動神経抜群ファッションセンスも良くて社交的で料理上手! 責任感と正義感が強くて、強引なところもあるけれど芯が曲がってない人!!」
「んな完璧なヤツ現実にいるわけねーだろ! 現実見ろよ現実!!」
「はぁ?! あんたに言われたくないわよ! あんたこそ現実見たらどうなの?!」
「俺は……!」と口を開きかけたところで、互いにハッとする。食堂にいる人間のほとんどの視線が俺たちに注がれていた。
(――うわ……すっげー見られてる……)
俺が周囲の視線に唖然としていると、ダンッと鞄をテーブルに打ち付ける音が聞こえて、そちらへ顔を向ける。望月が食堂を出て行く後姿が目に映った。
「…………」
俺には、望月を止める術が無い。止める理由も無い。何しろ、自分もここにいるのが居た堪れない。
(――……あんなにムキにならなくたっていーじゃねーか……)
相変わらず突き刺さるような視線を感じながら、俺も食堂を後にした。
あれから一週間。俺は望月と一言も口を利かなかった。すれ違う時も、隣の席に着く時も、目を合わせることもしなかった。
しかし、一週間もすれば、疲れてくる。どうにも、居心地が悪い。
(――どーしてこんな、意地張ってんだろーなー……)
意地を張り過ぎている自分が腹立たしくて、俺はイラついていた。自分から折れたっていいじゃないか。何も競う事なんてないじゃないか。
(――……よし)
教室に入って、あいつが居たら謝ろう。あいつが後から来ても、謝ろう。食堂での一件について、ちゃんと謝ろう。そう思って、俺は教室に入った。
入って先ず、席を見る。望月は――席に着いていた。そのまま自分の席へと向かう。自分の席の椅子を引く。腰を下ろせば、「おはよう」と言った。望月からの返事は無い。耐え兼ねて、望月の方へ向きながら俺は口を開いた。
「なぁ、望月――」
「話し掛けないで」
「…………」
一刀両断される。そうしてそのまま、朝礼の号令が掛った。
(――一週間経っても口利けねーとか、なんか……)
「やだなぁー……」
ため息交じりに愚痴を零しながら階段を上がる。踊り場に上がりきったところで、下りてくる人物に気付いて、ドキッとする。望月だ。幸いかどうか解らないが、望月は俺には気付いていないようだった。俯き気味の浮かない表情のまま、若干覚束ない足取りで階段を下りている。俺は声を掛けようかと口を僅かながら開くも、声が喉につっかえて出てこず、やれと首を振った。
「――っ、」
「……え、っ」
自分も階段を上ろうとした、その時だった。望月が段を踏み外し、踊り場へ落下してくる。俺は慌てて両手を広げた。ほんの一瞬の出来事だった。
「――――ってぇー……」
「…………、……」
尻もちをついたためか、若干尾てい骨が痛い。否、そんなことよりも、望月は大丈夫かと腕の中の人物を覗き込む。
「あっ……」
「…………」
ばっちりと視線が合う。そうして、望月は慌てて俺から離れた。俺は床に座り込んだまま、望月を見てしまう。
(――望月が、泣いてる……?)
プライドの高い望月だ。ここで泣いているなんて言えば、怒るに決まっている。そっとしておこうと思い、まだ少し痛む腰を押さえながら、俺はよろよろと立ちあがった。
「別に礼は要らねーから」
その場につったって俯いたままの望月の横を過ぎつつ、俺は声を掛ける。
「ぼーっとしてねーで、気を付けろよ」
「――ぁ……」
俺はそれ以上何も言わず、階段を上がって行く。
(――望月は、全然素直じゃない。目だってキツイつり目だし、口を開けば毒ばっかりだ)
あたしは、その場から動けずにいる。
(――河野くんは、全然かっこよくない。いつだって優柔不断だし、頭悪いし、真面目な話が通じない)
俺は振り向かず、階段を上がって行く。
(――一度機嫌を損ねたら、こうやって中々口利いてくれなくなるし。真面目すぎるし)
あたしは、その場から動けない。
(――別に運動が得意なわけでも、何か特別り柄があるわけでもない)
(――でも、)
俺は思う。
(――これって、まさか……)
あたしは思う。
(――これってもしかして……)
――――好き、なのかも……?
[/font]