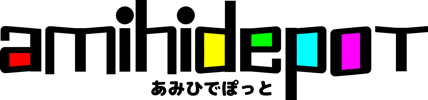[font]
「私の今までの恋愛って『逃げ』だったのかな」
「逃げ、ですか?」
「うん。『男は怖い』っていう先入観が働いて、男の人と関わること自体から逃げてきてたんじゃないかなって、思って。男の人と関わらないから、必然的に女の人としか交友関係がなくなって、好きとか嫌いとか、女の人との間でしか考えられなくなってたんじゃないかなって、思って。男の人と恋愛できないから、言い訳みたいに、女の人に逃げてたのかな、って」
「それが女性を好きになる理由なのは、何もおかしくないと思いますよ?」
「え?」
「男の人が苦手だから女の人に恋愛してきたってことですよね? そういうこと、普通にあると思いますけど」
私が「悪いこと・いけないこと」と思っていた部分を、小田さんはすんなりと、あっさりと肯定してくれた。私が男の人を苦手でいることも、女の人にばかり恋をしてきたことも、否定せず、受け止めてくれた。
「過去は過去、今は今です。今は僕と付き合ってるんですから、僕のこと見てくださいよ~」
そう言って、私の手を握りながら、小田さんは笑う。その笑顔が、かわいい。今すぐにでも押し倒したいくらいだ。――ああ、まさか私が、男相手にこんなことを思うなんて。私のこの気持ちは、嘘では、ないよね。
***5話***
小田さんと交際を始めて3ヶ月、8月の第1土曜日。夜8時。私たちは小田さんの家で、一緒に晩御飯を食べていた。
「あ、おいしい」
「えへへ、よかったあ」
小田さんが作ったオムライス。卵の中はケチャップたっぷりの、しっかりコショウもきいたチキンライス。母が作ったのよりも塩辛さがあって、私は好きな味だ。
「料理できるのいいな」
「篠田さん、料理苦手なんですか?」
「んー、多分。全然しないので」
「へえ。じゃあ、料理は僕の担当ですね」
「ん?」
「担当」と言われて、私は首をかしげながら小田さんを見る。小田さんは私の視線に気づき、それからハッとしてオムライスを頬張っていた手を止め、左手を顔の前で横にブンブン振った。
「ん、んっ! あっ、いや、もしその一緒に住んだりとかしたら、とか、っていう、その」
「ああ」
なるほど。小田さんはそこまで、将来のことを考えているらしい。それだけ私と真剣に交際してくれているということだろう。対して私は、学生がするようなふわふわした恋愛の感覚でいて、将来のことを考えられていなかった。
「ありがとうございます、真剣に思ってくれて」
なんと返したらいいかわからなくて、思い浮かんだ言葉をそのまま口にする。チラッと小田さんへ視線を向けると、照れたように少しほほを赤らめながら、もくもくとオムライスを頬張っていた。
6月に初めて小田さんの家を訪ねて以来、毎週土曜日の夜8時から、ここへ来て1時間ほど話すようになった。そうして気付いた――SNSのやり取りだけでは気づかなかった、小田さんの癖がある。小田さんは、恥ずかしくなるとすぐに顔が赤くなる。多分これまでも、ヘアサロンで会話していたときも、きっとこんな感じですぐに赤くなっていたのだろうけれど、そんなふうに気にしたことがなかった。それから、口ごもるときは大抵、ゆるく握った左手を口元に当てる。女の子みたいなしぐさだなと思っていたけれど、小田さんがやると様になって、とてもかわいい。照れて肩をすくめるときは、少しだけ首をかしげながら右肩が高く上がるし、悩みごとがあるときは、決まって両手を握ってもじもじしている。そういうところも、かわいいと思う。――小田さんに対して「好き」という感情を自覚してからというもの、私は小田さんにどんどん惹かれていた。
お互い食事を終えて、作ってもらったお礼にと私が食器を洗う。片付けは勝手がわからないだろうと、小田さんがしてくれた。すべて片付け終わって、ソファーに二人、並んで座る。
「あの、篠田さん」
「はい」
何も話すことがないと思って、無言の時間を覚悟していた矢先。さすがは美容師、小田さんが口を開いた。
「最近、敬語取れてきましたね」
「えっ、すみません」
「あ、いや、僕はうれしいです!」小田さんは慌てたようにパタパタと両手を振って、それからうつむいて、視線をそらす。「篠田さんの敬語は、なんか、遠慮してる感じがして、僕、寂しかったから……」
「遠慮……」
小田さんの寂しそうな顔を見て、ふと、友人の日野 明日香との昔の会話を思い出す。
――亜子ってさ、敬語で他人と距離取っとるよね
――なんか、亜子に敬語で話されると、それ以上近付けんっていうか、仲良くなれんって感じする
「……ごめん」
小田さんも、明日香と同じように思っていたのだろうか。申し訳なさと、笑ってほしい気持ちが胸の奥に生まれて、小田さんの――最近、イエローアッシュに染め直したばかりの――ふわふわの頭を撫でた。手が頭に触れた瞬間、小さく小田さんの肩が跳ねる。
「っ……え、あ」
びっくりした視線を私に向けて、みるみるうちに赤くなって、左手で口元を抑えた。キュッと細まった目が、縋るような、ねだるような色に変わる。その目に、思わず私はドキッとする。ああ、ダメだ。私、小田さんのこの目に弱い。
「……えっと」目をそらしながら手を引いて、私は言葉を探した。「小田さんも、タメ口で、いいから」
「はい……あ、うん」
小田さんの頷く声が聞こえて、それからお互い、無言になる。さすがに、気まずい。何か話そうと言葉を探したけれど、やはり先に口を開いたのは小田さんだった。
「あ、あの。篠田さん」
「ん?」
「名前で、呼んでも、いい?」
「え? うん」
特に嫌がる理由もなくて、了承する。顔を向けると、小田さんは居住まいを正して――ソファーの上で正座になって、こちらを向いていた。その姿に、思わず吹き出してしまう。
「っな、わ、笑わないでくださいよ!」
「いや、ごめん。かしこまってるの、おかしくて」
おかしい。けれど、こんなに真剣に私に向き合ってくれる姿が、かわいい。小田さんを真似て、私も居住まいを正す。ソファーの上で正座をした二人の膝がぶつかる。
「私も名前で呼んでいい?」
「う、うん」
「じゃあ、『琴くん』って呼ぶね」
「はいっ」
「ふふっ」
名前を呼ばれただけで赤くなる小田さん――否、琴くんを見て、また、つい笑ってしまう。本当に、かわいらしい。
「あ……亜子さんっ」
「何?」
名前で呼ばれて、少し、嬉しい。私は琴くんの言葉の続きを待った。
「……も、もう一回、撫でて……?」
言葉と同時、琴くんの右手は私の左腕の袖を摘まんでいた。ああ、こういうところだ。この子は、こういう甘え方を素でやってのける。それがとてもかわいい。私は言われた通り、琴くんの頭を撫でる。琴くんは、今度は目を閉じて、気持ちよさそうに笑みを浮かべた。
「じゃあ、あの時の美容師と付き合っとるん?」
「うん」
翌週の土曜日の昼間、私は久しぶりに駅中の喫茶店で、日野 明日香と会っていた。アイスコーヒーを飲み干して、少し物足りないから何かサイドメニューでも頼もうかと、テーブルに立てかけてあるメニュー表を開く。
「へえ。写真とかないん?」
「店のサイト見たら出てるんじゃない?」
「いや、自撮りとかないん?」
「ないよ。私が写真好きじゃないのに」
明日香は「つまらん」とか言いながら、スマートフォンを触る。
「名前なんだっけ?」
「ヘアサロン『パレット』の小田さん」
「んー……え、この人? 女子じゃなくて?」
顔を上げると、明日香がこちらにスマートフォンの画面を向けていて、私はそこに表示されているものを確認する。そこには琴くんの簡単なプロフィールが書かれていて、添えられている顔写真は確かに、ボーイッシュな女性と見まがうほどかわいかった。元の顔も確かに女性っぽいし、さすがだなと感心する。
「女の子みたいに顔も名前もかわいいけど、ちゃんと男だよ」
「ええ、これで男? ほんまに?」
「ほんとだって」
「ええー、かわいすぎて逆に無理」
「ちょっと失礼なこと言わないでよ」
「いや、普通思うって。ほんま女子じゃん」
これは、琴くんが聞いたら喜ぶだろうか。それとも悲しむだろうか。
「これで結婚はきついなー」
「ちょっと明日香さっきから失礼すぎる」
「いやだって、うちじゃったら自分より女子みたいな男のとなり立つんプレッシャーじゃし。結婚ってなったら、毎日自分よりきれいでかわいい男と顔合わせるんよ? きつくない?」
「私はそうは思わないけど」
「ふーん」
明日香とは価値観が合わないし、受け入れてもらえるとは思っていなかったけれど、こんな風に琴くんのことを言われるのは腹立たしかった。別に、琴くんがかわいくありたいなら、それでいいじゃないか。なぜ、自分とわざわざ比べる必要があるのだろう。
「てゆーかさ、うちらもいい年じゃん。結婚の話とかちゃんと考えとるん?」
「全然。向こうはわかんないけど」
「ふーん。ちゃんと話したほうがええんじゃないん? この年になって恋愛で遊んどる時間ないじゃろ」
「わかってるよ」
恋人のいない明日香に、なぜ私はこんなことを言われなければならないのか。実に不快だ。けれど――言われていること自体は、間違いではない。
「じゃあさ、亜子」
「ん?」
「小田さんとどこまでやったん?」
「……あんさあ別にそれ聞かんでよくない? ほんまさっきから失礼なんじゃけど」
むっとして、メニュー表から顔を上げて明日香を見る。視界に入った明日香は驚いた顔で私を見ていて、それを3秒ほど見つめた後、私はその表情の意味に気付いた。思った以上に苛立って、いつも抑えている方言が出てしまったのだ。
「……ごめん。私のこと心配してくれてるのに」
「いや、うちこそごめん。そういうこと知りもせんで彼氏もおらんのに、余計なこと言うた」
明日香が心配してくれている気持ちはよくよくわかって、私はこれ以上、明日香のことを悪く思えなかった。恋は盲目とも言うし、きっと琴くんが私と不づり合いなほどかわいいから、いいように付き合わされているだけなんじゃないかとか、もし本気ならちゃんと将来のこと見据えているのかとか、それなりに段取りを組んで関われているのかとか、そういうことを言いたかったのだろう。けれど、そう、明日香が言った通り、私たちはもう“いい年”なのだ。
「……将来のことはまだ見えてないし、三十路で、確かに焦る気持ちもあるけどさ。こればっかりは、焦ったってどうにもならないよ。恋愛して遊んでる余裕がないのもよくわかる。けど、だからって、この恋愛がちゃんと結婚につながるかどうかは、続けてみないとわかんないし」
「うん」
注文する気がなくなって、メニュー表を閉じながら、私はため息交じりに言葉をこぼす。
「向こうは、すごく真剣に私のこと考えて、向き合ってくれてるよ。恋愛経験が乏しいのも、男嫌いでどういうのが苦手だっていうのも、すごく気にしてくれてる。そこまで真剣になれてないのはむしろ私のほうで、向こうは私のペースに合わせてくれてるだけ。だから、そんなに心配しなくて大丈夫だよ」
「そっか」明日香は私の言葉に納得したようで、一つ頷いた。「よかったなあ、亜子。いい人に会えて」
「まだ分かんないよ。結婚してからも、離婚せずにいられるかどうかなんて分からないし」
明日香は、自分の前に置かれていたアイスカフェラテを飲んでから、小さくため息をつく。
「それも考えて付き合っとるんじゃろ?」
「まあね」
「いいなあ……。うちも恋愛頑張るわ。亜子がおらんなったら遊べる人おらんし」
そう言って、明日香はさばさばした笑みを浮かべた。
4時も過ぎたしそろそろ帰ろうかと、喫茶店を出た。駅の北口で明日香と別れた直後、聞き慣れた声に呼び止められる。
「亜子さん?」
振り返ると、琴くんがいた。
「あれ。琴くん」こんなところで会うとは思わず、驚いてしまう。「仕事は?」
「ああ。駅前店のヘルプが終わって、本店に戻るとこなんです」
「そうなんだ」
複数の店を行ったり来たりするのは大変だろうな、と、ぼんやり思う。琴くんは少し視線をそらして、何か言いたそうに胸元で両手を握っていた。
「あ、あの……亜子さん」
「うん?」
「……さっき一緒にいた方は、お友だち、ですよね」
「うん、そうだけど」
声をかけられたタイミングからして、きっと明日香のことだろう。何か気になることがあっただろうかと首をかしげる。
「です、よね。ごめんなさい、なんでもないです」
琴くんは、目線をそらしたまま小さく首を振って、笑顔を浮かべた。今までに見たどの笑顔とも違う、違和感のあるその表情に、私は自分の眉が寄るのを感じた。
「何でもないこと、ないよね」
私の声に、琴くんの顔が悲しそうにゆがむ。そうして、一度目を閉じて、悲しそうな表情のまま、私へと視線を向けた。
「すいません。夜、話させてください。本店に戻らないといけないので」
「……はい」
とても暗い、もやっとしたものが胸の中に渦巻く。足早に駐輪場へと向かう琴くんの後ろ姿から、しばらく視線を外せなかった。
夜8時半過ぎ。『すみません。今から帰ります』という琴くんのメッセージと、泣きながら手を合わせる熊のイラストが送られてきてから、もうそろそろ15分が経つ。私はずっと、青いドアに寄りかかりながら、昼間の琴くんを思い出していた。――あの表情の意味は、いったい何なのだろう。いつも明るい琴くんのあんなに悲しそうな表情を、今まで見たことがなかった。
バタバタと階段を駆け上がる音が耳に届いて、私はドアから体を離す。音のした廊下の先を見ると、琴くんが速足でこちらへと近付いてきていた。
「ごめんなさい、遅くなって……」
「いや。お疲れ様」
琴くんの表情は相変わらず陰っていた。何なら、私と目が合ったことで、今にも泣きだしそうな顔になった。私はどんな表情を返していいのかわからず、うつむいて、琴くんの背中をたたいて中に入るよう促す。私たちは無言で家に入り、明かりをつけて、いつもの場所に腰を下ろした。
「……琴くん」
「はい」
隣に座る琴くんへ視線を向ける。表情は相も変わらず悲しそうに影を落としたままで、こちらへと視線を向ける気配がない。私は少し迷ってから、左手で、琴くんの右手を握った。一瞬だけ、琴くんの右手が震える。
「……昼間、何が気になったの?」
「……」
沈黙。いつぞやの、私に告白しようとしていたときのような、言葉を必死に探しているような、そんな感じだった。急かさず、何もせず、ただじっと待っていると、琴くんは深く息を吐いてから、ゆっくり口を開いた。
「……あのとき、亜子さん、すごく、仲良さそうだったから。やっぱり、男の僕じゃ、ダメなのかなって……」
「えっと……、なんで?」
「だ、だって」琴くんの声が、つないでいる右手が、震える。「だって……男の人には恋できないって、女の人にしか恋したことないって言ってたから……僕、男だし。やっぱり勝ち目とか、ないんじゃないかって……」
琴くんに言われて、私はハッとする。そもそも私の恋愛対象は、これまで女性がほとんどだった。この3ヶ月、そのことを琴くんに話してきたし、琴くんもそれを受け入れてくれていた。だからこそ琴くんは、私の基本的な恋愛対象は“女性”で、“男性”である自分への好意はイレギュラーなものだと認識している。どうしてそのことに気付けなかったのだろう。今まで散々、こんな状況、BL漫画で読んできたというのに。やっぱり男の俺じゃだめだとか、女子には敵わないとか思って、葛藤する男たちを見てきたというのに。そんな気持ちを、今、目の前の恋人は抱えているというのに。
「……ごめん、不安にさせて」
琴くんは、私の言葉に力なく首を振る。
「僕こそ、ごめんなさい。お友だちなんだから、仲良くて当然、なのに……」
うつむいたままの琴くんの顔を見る。不安そうな色は、その表情からは消えていた。けれど、まだ何か、引っかかっているような、不機嫌そうな顔をしている。
「……もしかして、嫉妬してくれてるの?」
琴くんは驚いたように顔を勢いよく上げて、身を引いた。私の左手が引っ張られる。
「そっ、そんなつもりじゃないんです! 嫉妬なんてされても負担になるだけだし嫌な気持ちになるし亜子さんに迷惑かけたくないから! ごっ、ごめんなさっ……」
「ちょっ、悪いことなんかじゃないって」
左手が引っ張られた勢いで琴くんに被さりながら、私は言われた言葉に顔をしかめた。
「でも」
「でもじゃない」
琴くんがまだ何か言おうとするのを、私はさえぎる。
「わかるよ。嫉妬したくてしてるんじゃないって、どうしようもない気持ちだって。だから自分を責めないで。嫉妬して負担に思われたらどうしようとか、嫌われたらどうしようとか、そんなふうに思って、怖がって、気持ちを抑え込まないで。そんなことしたらもっと苦しくなるし、お互い傷付くだけだから。私も、そうだったから」
“あのとき”は、付き合ってなかったけれど。まだ、恋心だとさえ自覚していなかったけれど。私もそうだったから。今、私たちは、「恋人でもないのに」と否定された、拒絶されたあのときとは違うから。付き合っている私たちなら、この感情は、許されるはずだから――――。
忘れたい記憶と感情が胸の奥で起き上がってくるのを感じながら、私はまっすぐ、琴くんを見つめた。
「……嫌じゃない?」
琴くんの目が、また、不安そうに、縋るように揺れている。
「嫌じゃないよ」
私はため息交じりに、笑って見せる。
「じゃあ……」少し口をとがらせながら、上目遣いになりながら、琴くんは小さく言葉をこぼす。「不安にならないように、ぎゅーって、して」
琴くんの言葉に、私は目を瞬かせた。いつもより強引なねだり方が、少し、意外だったから。いや、それだけじゃない。その言葉以上に、何か求められているような気がしたから。――琴くんの体にまたがるように覆いかぶさって、私は、上からじっと、琴くんの目を見つめる。
「……ハグだけで、安心できるの?」
私の言葉に、琴くんの両目は大きく見開かれる。そうしてすぐに赤くなって、逃げるように、視線がそれた。小さく、首が横に振られる。
「なら、何してほしい?」
今度は、ジトっとした視線がこちらに向けられる。
「……恋人だからできること、したい」
まるで「いちいち聞くな」と言っているような視線と声。そんな視線と声に、私は腹の底から湧いてくる熱いものを感じた。そうして思うままに、私は、琴くんの両肩に手を掛けて、押し倒す。
「――好きだよ、琴くん」
交際を始めて3ヶ月。私は初めて、小田 琴という名前の恋人に、「好き」と言った。
[/font]