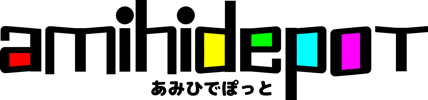[font]
「僕、『俺』って一人称、使いたくないんですよね。かわいくないし、なんか偉そうだし」
「そうですか? んー……まあ、言われてみれば確かにそう、かも」
「でしょ? でも、『私』だと、なんだか丁寧な感じで、業務的……じゃないけど、堅苦しいっていうか。だから僕は、『僕』って言ってるんです。響きもなんか、かわいいし」
小田さんの考えは、とにかく「かわいい」が中心にあって、ぶれることがない。そんな姿がかわいいと言ったら、私が小田さんを好きだと勘違いさせてしまいそうだから、言わないけれど。でも、なかなかに、かわいいと思う。
そう、かわいいとは、思う。けれど――私はちゃんと、小田さんを好きになれるのだろうか。
***4話***
小田さんと交際することになって1ヶ月。毎日少しずつ、SNSでメッセージのやり取りをした。そして毎週、日曜日の夜、小田さんが仕事を終えた後に3時間ほど通話をした。男友達のいない私にはよくわからないけれど、これはちゃんと「付き合っている」ことになるのだろうか。仲の良い女友達――日野 明日香とは、毎週のように連絡を取り合って、毎月のように遊んでいるし、体感としては、小田さんとの付き合いは「友達」と大差ない。強いて「友達」と違うことを挙げるなら、お互いのことを話して、理解し合う“作業”をしていることくらい。
最初は、お互いの家族について話した。
『僕はお姉ちゃんが2人です。上が36歳で、下が32歳』
「結構離れてるんですね」
『そうですか? ……あっ、どっちも結婚してるんですけど、よく家族ぐるみで一緒にご飯食べたりしてるんですよ。多分、お義兄さん同士も仲いいんじゃないかな』
「へえ。家族ぐるみで仲いいの、羨ましいです」
『篠田さんとこは、仲良くないんですか?』
「そう、ですね……。母とは、それなりに仲いいんですけど。父は、よくわからないです。典型的な昭和の、怒鳴るたたくの厳格な父で、あまり話さなくて……」
『えっ……DV、ですか?』
「ああ、いえ。あれはしつけの範囲内だと思います――とはいえ、昔の話なので、今の感覚で言えば、確かにDVかもしれないですけど――。それに、母子家庭で育った分、苦労を知ってるから、家事は率先してするし、家庭は大事にしてくれてるし、そういうところは尊敬してます。私自身、すごく大事に育てられたことも覚えてるので、怖いとは思いますけど、嫌いというわけではないです」
『うーん……怖いとは、思うんですね』
「はは……ええ」
『じゃあ、なんで、仲良くないって思うんですか?』
「……今年28になる弟が1人、いるんですけど。相当、嫌われてるので」
『そうなんですか? 篠田さん、面倒見良くていいお姉さんに見えるけど』
「いい姉ではないですよ。ずっと、『お前みたいな勉強のできないクズにはならない』って罵られてましたから」
『うわ……弟さん、ひどいこと言いますね』
「ええ、本当に。浪人して大学に行ったのが許せなかったみたいです」
『うーん……弟さん、真面目なんですね』
「はは。確かに、真面目ですね」
小田さんの家庭はきっと、小田さんの性格から想像が容易い、何でも受け入れてくれる優しいものなのだろうと思った。対して我が家は厳格で、小田さんにはいろいろと窮屈だろうとも思った。勉強の苦手な私は、いつも父に怒鳴られていたし。そんな私の姿をいつも見ていた弟からは、罵られて、見下されて、「俺はお前みたいな勉強のできないクズにはならない」と言われ続けていたし……。私が男嫌いになった一番の要因は、父と弟からの、こういう態度や、暴力だと、自覚している。
『……だから、男の人が苦手なんですね』
「ええ。本当にそれが原因かどうかは、わからないですけど。少なくとも、私はそう自覚してます」
『篠田さんがそう思うなら、きっとそうなんですよ』
別の日には、自分の性を意識したときのことを話した。
『僕、お姉ちゃんたちが可愛い服を着てるのがうらやましくて、ほんとに女の子になりたいって思った時期もあったんです。女の子になれば、お姉ちゃんたちと同じように、いっぱい可愛い服が着れるから、って』
「男の子だけどスカートを履きたいとか、そういう?」
『うん、それもありました。あっ、でも、心は男のままがいいって、中学のときに気付きました。ただかわいい服を着たいだけ、見た目がかわいくなりたいだけで……』
「なるほど。……そういえば小田さんて、顔と服のバランス取れてて、ほんとにかわいいですよね。なんというか、無理してない感じ」
『ほんとですか?! えへへ、嬉しいな……。なんか、一箇所どこかだけ頑張っても、見た目、かわいくなくなっちゃうんですよね。どこか頑張るんだったら、ほかも頑張らないと』
小田さんは、もとの顔がきれいだからか、肌の手入れもきちんとしているからか、ナチュラルメイクはバッチリ決まっていて、それでいて違和感がなかった。どうかすると、アイドルみたいだとも思った。痩せて骨張っているわけでもなく、ほどよく肉がついていて、柔らかい丸い顔をしているし、私なんかより全然かわいい。そこらの女の子にだって負けないくらい、かわいい。
『自分で、自分のこと、おかしいのかなって悩んだ時期もありましたけど……最近のメディア、トランスジェンダーの人とか、ゲイの人とか、女装家の人とか、ジェンダーレスの人とか、いっぱい出てるじゃないですか。だから、あんまり悩まずに、簡単に答え、出せたんですよね。今はちゃんと、見た目も中身もかわいいと思われたい、かわいくなりたい“男”だって、理解してますよ』
そうやって理解できていることが、私には羨ましかった。
『僕は、自分の性は男で、好きになるのは女性です。自分がどれだけかわいくなっても、男を好きにはなれないし、自分から男を捨てることもできないです。男の体のまま、もう少し可愛い体に生まれたかったなーとは、思うけど……この体はちゃんと“僕”なので、手術してまで変えたいとは、思ってないです。――篠田さんは、どうですか?』
「え……どう、とは?」
『男になりたいとか、そういうの、ありますか?』
私は、どうなのだろう。小田さんのように、心と体が違うことを望んでいるだろうか。同じなのだろうか。
「んー……どう、でしょう。なくは、ないかもしれないですけど。今の自分に違和感を感じたことはないし、あまり、意識することもなかったので……」
考えてみたけれど……どうしたって私は女だし、女の体だった。
『じゃあ、篠田さん自身は、心も体も女性なのかもですね』
「そう、ですね」
この先、男の体を望むことは、あるのだろうか。それは、わからなかった。
また別の日には、昔の恋愛について話した。
『篠田さんは、その……昔、誰かと付き合ったこと、ありますか?』
「あるにはありますけど、突然ですね」
『ご、ごめんなさい! そりゃあ、お付き合いの経験くらいありますよね……。すいません、失礼なこと聞いて……』
「いや、失礼だとかそんなことはないですよ。ただ、まあ……あれを、付き合ったと表現していいのかどうか……」
『……あの。どんな女性だったとか、聞いても、いいですか?』
「別にいいですけど。付き合ってたのは、男性ですよ」
『えっ!? だ、大丈夫だったんですか?』
「ええ、まあ。小田さんとは違うタイプの人でしたけど、とても柔らかい雰囲気の、優しい人でしたから」
『そうですか……』
大学のとき、同じ学科だった、同級生の松本 聡太くん。今どきの細身の男の子で、おとなしいけど、話すと面白くて、割とおしゃれで、清潔感があって、背が低かった。いい人だった。
「怖いと感じない男の人が珍しかったので、私から、よく話し掛けてたんですよね。それで、仲良くなって。“友人”の延長線上に“恋人”って関係が見えて、この人なら大丈夫かもしれないと思って、私から告白したんです」
『……どうして、別れたんですか?』
「友人の関係から、発展しなかったから、ですね。私は会話だけで満足してて、手をつなぐことも、望んだりしなかったので。友達以上恋人未満っていうのかな。友だちと変わらないね、ってなって。じゃあ、付き合うの止めよう、って。ただの友だちに戻ろう、って。それで、別れました」
別れたときのことを思い出して、そのときよぎった不安を、私は口にした。
「……だから、正直、小田さんとの今の関係も、いつまで続けられるか、不安なんですよね」
『ぼ、僕は……』
「ん?」
『僕は……篠田さんとは、手を繋ぐとかだけじゃなくて。それ以上のこと、したいです』
小田さんが思いの外真剣な声で、そうはっきり言ったことがおかしくて、私は思わず笑ってしまった。
『な、なんで笑うんですかっ!』
「ごめんなさい、悪気はなくて……。ただ、今までそういうこと、誰に対しても想像したことなかったから。そんなにはっきり言えるものなんだな、って」
『……だって。僕、何度もイメトレしましたもん……』
「私相手に?」
『篠田さん以外に誰がいるんですか!』
「ははは……」
『……僕じゃ、やっぱり、ムリですか?』
「何がですか?」
『その……手を繋ぐ以上のこと、するのは』
「……どう、でしょう」
そもそも私は“そういうこと”を、誰相手にも想像したことがなかった。
『想像するのも、難しいですか?』
「いや……想像するくらいなら容易いと思いますよ、したことがないだけで。ただ、実際にできるかどうかは、試してみないことには……」
『……じゃあ、試してみますか?』
「え?」
『来週……僕と』
「……」
『……』
それは、とても急な話だった。それまで考えたことのなかった出来事で、心の準備もできていなかった。それでも。
「……いいですよ。土曜日なら、いつでも」
『えっ、あっ……、じゃ、じゃあ……夜、8時でも、いいですか?』
「ええ。小田さんはお仕事ですもんね。大丈夫です」
それでも拒否しなかったのは、きっと、小田さんを受け入れたい気持ちが、どこかにあったからだと思う。――これが、小田さんとの交際の、1ヶ月。
6月頭の土曜日。夜8時。駅前の広場で、私は小田さんを待っていた。周りでは学生らしい人たちが騒いでいて、車の往来も激しくて、とても騒がしい。あまりこういう場所には来ないからか、喧騒さえも私には新鮮だった。
「篠田さんっ、お待たせしました!」
聞こえた声に、足元へ落としていた視線を上げる。少し肩で息をしながら小田さんがこちらへ走ってきていた。
「すいません、遅くなって……」
「いえ。まだ8時過ぎたばかりですからそんなには」
「もう10分過ぎてますよ!」
「そんなに気にしないでください、仕事でしょう?」
「うう……そうですけど……すいません」
息を整えてから、小田さんは遠慮がちに笑う。
「じゃあ、行きましょうか」
小田さんは体の向きを変えて先に歩き出した。私はすぐに後を追って、小田さんの右隣に並ぶ。顔を見ていないのにそわそわしているのがわかって視線を左へ向けると、小田さんの右手が開いたり閉じたり、持ち上がったり下りたりしていて、何かを迷っているようだった。
「……手、つなぎますか?」
「あっ……」
顔を見て尋ねると、小田さんは驚いた顔でこちらを見た。それから視線がゆるゆると下へと落ちて、二人の手を見つめる。しばらく黙った後、「お願いします」と言いながら、開いた右手がこちらへと伸ばされた。私は黙って、伸ばされた右手を左手で握る。不思議なことに、私の左手の中に小田さんの右手があることに違和感はなかった。少しだけ、ぎゅと小田さんの手に力が入るのを感じる。それからは、お互い黙って歩いた。
駅から5分ほど歩いたところで、「藤田ビル」と大きく書かれた古いアパートに着く。赤レンガでできた壁に、青いドアと、白いフェンスで囲まれた外階段。8階建てだけれどエレベーターはない――洋風の外観でとても目立つ、昔から有名な建物だ。小田さんは躊躇なく入り口の赤レンガの階段を上り、そのまま外階段を4階まで上る。そして、突き当りの部屋まで歩き、立ち止まってから、私の手を放した。鍵を開けて、青いドアを開く。
「どうぞ、入ってください」
「……お邪魔します」
玄関へ足を踏み入れる。ふわっと甘い香りがして、それが小田さんの匂いだと、すぐにわかる。靴を脱いで上がると、扉が閉まり、施錠する音がして、照明が点いた。
「どうでした?」
「え?」
靴の向きを直していると、上から小田さんの問いかけが降ってくる。「何がですか?」と首をかしげると、小田さんは靴を脱ぎながら、困ったように笑って言った。
「手、繋いだじゃないですか」
「ああ。いや、どうと言われても……」
「嫌じゃ、なかったですか?」
「ええ」
言われた通り、嫌ではなかった。むしろ、小田さんの右側にいることに、安心感さえ覚えた。
「よかったあ」
小田さんはほっと胸を撫で下ろした様子で、そのまま部屋の奥へと入っていく。私は小田さんの後ろに続いた。
「すいません、ソファー座って待っててもらえますか?」
「はい」
私は言われるまま、部屋の真ん中に置かれている座椅子のような二人掛けのソファーに腰を下ろす。小田さんはかばんを壁際の本棚の上に置いてから、キッチンへと入って行った。
ぐるっと、そう広くない部屋を見回す。シンクで部屋とキッチンが区切られた1DK。黄緑色の無地のカーテン。小さなテレビと、ピンク色の天板の小さな折り畳み式テーブル。オレンジの水玉模様の掛布団が広げられたベッドと、その上に置かれたカエルらしきキャラクターの巨大なぬいぐるみ。小さな本棚には雑誌や書籍が並べられている。大きな観音開きの鏡が乗った、引き出しが3段付いた化粧棚もある。クローゼットは備え付けのようだ。
「篠田さん、もう晩御飯は食べました?」
シンク越しに小田さんの声が聞こえる。私は部屋の観察を止めて、小田さんがいるであろうキッチンを見た。
「ああ、はい。小田さんは?」
「これからなんですよ~。すいません、食べてもいいですか?」
「もちろんですよ」
きっと、仕事が終わって直接、私を迎えに来てくれたのだろう。なんだか申し訳ない。少し、居心地の悪い無言の時間が流れる。
「あの、篠田さん」
「はい」
しばらく無言の時間が続くと覚悟していたのに、小田さんはまた話しかけれくれる。さすがは美容師だ。私はまた、小田さんがいるであろうキッチンを見た。
「さっき、僕の右側に立ったの、何か理由がありますか?」
「え? いえ、特には……なぜですか?」
「前に付き合った人はみんな、僕の左側に立ってたので、ちょっと気になって……あっでも嫌だとかそんなのじゃなくて、すごく居心地よかったです。すごく安心できたっていうか、違和感がなくて。それが定位置、みたいな?」
「……そうですか。私も、小田さんの右側、違和感なくて居心地よかったですよ」
「ほんとですか!?」
がばっと、小田さんはシンクから身を乗り出してくる。そんなに驚くことだろうかと、私は首を傾げた。
「ええ。……何か、気になります?」
「いや……、えへへ」
「うん?」
急に照れ笑いをする小田さんに、私は意図が読めずに顔をしかめる。小田さんは少し困ったように眉尻を下げた。
「へへ……すいません。僕たち、相性いいのかなーって思ったら、うれしくて」
そう言って、小田さんはキッチンに引っ込む。私は不意を突かれた気になって、言葉を失ってしまった。私たちの相性がいい? 本当に? 小田さんの言葉に首をかしげていると、電子レンジが鳴って小田さんがバタバタと動く。すぐに、温まったカレー1皿と水の入ったコップを2つ乗せたトレー持って、私の左隣に腰を下ろした。私はその瞬間、左隣に座った小田さんを見て思う。
「……確かに、並びの相性はいいかも」
「ほ、ほんと……?」
私の前にコップを1つ置いてカレーを食べようと合唱した小田さんは、やはり驚いた顔をこちらに向けた。頷いて答えると、小田さんはスプーンを持ったままの両手を胸の前で握って、肩をすくめる。そのまま顔を赤らめて、視線だけそらした。
「あ、あの……篠田さん」
「はい」
「ちょっとだけ、その……寄りかかってみても、いい、ですか?」
「……? ええ、どうぞ?」
相性がいいと言って、なぜ、寄りかかりたいと思ったのだろう。疑問に思いながらも承諾すると、小田さんは私の左肩に頭を乗せた。肩に重みを感じて、小田さんの甘い香りがして、少し、ドキッとする。
――ん?
自分の中に生まれた気持ちに、私は首をかしげる。なぜ今、私はドキッとしたのだろう。小田さんは男なのに。いや、男でもこんなにかわいいじゃないか。いやいや、それでも男には変わりなくて。ただ接触したことに緊張しただけかもしれない。でも、……今、確かに私は、ドキッとした。
「えへへ……。こうやってると、ほんとに恋人みたいですね」
「一応、私たち付き合ってるはずですけど」
「へへ……そうなんですけど、ね」
小田さんの頭の重みが、私の左肩から消える。時間にすると10秒程度。一瞬のような、けれど何分も経ったような気分だった。
「篠田さん」私をじっと見つめて、小田さんは真剣な声で問う。「今のは、嫌じゃなかったですか?」
「ええ」
嫌じゃなかった。むしろ、あれは多分、うれしいとさえ思った、気がする。
「へへ……よかったです」
小田さんはほっとしたように笑うと、ようやく「いただきます」とつぶやいて、カレーを食べ始める。さっき電子レンジで温めたばかりの、たぶん、作り置き。食べる姿を眺めながら、私はなんとなく思い浮かんだ疑問を口にした。
「……いつも、自炊してるんですか?」
「んむ?」
もくもくと食べていた小田さんは、私の質問に手を止めて、飲み込んだ。
「はい。そうですよ~」
「そう……すごいですね」
「えへへ。篠田さんにすごいって言われるとうれしいです」
そう言って、小田さんはまたもくもくと食べる。私は小田さんの横顔を見つめながら、黙って小田さんがカレーを食べ終わるのを待った。そうして、水を飲んで、食器を片付けるからと席を立って、そのまま歯磨きをさせてほしいと洗面所へ駆け込む小田さんを見送って、ひとつ、ため息をついた。
――手を繋ぐ以上のことをしたい、か
正直、ここまで抵抗なく小田さんを受け入れられている自分に、私は驚いていた。小田さんと手を繋いだとき、嫌な感じはひとつもなかったし、さっきの寄りかかられるのだって、嫌ではなかった。小田さんが男だとわかっていながら、抵抗感はこれっぽっちもなくて――私はもしかして、“怖い”とさえ感じなければ、男相手でも問題ないのではなかろうか。「男性に恋ができない」というのは、私の思い込みで、努力すれば、可能なのではないだろうか。大学のときだって、私がもう少し勇気を出せば、聡太くんとの進展も望めたのではないだろうか。女の人にばかり、“逃げるように”好きにならなくてよかったのではないだろうか――――。
「お待たせしました」
小田さんの声に、我に返る。小田さんは私の左隣に腰を下ろすと、私をしばらく見つめた後、ほほを赤らめてうつむいた。
「……小田さん」
私はひとつ深呼吸をして、小田さんの顔に左手を伸ばす。小田さんは今日、駅で会ってからずっと、私がどこまで受け入れられるかを確認するように、少しずつ触れて、私が不快に思わないかを気にしてくれていた。その気遣いが、嬉しくも、申し訳なくもあった。だから、というわけでもないけれど、小田さんが望むなら、これくらい――キスくらい、私からしても、いいのではないだろうか。
「っえ、あ、あの……しの、だ、さん」
小田さんは驚いてこちらに顔を向ける。耳まで赤くなって、目が泳ぐ。その姿に私は、小田さんの匂いを感じたときのようにドキッとした。……この顔、好きかもしれない。
「嫌ですか?」
「いいい嫌じゃ、ない、です……」
「じゃあ、目、閉じてください」
「うっ……」
私に言われるがまま、小田さんはぎゅっと両目と閉じて、同時に口も強く結ぶ。その姿に私はまた心臓が高鳴るのを感じながら、今度はゆっくり、そっと唇を重ねてみる。ほんの少し触れるだけ。うん、嫌じゃない。むしろ、いいかもしれない。
離れながら目を開ける。小田さんの目もゆっくり開いて、視線が交わった。
「う、わ……ぁっ」
視線が交わると同時に、小田さんは今にも泣きだしそうな顔になって、両手で自分の口を押えてうつむく。私は、小田さんのほほに添えていた左手を引っ込めた。どうしよう、私からされるのは嫌だっただろうか。
「し、篠田さんっ」
小田さんの震える声。手元に落ちてしまった視線を上げると、顔を真っ赤にした小田さんが、涙目でこちらを見つめていた。
「……はい」
「い、嫌じゃ、なかったです、か?」
「ええ、まったく」
「……っ、じゃあ、あの」
小田さんの視線が揺れる。同時に、私の左手に、小田さんの右手が重なる。
「も……もう一回、ダメ……?」
ねだるような甘ったるい声が、耳の奥に響く。この瞬間、私はもう、自分の心臓の高鳴りを無視できなかった。――小田 琴。女の子のように甘えるかわいい男の子。私は――この人が好きだ。
[/font]