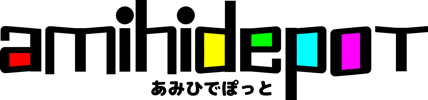[font]
メガシティ・トーキョーの下層。スラム街の一角に、あたしが帰る家――あたしが所属するレジスタンス、「アカギ派」の拠点はあった。ロストシティから脱出したあたしは、拠点へと続く小道を歩くように滑る。日が傾いて赤く染まったスラム街を通りながら、漂ってくる夕飯の匂いに、この家はシチューだとか、ここは魚料理だとか、そんなことを思ってひとり笑む。
スラム街は整備された土地ではない。むき出しの地面の上にさびたトタン屋根が所狭しと並び、小さな煙突が間隔をあけて立っていて、その煙突一つひとつが、そこが家であることをうかがわせる。屋根と屋根の間を縫うように通る細い道には、ゴミをため込むドラム缶が並んでいて、黒いゴミ袋も所々に積まれている。決して衛生的ではない、けれど確かに、人間が生きている様子が見て取れる街だった。
大通りから脇に外れて、ニワトリ小屋のある家の角を右手に曲がる。数メートル先に、オレンジ色の明かりとにぎやかな談笑が漏れる酒場が見える。近付くほどに大きくなる聞き慣れた声たちに、心の緊張が解けていく。ここが、レジスタンス・アカギ派の拠点。賑やかな普通の酒場。あたしの“家”だ。
「ただいまー」
大きく開いたシャッターをくぐり、オレンジ色の明かりの中へと入る。揚げ物と酒の匂いを感じる。
「あっ、ニーナ! おかえり!」
「おかえりニーナ!」
栗毛の男の子と黒毛の女の子が駆け寄ってくる。ここの酒場の子供、ジュンとチサト。あたしの弟分と妹分だ。二人は、あたしの腰ほどの身長しかないその体で、ぎゅっと抱きついてくる。愛らしいその姿に微笑んで、あたしは二人の頭に手を乗せた。
「ただいま、ジュン、チサト。二人とも、ちゃんとマイコさんのお手伝いした?」
「うん!」
「あのね、お皿洗ったの!」
「おおー、えらい! じゃあ、そんなえらい二人に」
言ってあたしは、腰に下げた袋から飴玉を取り出す。
「はい、お土産」
「わあっ……!」
「あめだま!」
飴玉を見たジュンとチサトの目がキラキラと輝くのを見て、口元が緩む。本当にかわいい子たちだ。
ジュンとチサトはあたしの手のひらから飴玉を取って、満面の笑みを浮かべた。
「ニーナありがとう!」
「ありがとう!」
「うん。どういたしまして」
二人は近くのイスに座って、口の中に飴玉を放り込む。そうそう、飴玉は喉に詰まるから、食べるときはちゃんと座って。「えらいね」と声を掛けると、ジュンとチサトは照れくさそうに笑って応えてくれた。
子どもたちがおとなしく飴玉を舐める様子を確認して、今度は酒場の奥へと視線を向ける。テーブルの間を縫って、部屋の最奥へと進む。進むたび、右から左から、見知った男たちから声が掛かる。
「おけえりニーナ! 後で飲もうぜ!」
「今日はパス! 疲れてんの」
「ニーナちゃん、俺たちとは〜?」
「疲れてるっつってんでしょ!」
「こっちで晩飯だけでもどーよー?」
「静かに食べたいからやだ!」
叫ぶように右へ左へと会話しながら、部屋の最奥にたどり着く。ほかのテーブルから少し離されたその席には、あたしにとっては見慣れた、三人の男性が座っていた。正面に座っているのは、大きなゴーグルを顔に掛けた、短い白髪頭の老人――ケイゾウ・アカギ。右手側に座っているのは、ふわふわと波打った短い茶髪で、メガネをかけた細身の青年――ショウヘイ・ヤマモト。そして左手側に座っているのは、白髪交じりの短い黒髪頭にバンダナを巻いた、恰幅のいい壮年――ザック・モンド。このレジスタンス・アカギ派の中心人物たちだ。
あたしは、正面に座っている老人に、かしこまって頭を下げる。
「団長。ニーナ・ユウザキ、ただいま帰りました」
「ああ、おかえり。無事で何よりだ」
レジスタンスの団長――あたしの“じいちゃん”はゆっくりとうなずいて、歯を見せて笑う。ショウヘイ兄さんが静かにこちらへ手を出してきたので、あたしはいつもそうするように、メタエネルギーコアの入った袋をショウヘイ兄さんの手に載せた。
「今日もたんまり持って帰ってきたなあ!」
ザックおじさんが、ガハガハと笑い声混じりに言う。
「でも……ニーナにしては、少ないね。387グラム」
ショウヘイ兄さんは、メタエネルギーコアを秤にかけて目盛りを見ながら、ぽつりぽつりと言葉を区切る。「ニーナにしては」という言葉に、後ろめたさを感じて視線が下がる。
「すみません。実は、」
一度、言葉に詰まる。下がった視線をもう一度上げて、じいちゃんをまっすぐ見て言う。
「軍に、見つかりました」
「まじかよ!?」
ザックおじさんの大きな驚きの声が酒場に響く。騒ぎながら酒を飲み交わしていた皆がこちらを振り返り、声が一つ、また一つ消えていく。あたりが、しんと静まり返った。
「おい……ニーナちゃん、見つかったのかよ」
「うそだろ……」
「ニーナが見つかったって……」
ざわざわと、周りが口々に驚嘆の言葉を呟く。じいちゃんは一つ咳払いをして、「まあ、」と口を開いた。
「見つかったもんは仕方ない。んで、どこで見つかった?」
「第三層のE区です」
言って、あたしはじいちゃんたちのテーブルに広げられた地図の”第三層E区”を指差す。
「移動範囲は?」
「ここから東に8キロ。突き当りを北に出た広い空間までです。ここで相手の目から逃れました」
指をE区から横へとスライドさせ、途中で空白になった部分で止める。地図を覗き込んでいたじいちゃんは、腕を組んでイスに寄りかかった。
「フム、未開拓エリア……G区か。わかった。これから一ヶ月、D、E、F、G区での採掘を禁止にする。それからニーナは一週間、ロストシティへの立ち入り禁止だ」
「はい」
「ほかに報告はないか?」
「第三層E区でマザーゴーストと遭遇、この広い空間で機能停止を確認しました」
「マザーに、遭遇したのかい?」
今度はショウヘイ兄さんが、静かに驚いた声を出す。あたしは一つうなずいた。
「よく無事に帰ってきてくれたな」
ザックおじさんはあたしの腕を二度、分厚い手でたたく。あたしはゆるゆると首を横に振るしかできない。
「ニーナ」
じいちゃんが、組んでいた腕を解いて、少し前のめりになる。ゴーグルの奥の優しい青い目が、レンズ越しにちらと見えた。
「軍に見つかるのは、皆、いつものことだ。この一年、ただお前の運がよかっただけのこと。それがわかったら、今日はもう休め」
「はい」
ありがとうございます。そう言って、あたしは三人へ頭を下げる。顔を俯かせたまま踵を返して、三人のテーブルから一番遠くにあるカウンター席へ一直線に向かった。
席につくと、タイミングを見計らったように、氷の浮かんだグラスが目の前に置かれる。波打つ黒髪を首の後ろで結ったふくよかな女性が、カウンター越しに笑顔で立っていた。
「おつかれ、ニーナちゃん」
「……ありがとうございます、マイコさん」
マイコ・グエンさん。レジスタンス・アカギ派が拠点にしている酒場を切り盛りしている女店主で、ジュンとチサトの母親。ふくよかな体と柔和な表情が、いかにも「お母さん」という言葉を連想させる人だ。
あたしは、マイコさんから出された水を一口飲む。全身の緊張が解けて、深いため息がこぼれる。
「そっか~。ニーナちゃん、軍人さんに見つかっちゃったのか~。ねえ、男の人? 女の人?」
マイコさんは楽しそうな笑顔を浮かべて、カウンターに寄り掛かり、こちらへ身を乗り出してくる。
「男でしたよ」
「へぇ~。ねえ、その人イケメンだった?」
にこにこ、にこにこ。マイコさんはこちらの様子をうかがいながら、とても楽しそうにしている。ああ、そう、マイコさんは色恋沙汰が好きだ。イケメンが好きだ。だから、こんなに楽しそうにしている。
あたしは頬杖を突きながら、ぼさぼさ紫頭の軍人の顔を思い浮かべる。不機嫌そうに吊り上がった眉。眠そうに瞼が伏せられた、けれど澄んだ金色の瞳。感情の見えない口元……。思い出すとイライラしてきて、無意識に自分の眉が寄るのがわかる。
「んー……まあ、イケメンなんじゃないですか? 一般的には」
「あら」
マイコさんは驚いたような声を出したけれど、あたしは気にも留めなかった。それよりも、自分の口から出た声が、あまりにも不機嫌すぎて。本当に、あの紫頭の顔を思い出すだけで気分が穏やかじゃなくなってしまった。確かにあたしは、あいつから逃げたはずなのに、すごく負けた気持ちになる。だって、そう、確かにあたしはあいつに捕まったのだ。顔と名前を覚えられてしまったのだ。今まで軍人の誰にも見つからなかったあたしが、見つかってしまったのだ。不快な気持ちが喉まで上がってきて、落ち着こうと、ひとつ、大きく肩で息をする。
手元に落ちていた視線を上げると、いまだににこにこしたままのマイコさんの顔が目に映る。何がそんなに楽しいのだろう。
「……なんですか」
「いや~、だってね? ニーナちゃんがイケメンだって認めるの、珍しいから」
「そうですか?」
「そうよ~。いつも『かっこいい人なんていない。強いて言えばショウヘイ兄さんくらいだ』って言ってるじゃない。ほかの人の顔を認めるなんて珍し~と思って」
「ふぅん……」
「あ、そうだ。今日の夕食はタンドリーチキンなの。準備してくるから待ってて」
「ああ、はい。ありがとうございます」
マイコさんは奥の厨房へと姿を消す。残されたあたしは、目の前のグラスに再度手を付ける。
「……男なんて」
誰も同じだ。言葉を、声にはせず、口の中で噛み潰す。
大半が男を占めるレジスタンスという組織の中にいるせいか、「女だから」という理由で気遣われたり、なめられたりしたくない気持ちが常にあって、色恋沙汰に関しては無関心を貫いてきた。男は、誰も同じ。顔がいいとか、性格がいいとか、そういうことに興味を持ちたくない。万が一興味を持って、情に付け込まれたなら、すぐに崩れてしまう。きっとあたしは、そうしないと強くいられない、弱い人間だ。
「虚勢なんて張らなくていいのに」
右隣りで声がして、ハッとして顔を上げる。ミディアムショートのさらさらな黒髪が目に映った瞬間、あたしは血の気が引いた。そして目をそらすよりも先に灰色の瞳と目が合って、線の細い整った顔が目に映って、嫌悪感が全身を駆け巡る。顔をしかめながら思い切り顔を背けた。
「ひどいな。そこまで露骨に嫌がられると、さすがに傷付くよ」
声に一切の感情が乗っていない。傷付くと言いながら淡々としている、余裕の塊のその声が、本当に嫌になる。――リック・キース。あたしがレジスタンス・アカギ派の中で唯一、心の底から嫌悪している人物だ。
「……どっか行って」
「無理な話だよ。俺は君と話がしたいんだから」
「あたしは話すことなんてない」
「俺はあるよ。まあ話さなくたって、君の隣にいるだけでも嬉しいけれどね」
「きっ……」
――きもちわるい。
ああ、今すぐ殴り掛かりたい、蹴り飛ばしたい、離れたい。怒りのようなものが腹からこみあげてくる。だめ、だめだ。マイコさんがタンドリーチキンを持ってくるまでは、タンドリーチキンを食べ終えるまでは、ここを離れられない。わかってる、こいつがそのタイミングを狙って来たことだってわかってる。ああ、でも、でも。とにかく離れたい。離れてほしい。一緒にいたくない。
「……どっか行ってくれない? せっかくのご飯がまずくなる」
「マイコさんの食事はいつでもおいしいはずだけど」
「あたしの気分の問題」
「そう。じゃあ、俺を意識しなければいいよ」
「……」
勝手に近付いてきて、勝手に話しかけてきて、どの口がそれを言うか。大体、なぜ、そんなにもあたしに好意を向けてくるのだろう。可愛い女の子はそこらじゅうにいるし、レジスタンス・アカギ派のメンバーの中にだって、もちろん何人かいる。顔が整っていて女子に人気があるのだから、そっちに行ってくれればいいのに。どれだけ嫌だと言葉で伝えても、態度で伝えても、あたしの拒絶を受け入れてもらえない。あたしの拒絶を無視して、踏み込んでくる。まだ軽い気持ちだったなら、遊びならよかっただろう。でもこいつは、違った。何を考えてるかは読めないけれど、あたしからの好意を、はっきりとしつこく求めてくる。そうして、こいつから好意を求められれば求められるほど、あたしの中のこいつへの嫌悪感は、増す一方だった。
「お待たせ~、あら」
厨房からタンドリーチキンを持って出てきたマイコさんは、あたしとリックを交互に見やって、にっこり笑う。そういえば、マイコさんはリックを気に入っていて、付き合えばいいのにと言われたことがあった。なんだか誤解されたような気がして、あたしは怪訝な顔をする。あたしの気持ちなどお構いなしに、湯気の立つあつあつのタンドリーチキンがあたしの前に置かれた。
「冷めないうちに食べてね~」
「……はい、いただきます」
そばにあったナイフとフォークで鶏肉を口に放り込む。気分は最悪だけれど、ああ、やっぱりおいしい。
「リックくんは何かいる~?」
「いえ、俺はいらないです」
「そう、じゃあごゆっくり~」
厨房を片付けてくると言って、マイコさんはまた奥へと入っていく。また、カウンター席に二人。不快だ。
もくもくと鶏肉を食べながら、横目でリックの手元を見る。二丁の拳銃を白いクロスで念入りに拭いている。そういえば、あの紫頭も拳銃使いだったっけ。無駄のない正確な動きで、綺麗な身のこなしだったな。
「気になる?」
「っんぐ」
あたしの視線に気づいたリックに声を掛けられて、驚いて、思わず鶏肉がのどに詰まる。慌てて水を飲んだ。
「……っ、はあ……別に」
肩で息をしながら正面の宙をにらんで、鶏肉をほおばる。別に、気になったのは、あんたじゃない。なんとなく、あの紫頭の軍人を、カインを思い出しただけだ。よくわからないけれど、なんだか、悔しい。誰の何に対してかわからないけれど、悔しい。
「……ん。ご馳走様」
鶏肉と、それから添えられた野菜を口の中にかきこんで、ここから離れたい一心で席を立つ。残りの水をぐいとあおって、グラスを強めにカウンターへ置く。ガンッと、いい音がした。
「ニーナ」
リックがあたしを呼ぶ声を無視して、あたしは足早に二階の自室へと続く階段を上った。
翌日。ロストシティに行けないあたしは、下層の市場に来ていた。スラム街よりも少し治安のいい、にぎやかな場所。お目当ては、マシンのジャンク品が集まっているガラクタ市。マシンを自作・改造するあたしにとって、ガラクタ市に並ぶマシンのジャンク品は宝の山だった。
さて、ジャンク品が積んである露店はどこだろう。そう思い、辺りを見回してみる。先月来たときは、この近くだったはず――――。
「……あれ?」
ジャンク品の山を見つけるよりも先に、目に留まるものがあった。露店一区画を挟んで反対側の道に立つ人影。ぼさぼさの紫頭と、下層に似つかわしくない綺麗な軍服、チタン製であろうシルバーの右腕。一瞬見間違いかと思って、凝視してしまう。そして、凝視したのが間違いだった。あちらの金色の瞳がこちらを向いて、ばっちりと視線が合う。眠たそうな瞼が開いて、驚いた表情に変わっていく。
「――なっ?!」
あたしは慌ててその場にしゃがみ込み、露店の棚を背にして物陰に隠れた。待って、待て待て待て! なんであいつがここにいるの!? カインが下層にいる理由が分からなくて、推測しようとして、頭の中がぐるぐるする。カインと目が合った瞬間の驚きと焦りで鼓動が速くなる。気付かれた。あの表情は、確実に、“あたし”だと気付かれた。どうしよう、ここにずっといたら捕まってしまう。逃げる? ああ、そうだ、逃げないと。
あたしは恐る恐る、棚から顔をのぞかせる。さっきカインを見つけた通りを見やるけれど、右にも、左にも、もうさっきの紫頭は見えなかった。どうやら、どこかに行ってくれたらしい。まだドクドクと鳴っている胸を手で押さえながら、ため息をついて立ち上がる。
「何を探している」
「ぎゃあああっ!!?」
真後ろから投げかけられた声に叫びながら飛び上がった。振り返るまでもなく、その声の主が誰かわかってしまう。落ち着きを取り戻しかけた心臓が一層速く鳴って、全身から冷や汗が出る。驚きすぎて心臓が痛い、本当に止まりそうだ。悔しい。逃げられると思ったのに、また逃げられなかった。このまま簡単に捕まりたくない。あたしは肩で呼吸をしながら、そして痛む胸を両手で押さえながら、さっき消えたはずの青年――背後に立つ“紫頭”をにらみつけた。
「……何?」
頭一つ分高い顔を見上げる。想像と違わず、確かにカインが立っていた。眠たそうな金色の目でこちらを見下ろしている。うっとうしい紫色の前髪が風に揺れている。
「捕まえに……来たの?」
「……? 今、俺を探していたんじゃないのか」
「違……あれは、あんたが、いなくなったかを、確認しただけ……」
「そうか」
それだけ言うと、カインはあっさり背を向けて、歩いて行ってしまう。その行動に、あたしは拍子抜けした。心臓はドクドク言っているのに、肩の力ががくんと抜けてしまう。疑問符が頭の上にたくさん浮かぶ。
「え、ちょ、ちょっと……」
訳が分からず、慌てて追いかける。ふと、カインの両手に、食料が入った布の手提げ袋が握られていることに気付いた。なぜ? 買い物? 確かに今は昼時だけれど。わざわざ下層に? また一つ、頭の上に疑問符が増える。
「ねえ、ちょっと」
すぐに追いついて、声を掛ける。あたしの声に立ち止まる様子はなくて、歩きながら疑問を投げかけた。
「ねえ。なんで捕まえないの」
「捕まりたいのか」
「そうじゃないけど!」
カインはこちらを振り返ることなく、市場の外に向かって歩きながら答える。よくわからないけれど、疑問を抱えたままにしたくなくて、あたしは後ろをついて歩く。
「そうじゃないけど……ふつー、目の前にいたら捕まえるじゃん」
「……。ロストシティ不法侵入の罪は、ロストシティ内でしか問うことができない」
「え?」
「ロストシティ内で見つけた不法侵入者をロストシティ外で見つけても、捕まえることはできない。ロストシティの治安維持及び保存法によって決められている」
「へえ……」
「だからレジスタンスの拠点が捜査されることもないし、レジスタンスが一斉摘発されることもない。高校で学ぶだろ」
「あたし中卒だから、知らない」
「……そうか」
初めて聞く話だった。確かに、団長のじいちゃんや、その補佐を務めているザックおじさん、ショウヘイ兄さんは知っているのかもしれない。でも、法律のこととか、そんな話は聞いたことがなかったし、勉強したこともなかった。もしかして、だから、見つかった翌日から一週間は、ロストシティに入れないのかもしれない。きっと監視の目が強まるから、見つかった人は捕まりやすいとか、そんな感じだろう。
「それから、俺はお前をロストシティ外で捕まえる権限を持っていない」
「うん?」
「俺はロストシティ治安維持部隊所属だ。下層地域治安維持部隊所属じゃない。警察でもない。だからここで犯罪者を見つけても、捕まえる手助けをするだけで、俺自身が誰かを捕まえることはできない」
「ふぅん。じゃあ、今あたしが何してもあんたはあたしを捕まえられないんだ?」
「迷惑行為で通報することならいくらでもできるぞ」
「ちっ……」
ちょっと腹いせに遊んでやろうと思ったのに、つまらない。でも、こいつが今、あたしに手を出せないというのは、好都合だった。
気付けば市場を抜けていて、住宅街に差し掛かっていた。心臓も呼吸もとっくに落ち着いて、あたしは胸の前で腕を組みながら、新しい疑問を投げかける。
「なんであんた、下層にいんの?」
「……」
「軍人ってさ、中層とか上層の人間でしょ? 下層に何の用?」
「……俺は、」
ぱた、とカインが足を止める。近寄りすぎたのか、背中にぶつかりそうになる。ギリギリで止まって、一歩下がった。
「俺は、スラム出身だ」
「え?」
カインが立ち止まったのは一瞬だけで、振り返りもせず、すぐに歩き出す。でも、あたしはしばらく動けなかった。
スラム出身と言われて、あたしは少なからず動揺していた。何に動揺しているのかは、わからない。ただ、スラムの人間は皆、「仲間」だと思っていた。それを、軍人という立場で以て、裏切られたような気分だった。
「……ねえ」
市場から10分ほど歩いただろうか。未だにカインは立ち止まることなく、マシンブーツで颯爽と駆けるわけでもなく、ただ、右足をカシャンカシャンと鳴らしながら歩いていた。いつまでこいつは歩くんだろう、買い物袋を両手に下げたままで。
「ねえってば」
「……」
無言。具体的に何か質問しなければ、こいつは何も答えないのだろうか。
「どこに行くの?」
「……」
嘘、違う。具体的な質問にも答えない。これは完全な無視だ。こうなったら、どこに行くのか突き止めてやろう。そんな考えが浮かんだ直後、カインが左手の横道に入った。見失いそうになって、慌ててあたしも横道に入る。
左手に曲がった先、ほんの二メートル先に、さびれた金属製の階段があった。階段をきしませながら、カインはそこを上がっていく。あたしは、視線を階段の先に向ける。玄関らしき扉があって、それは船についているもののような楕円形をしていた。建物自体は、まるで窓の付いた金属の箱が連なった姿をしていて、太いパイプが壁伝いに何本も張り巡らされている。T字の煙突があちこちから突き出ていて、その箱が家なのだと証明してくれている。言うなれば、そう、それは大きなマシンのようだった。
バタンと扉が閉まる音がして、階段の先へと視線を戻す。もうカインの姿はそこになくて、中に入ったのだと悟る。部屋に入るか入らまいか、躊躇したのは一瞬だけで、あたしはすぐに階段を駆け上がる。扉に付いたハンドル型のノブを手前に引くと、ギィときしみながらもそれは容易に開いた。足元の段差をまたいで中へと入り、扉を閉めながら、部屋をぐるりと見渡す。
中は、外観以上だった。大小さまざまなパイプが、天上を埋め尽くすように這っている。パイプは途中で何本も枝分かれしていて、ところどころにパイプ栓と気圧計が付いている。右も左も、ジャンク品の詰まった木箱や紙箱が積み上げられていて、箱が置かれていない“足場”によって、入り口から部屋の奥へと続く細い道ができていた。
「よぅ、カイン。帰ってきたのか」
「ん、ただいま」
「ハハッ、おけぇり」
細い道を進みながら、奥から知らない男の声が聞こえる。道の先には、買い物袋を持ったままのカインの背中が見える。
10歩もせずにたどり着いた空間の左手には、木製の大きなデスクがあって、その向こう側に、右目にルーペゴーグルを装着した、くたびれた白衣の人影があった。その姿は強烈で、思わずまじまじと眺めてしまう。顔はやつれて覇気がないのにニヤニヤと笑っていて、目の下のクマがひどい。カインとは比べ物にならないほどぼさぼさで一切手入れされていないような黒髪は、無造作に首の後ろで一つに束ねられている。無精ひげとクマさえなければ笑顔がきれいなのだろう、垂れた目じりに愛嬌を感じる、くすんだ黄色い瞳をしていた。
強烈な外見とともに、漠然とした違和感も感じる。くたびれた姿とは対照的に、声が異様に明るい。そして、視線の先は常に手元のマシンで、カインをまったく見ていない。まるで、マシン以外に興味がないとでもいうような様子だ。
「で? 今日はどーした」
「修理」
カインは、そばにあった棚の上に買い物袋を置いて、軍の制服を脱ぐ。次いで、アンダーシャツも脱いで、あっさりと上半身裸になった。慌ててあたしは顔を背ける。
「ちょっ、いきなり脱がないでよ!」
「んー?」
慌てたあたしの声に反応したのは、カインではなく、白衣の男の方だった。あたしが来てから初めて、マシンをいじる男の手が止まる。黒いグローブをはめた手が右目のルーペゴーグルを持ち上げ、くすんだ金色の双眸でこちらを鋭く見つめる。
「そちらさんは?」
「仕事仲間だ」
肩に巻き付いた義手を固定するベルトを外しながら、カインが白衣の男の質問に答える。あたしが答える隙を与えないとでも言うように。そして、それをあたしが否定するよりも先に、白衣の男が納得する。
「ほぉー? ほぉー、なるほどねぇ」
「あの……」
「ん? ああ、こりゃ失礼。俺ぁこいつの兄貴、アルバート・オルティス。見ての通り、エンジニアだ」
「えっ、と……」
アルバート・オルティス。その名前を、あたしはよく知っていた。エンジニア。そう、スラム街のエンジニア――――。
「あ……アルバート・オルティス!? ほ、本物ですかっ!?」
「ハハッ。嬉しい反応してくれんねぇ。そーそ、本物」
アルバート・オルティス。下層で唯一の“天才”エンジニア。彼の手がけるマシンはどれも精巧な作りで、ほかの人が分解すれば、二度と同じ形にはできないとまで噂される。上層の大企業から多額の資金援助を受けて、メタエネルギー工学の最前線を研究しているにも関わらず、スラム街からは一切出たがらない、変人。
そんな有名人を、偉人を目の前にして、あたしは舞い上がってしまう。
「あ、あたし、ニーナ・ユウザキっていいます。あの、あなたに憧れてエンジニアを目指してて、独学なんですけど、メタエネルギー工学勉強してて」
「へぇー、そりゃあありがてーことだぁな?」
アルバートさんはきゅっと目を細めて、黒いグローブをはめたままの指を口に当てて、喉の奥でクツクツと笑う。ああ、無精ひげとクマさえなければ、本当にきれいな笑顔だ。
そう、きれいだと思ったのもつかの間。すぐにその顔から優しそうな笑顔は消えて、ニタニタした顔に戻って、また手元のマシンに視線が落ちる。本当に、マシン以外に興味がないようだ。
「で、どこ?」
「右手の人差し指と中指の挙動がおかしい。パワー制御も効きにくい」
スッと、アルバートさんの右手がカインに伸びる。カインは、左手に握った“右腕”をアルバートさんの右手に乗せる。今のさっきまでデスクに置かれていたマシンが、デスク横の木箱の中にガラガラと落とされて、代わりに“右腕”が横たわる。
「いつから?」
「21時間前。マザーの腹の中に入った直後から」
21時間前と聞いて、あたしはハッとした。今は昼の12時半。21時間前は、あたしたちがマザーゴーストと対峙していた時間――カインが、ダズという軍人を、マザーゴーストの中から救出したときの時間だ。
「わかってんならさっさと帰って来い。いつも遅ぇんだよ」
「なるべく早く帰るように努力はしてる」
「誰に手足作ってもらってると思ってんだ、あぁ? 俺の作品をジャンクにすんじゃねえ」
口喧嘩のような会話をしながらも、気付けばアルバートさんは腕をあっさり解体し始めていた。腕の中を覗き込みながら、不機嫌そうに舌打ちをする。
「チッ、完全にイッてらぁよ。だからリミットは12時間つってんだろーが」
「……」
アルバートさんの顔はニタニタと笑っていて、声も明るい。一見楽しんでいるようにも見えるけれど、彼の口から発せられる言葉の汚さが、彼の怒りを体現していた。あたしは、カインのほうをちらと見やる。驚いたことに、カインは子供のように不貞腐れた顔でアルバートさんを見ていた。ちょっと、珍しいと感じてしまう。
「足は?」
声に、あたしは視線をアルバートさんへ戻す。ピンセットで、義手の中から配線を取り出していた。
「問題ない」
「そ」
カインの答えに、アルバートさんは短く返す。そして手際よく、そばに広げた白い布の上に、一本、二本、義手から取り出した配線を並べて置いていく。次いで、小さな歯車も並べて置いていく。ぴくり、左眉が怪訝そうに動いた。
「あぁ? カインお前、なんか50キロくらいでぶつけたか?」
「あっ」
息を飲んだような、小さな声。視線をカインに向けると、カインもこちらを見ていた。視線が合うと同時に、サッと目をそらされる。何だろうと思った疑問は、すぐにカインの口から出た。
「……マザーの腹に入る10分前に、60キロの速さで右腕から床に衝突した」
「ふん、人差し指と中指がイカれてんのはそれが原因だぁな。フツーなら大した衝撃じゃねえが、お前がメンテすっぽかしてるせいで摩耗してギアが歪んでらぁよ。ま、こっちは大したことねぇ。で、完全にイッちまってる配線の侵食はちょーど9時間ってとこだぁな。どーせ寝て起きたら挙動がおかしかったんだろ」
「ん……」
「チッ。わかってんならいい加減リミット過ぎて来んな」
60キロで床に衝突。カインとさっき目が合って、そらされた理由。それも、身に覚えがあった。あたしがカインに捕まったときだ。時速30キロくらいで逃げていたあたしを、倍以上の速さでカインは追ってきて、あたしを捕まえて、多分あたしを庇って、あたしごと背中から床に落ちた。なぜだろう、あたしは何も悪くないのに、あたしのせいで右腕が悪くなったみたいに思えてしまう。
妙な罪悪感に駆られてカインを見やる。カインは何とも思っていない様子で、平然とした顔のまま三分袖のアンダーシャツを着なおしていた。もちろん、右腕はない。
「メシ」
脈略なしに、突然アルバートさんがつぶやく。兄弟だから分かるのか、当然のように、その言葉にカインは答えた。
「いつから食べてない」
「あー?」
カインの言葉に手を止めたアルバートさんは、背後の壁に掛けてある時計を見上げた。
「18時間11分前」
「ちゃんと食え、死ぬぞ」
「ハハッ。じゃあメシ食わせに朝晩帰ってこいよ」
「俺は社宅生活だ。さっさと結婚してくれ」
「そりゃお前もだろーが」
「俺はまだいい」
「へーへー」
カインは、棚の上に置いていた買い物袋を左手で持って、一つ奥の部屋に行ってしまう。追いかけようとすると、アルバートさんに「ニーナちゃん」と呼び止められた。相変わらず、こちらはまったく見ずに、カインの右腕を分解しながら。
「あんたのソレ、マシンブーツだろ」
「あ、はい」
「ソレ、後で見せてくんねぇかな。代わりに俺の仕事見せてやっからよ」
「えっ。い、いいんですか?」
「おーよ。あぁ、と、細けぇこと手伝ってくれっと嬉しーな?」
顔は義手に向けられたまま、視線だけがこちらを向いて、きゅっと目を細められる。ガサツ、横暴。さっきまでの会話の様子から、そんな言葉が似合うはずなのに、なんだか憎めない人だと思った。
あたしはアルバートさんの右手そばに歩み寄る。アルバートさんは、無言で近くにあった丸イスを引き寄せて、ここに座れと座面をたたいた。おとなしく、出された丸イスに座る。
「ニーナちゃん。マザーの毒、見たことある?」
「マザーの毒、ですか?」
ピンセットの先で指し示されたのは、義手から取り出された四本の配線だった。周りに、黒い煤が付着している。
「煤?」
「煤に見えるが、煤じゃあない。マザーゴーストだけが腹の中に持ってる、純粋なメタエネルギーの結晶だ」
「純粋なメタエネルギー……」
普通のメタエネルギーと何が違うのだろうかと、右手を伸ばす。すると左から、すぃーっと、ピンセットを持ったままの右手が流れるようにあたしの右手を掬い上げる。ギョッとして視線だけをアルバートさんに向けるが、アルバートさんはこちらを見る気配がない。
「素手で触っちゃだぁめ。グローブ付けな?」
言って、茶色いグローブを投げ渡される。表面が水にぬれている。
「マザーの毒は、接触したものを“情報”に分解する。分解されないのは水だけだ。マザーの毒に触るときは、必ず水を含んだ布を使うこと。覚えときな?」
「……はい」
渡されたグローブを手にはめる。中は防水になっているのだろう、普通の布の感触だった。
「じゃ、そこの配線に付いたマザーの毒、全部水で洗って」
「はい」
水で洗えと言われて、目で水を探す。自力で見つけるよりも先に、アルバートさんがピンセットで、デスクの反対側に見える流し台を指した。そばにバケツも見える。一旦その場から離れ、流し台に置かれていたバケツに水を汲んで、席に戻る。デスクの端にバケツを置いて腰を下ろし、並べられた配線を手に取り水に漬けると、ジュウッ……と、高温の鉄を水に漬けたときのような音がして、マザーの毒が消えた。
「消えた……?」
「あぁ。水に触れると、マザーの毒は蒸発する。だから雨が降る地上じゃあ、メタエネルギーが自然に増えるこたぁねんだ」
そんなものなのかと、とりあえず納得する。よくわからないけれど、メタエネルギーがロストシティにしかないと言っていることだけは、わかった。
マザーの毒が消えた配線を水からあげると、エナメル線がむき出しになっていた。どうかすると、エナメル線もガタガタで、今にも千切れそうだ。配線に付いた水気を取ろうと、今度は乾いた布を目で探す。すぐに左側から乾いたタオルが出て来て、「ありがとうございます」と言いながら、素直にそれを受け取る。人の行動や考えていることを先読みするのは、この兄弟の特技なのだろうか。
配線の水気を取って、デスクに置く。二本目の配線を水に漬けながら、あたしは疑問を口にした。
「あの……マザーの毒が接触したものを情報に分解するって、どういうことですか?」
「あぁ? 文字通りの意味だ。それ以上でもそれ以下でもそれ以外でもねぇよ」
わからない。二本目の配線の水気を取りながら首をかしげると、アルバートさんは、「んー……」と小さくうなった。
「そーだぁな……。とりあえず、マザーの毒がくっついた物質は、水以外ならどんなもんでも、12時間経過した時点で、一秒間に0.1マイクロメートルずつ、メタエネルギーの粉になってく。今はそれだけ覚えときゃいい」
「はい……」
二本目の配線の水気を取り終えて、三本目の配線を洗いながら、覚えておけと言われたことを、頭の中で復唱する。マザーの毒が付いた物質は、12時間経ったら、一秒間に0.1マイクロメートルずつメタエネルギーの粉になる。そしてマザーの毒は、マザーゴーストの腹の中だけにある。
三本目の配線をきれいにして四本目の配線を洗いながら、ふと、じいちゃんたちの言葉を思い出した。そういえば、今までずっと、「マザーゴーストには食われるな」と言われてきた。食われたらもう二度と戻ってくることはできないと、そう言われてきた。つまり、マザーゴーストに食われて、腹の中でマザーの毒に触れて12時間経ったら、体内で消化されるのだろう。なるほど、だから「食われるな」だったのか。あたしは一人、納得する。
「ところでニーナちゃん」
四本目をきれいにしてデスクに置いたところで、アルバートさんに声を掛けられる。
「あいつとの仕事、なかなか難しーだろ?」
「えっ……と、……まぁ……」
難しいというか、そもそも対立組織の人間なのだけれども。曖昧に笑うと、アルバートさんはギアを研磨する手を一瞬だけ止めて、視線をこちらに向け、目を細めて柔らかい笑みを浮かべた。それはほんの一瞬だけで、すぐに作業に戻る。
「あいつのやることとか、態度とか、冷てぇとか思うかもしれねーけど、悪く思わねぇでやってくれな? 軍人とはいえ、スラム出身だからさ。やっぱどっかで、自分に引け目を感じてんだろーよ」
「そう、なんですか」
借りたグローブを外して、デスクに置きながら思う。引け目を感じているようには見えないと思ったけれど、あたしは、カインの何かを知ってるわけじゃない。ただ、昨日捕まって、今日遭遇しただけの関係だ。兄のこの人が言うのだから、きっとそうなのだろう。
「中層、上層の人間がほとんどの軍の中で信頼されるにゃあ、どーしたって結果が一番になる。だから結果に固執するし、人より無茶もするし、あっさり他人を切り捨てることもある。おかげで軍の中じゃ、あいつを嫌うやつも結構いるって話だが、別に、情がねぇわけじゃねんだ」
「そうですね」
カインに情がないとは、思わなかった。昨日捕まって、今日遭遇しただけの関係だけれど、何度も、情を感じる部分があった。顔に出さないだけで、人としての優しさくらいは持ち合わせているように感じた。
「しっかしまぁ、友人の少ねぇあいつがいきなし若ぇ女連れてくんだからな。そりゃあ驚くって」
「あ、と。それは……」
あたしが勝手についてきただけとは、今更言いづらい。ぎこちない笑みを浮かべて、言い訳を考える。偶然市場で会って、買い物を手伝った? いや、ないない。想像ができない。
「まぁ、なんだっていーさ」
あたしが言い訳を思いつくよりも先に、アルバートさんは作業の手を休めて、こちらに向いて頬杖を突きながら、きゅっと目を細めて笑う。
「これからも、あいつと仲良くしてやってくれな」
「……はい」
あたしも、笑顔で答える。愛嬌のあるその笑顔を見て、言葉を聞いて、いいお兄さんだなと思った。それから、あたしとカインは、レジスタンスと軍という敵対関係にある間柄だけれど、もしかしたら、少しくらいは分かり合えるかもしれないと、頭の隅のほうで思い始めていた。
20分ほどして、義手の組み立てが終わるころ、カインが「食事ができた」と部屋に戻ってきた。家族の時間を邪魔するのは悪いからとあたしは帰ろうとしたけれど、まだマシンブーツを見ていないという理由で半ば強引にアルバートさんに昼食に誘われて、あたしはオルティス兄弟と昼食を共にしたのだった。
[/font]