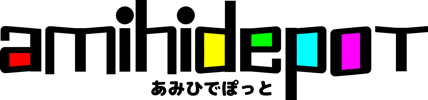[font]
政府軍本庁舎は、メガシティ・トーキョーの上層地域、官公庁が立ち並ぶ東部にある。上層の建物に相応しく、地上30階の高層建造物で、光沢のある花崗岩でできた外壁が荘厳さを物語っていた。建造物内部ももちろん、磨かれた石材の床や柱ばかりで、温もりは一切感じられない。10階まで吹き抜けになっている正面口のフロア1階には、そこを行き交う関係者の足音が響き合っていた。
その、政府軍本庁舎の正面口フロアに、カシャンカシャンと金属の擦れる音が響く。周囲の話し声や他人の足音にかき消されることなく、その音は、いつもフロアの床や壁に反響する。音を消したいと思ったことも多々あったが、2年も経てば、いい加減自他ともに慣れてしまった。誰ももう、この足音に好奇心だけで振り返ることはない。
「――ちょっとカイン!」
……そう。好奇心だけで、振り返ることはない。つまりは、好奇心でなければ――俺を探しているのなら――逃げることも隠れることもできず、すぐに見つかるのだ。今みたいに。
俺は小さくため息をついて、声に振り返ることなく歩き続ける。先ほど俺は、部長命令で通常の巡回任務から外され、呼び出しを受けた。他人と話している時間はない。
「カインてば!」
甲高い声が耳に刺さると同時に、ぐいっと左手を引っ張られ、足が止まる。体を触られるのが不快で、すぐにその手を振り払った。
「もう、呼んでるのになんで無視するのよ!」
俺が立ち止まったのをいいことに、声の主は俺の前に立ちはだかる。きれいに切りそろえられた長い黒髪が、眼の前で大きく揺れる。――サキ・ローズワース。俺と同じロストシティ治安維持部隊所属の同僚。いつも、腰まで伸びた艶のある黒髪をなびかせている、俺の胸元までしかない背丈の、小柄な、うるさい女。
サキは、黒い目で俺を睨んでいる。絡まれるのが面倒で、俺は黙ったまま視線をそらした。
「昨日、下層で知らない女と歩いてたんですって?」
「……」
「ちょっと、こっち見なさいよ!」
「はーいどうどうサキ、ここでデカい声出すなって」
聞き慣れた友人である同僚の声に、そらしていた視線を向ける。サキを追ってきたらしいダズが、ずり落ちたヘアバンドを上げ直しながら、俺とサキの間に割って入っていた。両手でサキの両肩を押して、俺から引き離す。こちらに振り返ったダズは、俺と視線が合うと、にっと歯を見せて笑った。
サキはダズの両手を払い除けて、また俺に一歩近付く。慌ててダズが、背後からサキの首に腕を回す。ダズの腕を剥がそうとしながら、サキは声を一層張り上げた。
「ここがどことか関係ないわよ! わたしは真剣に話してるの!」
「いーから声落とせって……!」
俺より、ダズの方が困っているようだ。ここで立ち止まっていてもらちが明かないだろう。俺は二人の横を抜けて、フロア奥のエレベーターに向かう。3歩進んだところで、背後から「あっ、こら!」というダズの慌てる声が聞こえて、もう3歩進んだところで「いつまで無視する気よ!」というサキの金切り声が聞こえる。無言のままエレベーターの扉の前にたどり着いて、上昇ボタンを押す。今は25階に止まっているらしく、1階に降りてくるまでには時間がかかりそうだった。
黙って立っていると、視界の左端に、腕を組んで仁王立ちになったサキの姿が入り込んでくる。「ねえ」と、棘のある声が耳に入った。
「あなたが下層出身なのは仕方ないけれど、仮にも軍人なのよ? 行動するにも立場を弁えなさいよ」
「お前が気にする必要はない」
「班員でしょ!」
そう。サキは俺と同じ班のメンバーだった。治安維持部は、ロストシティ治安維持部隊・下層地域治安維持部隊・中層地域治安維持部隊・上層地域治安維持部隊の4部隊に分かれていて、それぞれの部隊には4人1組の班がいくつも存在している。そして俺の所属する班は、フェイ・ロー班長、ダズ・エンデリオン、サキ・ローズワース、俺の4名で構成されていた。
サキは班員だからと言うが、俺は別に構わないだろうと思った。それに、昨日ニーナ・ユウザキが家までついてきたことについて、どんな言葉を吐き出したところで言い訳にしか聞こえないだろうし、説明するのも面倒だった。話題を変えようと、俺は先ほどから気になっている些細な疑問を投げかけた。
「……二人とも、巡回の時間じゃないのか」
「ええ、そうよ」
「お前が部長命令で班から外れたって、さっきロー班長から聞いたんだよ。それで、俺たちだけで出ようとしたら、サキがお前を見つけたもんだからさ」
「何よ、ダズだって同じことカインに言おうとしてたじゃない!」
「いや、俺は女のこと言おうとしたわけじゃねーし」
「そうか」
エレベーターが10階で止まっている。そろそろ会話を切り上げたほうがいいだろう。階数表示ランプからダズとサキへ視線を移して、社交辞令を述べる。
「無事に帰ってこいよ」
「おう、行ってくるわ」
にっとダズが笑う。対して、さっきまで騒いでいたサキは、頬を赤らめて、目を見開いた。様子に気付いたダズが首を傾げ、俺も視線を投げる。すぐに、サキは顔をそらした。
「え……ええ。行って、くるわ」
顔をそらしたまま、ぼそぼそと言う。一瞬だけ、ちらりとこちらを見たかと思うと、パタパタと駆けて行ってしまった。意図が読めずに、俺は顔をしかめる。ダズは渇いた笑い声をこぼした。
「ははっ、なにあいつ照れてんだ」
「……そうか」
俺の反応に、他人行儀だと、ダズはケタケタ笑う。確かに俺のことかもしれないが、それでも、俺には関係のないことだ。
「じゃ、俺も行くわ」
そう言って、ダズは軽く片手を挙げる。俺も「ああ」と短く返して、ちょうど扉の開いたエレベーターに乗り込もうと一歩踏み出す。
「あ、そうだ」
出口へ向かおうとしてふと足を止めたダズが、こちらを振り返ることなく、俺の左肩に腕を載せた。
「――お前がレジスタンスとつるんでたこと、上層部で問題になってるっぽい」
耳元でささやかれた言葉に、ハッとする。何もなかったかのように、「じゃあまた夜になー!」とダズの明るい声が遠退いて行く。なるほど、サキが言い寄ってきた原因は、そのせいか。ダズも、これを言いに俺のところへ来たのだろう。数少ない友人に、心の中で礼を言う。
しかし、上層部で問題になっているのなら、部長にも責任が及んでいるのではないだろうか。そうなら、早急に詫びて対応しなければ。俺は頭を抱えながら、エレベーターに乗り込んだ。
26階、灰色の絨毯が伸びる広い廊下の突き当り。重みのある木造のドアに掛けられたプレートには「治安維持部 部長室」と書かれている。ドアの前に立った俺は、4回ノックした。
「カイン・オルティスです」
「――入れ」
ドアの向こうから、落ち着きのある男の声が聞こえる。俺は息を吸って、ドアノブを回した。
「失礼します」
頭を下げて部屋に入る。部屋の奥、窓を背にした広いデスクに、書類を見つめる、短い黒髪を後ろへ流した男の姿があった。ドアを閉めてから、俺は5歩、デスクへと歩み寄る。デスク越しに、深く頭を下げた。
「サカイ部長。この度は急遽休みをくださり、ありがとうございました」
「フム」
治安維持部のトップ――レンジ・サカイ部長は、手にしていた用紙をデスクに置いて両手を組み、深みのある青い目で俺を見た。
「構わんよ。君の大事な右腕のためだ。どうだね、調子は」
「はい。おかげさまで、良好です」
「フム。それはよかった」
サカイ部長は表情を変えることなく一度目を伏せ、そしてまたこちらを見つめる。
「兄君は何か言っていなかったかね」
「……? いえ、特には」
兄貴、アルバート・オルティスの顔を思い浮かべる。何か、と言われても、特に思い当たる節がない。サカイ部長は「そうか」と言って視線をそらしたあと、淡々と続けた。
「この3ヶ月、メンテナンスに帰っていなかっただろう。あの神経質な男のことだ、文句の一つでも言っていると思ったのだが」
「そう……ですか」
確かに小言のようには言っていたが、大して気にすることではなかったように思う。それよりも、ニーナ・ユウザキをいたく気に入っていたことのほうが気にかかって――――。
「……部長」
レジスタンスの女の顔が脳裏に浮かび、話さなければならないことを思い出した。
「私が昨日レジスタンスと接触していたことが上層部で問題になっていると、噂を耳にしました。接触したことは事実です。申し訳ございません」
「フム」
俺が頭を下げると、ぴらっと、紙を拾う音がする。
「ニーナ・ユウザキ、女、2184年9月17日生、18歳、A型。出身籍はメガシティ・トーキョー。戸籍はメガシティ・トーキョー下層地域西部第7区48号3番。国際中等教育を修了。現在はレジスタンス・アカギ派に所属し、就業先はなし」
「……」
聞こえる情報に顔を上げる。俺が言うまでもなく、すでに調べはついているようだった。
「接触していた人物はレジスタンスとはいえ、“善良派閥”と名高いアカギ派のメンバーだ。特に目立った犯罪歴があるわけでもない。接触したところで、問題視する必要もなかろう。それとも、何かね」
手にした用紙を再度デスクに置いて、流れるように両手を組み、こちらへ向けた視線をスッと細める。
「君は何か、取り引きをしたとでも言うのかね」
「いえ、そのようなことは決して」
俺は即座に否定した。無実でも、サカイ部長にこのような質問を投げられると、慌ててしまう。この人からの信頼だけは、裏切りたくない。
「では問題なかろう」
目を閉じて、サカイ部長は一度言葉を区切る。次いで目を開けると同時に、口元が和らいで、ようやっと表情が変わる。
「お前がそのような人間でないことは、私が一番よく知っている。何、どうせいつもの、お前の成績を妬む上層部のくだらん戯言だろう。放っておけばよい」
「……はい」
静かな、しかし説得力のある声に、ただ頷く。この人が「くだらない戯言」と言うのだから、きっとそうなのだろう。疑念など、この人に対しては不要だ。
今回の件に限らず、サカイ部長はいつも、下層地域の人間に対して理解を示してくれる。決して、生まれた地域だけで優劣を決めない。俺が入隊試験を受けたとき、生まれを問わず俺の入隊を推薦してくれたのも、この人だった。
「さて、君をローの班から外してここに呼んだ理由だが」
和らいでいた表情を引き締め、サカイ部長は話を切り替える。俺も、姿勢を正した。
「A区に向かってもらいたい」
「A区、ですか」
A区といえば、メガシティ・トーキョーの上層地域中央部の真下。毎月、政府がメタエネルギーを採掘するために通るエリアだ。特に第1層は、都市崩壊以前に存在していた「東京都」の街並みが色濃く残り、採掘作業の拠点としても活用している。そのような場所で、何があるというのだろう。
俺の疑問には直接答えず、サカイ部長は続ける。
「詳しいことはツェレンに聞いてくれ。すでに現地へ向かっている」
ツェレン。その名を聞いて、瞬時に“普通ではない”ことを察する。
「承知しました」
俺は頭を下げて、足早に部長室を後にした。
――ナオ・ツェレン。治安維持部・部長補佐で、レンジ・サカイ部長の“右腕”。今年の4月からは、ロストシティ治安維持部隊の隊長でもある。個人的なつながりはなく、班長伝手に任務指示を受けるくらいしか関りはない。個人的にサカイ部長に呼ばれることが多いため、いつも部長室で顔を合わせはするが、会話をしたことはない。
俺は上層地域の中央通りをバイクで走りながら、ツェレン隊長の容姿を思い浮かべる。微笑むように小さく上がった口角と、丸いふちで茶色いレンズのサングラス、茶色い髪は肩にかかるくらい長く、いつも首の後ろで束ねている。体格は華奢なほうで、背は俺より頭半分ほど低いくらいだったか。
政府軍本庁舎からバイクで5分、大きな鉄格子に囲まれた門の前にたどり着く。門番に身分証明書を見せて中に入り、道のわきにバイクを寄せて降りた。積み上げられた無数のコンテナの間を通って奥へ進むと、地上に突き出たエレベーターの扉の前に立つ軍服姿の人影が目に入る。歩み寄ると、その人影はこちらへ振り向き、うっすらと笑みを浮かべた。
「ヤァ、待ってたヨ」
語尾がわずかに強調されるような、独特なしゃべり方。男性にしては高めの、女性にしては低い、中性的な声。間違いなく、ナオ・ツェレンその人だった。
「早速だケド、入ろうカ」
俺があいさつするよりも先に扉へ向き直り、開けて、中へと入る。俺も、無言で後を追った。隣に並び、遅れてあいさつをする。
「……よろしくお願いします」
「ウン、よろしくネ」
首だけこちらを振り返って、ツェレン隊長はあいさつを返してくれる。声色や表情は柔らかく、とても優しそうな、人当たりのよい印象を受けた。しかし、ほんのわずかに違和感も感じる。言葉ひとつ、動作ひとつ、どれもわざとらしい感情が目立って、本心が読めない。はっきりと、他人との間に壁を作るタイプの人のようだ。
「今回の任務だケド」
エレベーターの扉を閉め、ロストシティへと降りながら、ツェレン隊長は説明を始める。
「諜報部の報告によるト、レジスタンス・トーゴー派が6人、A区第1層で何かしてるみたいなんだよネ」
「トーゴー派、ですか」
レジスタンス・トーゴー派は、政府が危険視している過激派組織のひとつだ。彼らの活動は、メガシティ中層地域にある政府管轄機関を襲撃・破壊したり、中層地域にあるメタエネルギー保管庫からメタエネルギーを強奪したりと、武力行使が目立つ。下層地域内でも危険視されていて、実際のところ、ロストシティ治安維持部隊よりも、下層地域・中層地域治安維持部隊との衝突のほうが多い。
そんな組織のメンバーが、メタエネルギー採掘作業の拠点であるロストシティA区にいる。それは確かに、とても危険なことだ。しかし一体、A区で何をしているのだろうか。仮にメタエネルギーを強奪するためにA区を占拠しようとしているのだとしても、いつもの彼らの手口とは違い過ぎて、違和感がある。これ以上考えても答えは出ないだろうと、素直に疑問を口にした。
「彼らは、一体何を」
「サァ? それを調べるのガ、今回のボクらの仕事だヨ」
「……そうですか」
レジスタンスがA区で何をしているのかを調べるのが、今回の任務。それはいささか、理解しがたいことだった。基本的にロストシティ治安維持部隊は、巡回でなければ、諜報部が入手した情報を基に捜索・制圧・討伐などを行う。今回の任務は、完全に諜報部の管轄だ。
任務内容の不可解さに顔をしかめていると、ヌッと、ツェレン隊長が下から顔を覗き込んでくる。少し驚いて、体を引いた。
「今回の任務内容、納得できてないみたいだネ?」
「……はい」
微笑みを顔に貼り付けたままのツェレン隊長は、ひとつ瞬きをして、元の姿勢に戻る。大げさに肩をすくめながら話し始めた。
「ロストシティはこっち側のテリトリーだシ、やろうと思えば大人数で捜索することだって容易にできル。でもそうしちゃうト、ヤツらは“してること”を消して逃げる可能性があル。だからこっちモ、なるべくこっそり捜索したイ。なら諜報部が適任……って思うよネ、普通なラ」
俺は黙って話の続きを待つ。ツェレン隊長はちらと俺の方を見てクスッと笑い、話を続けた。
「今回の相手ハ、過激派で有名な集団。もし見つけたラ、その場で正面からの戦闘になる可能性があル。諜報部の連中はそんなに戦闘能力が高くないかラ、任せにくいんだよネ」
なるほど、ツェレン隊長の言うことも一理ある。治安維持部は戦闘に特化した訓練を受けているが、諜報部は情報収集のための訓練が主で、任務の内容も多岐にわたる。万一、諜報部員1人が本格的な戦闘に持ち込まれたら、勝ち目はないだろう。
「それかラ、さっきボク、『調べるのガ』って言ったケド」
宙を指さして、ツェレン隊長は付け加えるように言葉を続ける。
「最悪、ボクらはレジスタンスを見つけて捕まえさえすればイイ。ヤツらの口を割らせるのハ、それこそ諜報部の仕事だヨ」
「……なるほど」
それなら、確かに今回の任務内容に納得がいく。ようは戦闘必至の敵を捕まえればいいのだ。何ら、いつもの仕事と変わらない。確認するように、俺は小さく頷いた。ツェレン隊長は、俺が納得いったことを悟って頷きを返してくれる。
「肝心の捜索だケド、ヤツらはA区の中央付近、半径5キロ圏内をうろうろしてるみたイ。ボクは東側を捜索するヨ。キミは西側をよろしくネ」
「承知しました」
再度頷いて、今回の任務内容について改めて整理する。ふと、ひとつ気になっていることを思い出した。
「……ひとつ、お伺いしても」
「ウン?」
ツェレン隊長は、微笑みを顔に貼り付けたまま首を傾げる。
「なぜ、隊長直々に任務を……しかも、私と、なのでしょうか」
「ああ、それはネ」
まるで大したことではないといった様子で首を戻して、ツェレン隊長は続ける。
「サカイサンたっての希望でネ、キミを班長に昇格させるための前準備だヨ。ボクは隊長だかラ、班長を選定する義務があル。そのために、キミの能力を間近で見ておきたくてネ」
「班長に」
まさかの答えに、戸惑って、聞き返してしまう。俺が、班長に。それは何かの間違いではないだろうか。
「……私が班長になって、何か利点がありますか」
「単純だヨ。サカイサンの息がかかった部下が幹部になれバ、それだけサカイサンの政府軍内部での影響力も増えル。特にキミはサカイサンのお気に入りだシ、融通の利く子が班長になってくれれバ、ボクも仕事がしやすくなって助かるんダ。キミだって昇格できるんだシ、悪い話じゃないよネ」
「……そうですね」
サカイ部長たっての希望。俺が、班長に。班長としての器かどうか自身では分かりかねるが、サカイ部長はそう判断されたのだろう。だから今、俺はここにいる。ツェレン隊長からの情報を素直に受け止めて、任務遂行に集中することにした。
長いエレベーターが下降を止めて、廃れた“街”にたどり着く。ロストシティA区、第1層。都市崩壊以前の「東京都」の街並みが色濃く残る、廃墟と化した大都市。はるか高くに見える“天井”には無数の照明が取り付けられていて、それが都市崩壊後の技術で作られたものだということは、容易に見て取れる。地面には、ところどころに採掘作業用の物資と照明が置かれていて、定期的に使用されている様子があった。周囲にそびえる建造物は、崩れることなく本来の姿を保っている15階建てのものもあれば、上層階が下層階を押しつぶすように倒壊したものもある。地上とロストシティをつなぐエレベーターのすぐそばには、「東新宿駅」と書かれた看板の掛かった建物が建っていた。
「じゃあ、よろしくネ」
「はい」
エレベーターから降りてすぐ、言葉少なに、俺とツェレン隊長は別れる。エレベーターの中で話した通り、俺は道を西へ、ツェレン隊長は東へ進んだ。
辺りを観察しながら、崩れかかった建造物の間を歩く。2歩進むたび、カシャンと金属の擦れる音が響く。これでは自身の場所を伝えているようなものだ。ツェレン隊長は「こっそり」と言っていたが、どうもやはり、俺の体は隠密行動に不向きらしい。自身の場所がばれてしまうことはもうあきらめて、ひとまずは痕跡を探そうと、思考を切り替えた。
落ち着いて、もう一度辺りを見回す。この空間には、最近になってここへ持ち込まれたであろう物を除けば、見事なまでに無機物しか残っていない。それでも200年分のほこりはしっかりと積もっていて、採掘作業を含め、人がそこを動いたであろうわかりやすい痕跡があちらこちらに見える。ただ、レジスタンスの残した痕跡がどこかにないかと探してみるものの、最近できたような足跡は見当たらなかった。
歩いて5分。代り映えのしない景色に、一度歩みを止める。かつて道路だった場所には貨物車の轍がくっきりと残っていて、先に見える交差点まで続いている。左手に伸びる脇道にも、人が通ったような足跡はひとつもなく、ほこりは見られない。まだ先だろうかと足を出しかけたところで、ふと、今見たものに違和感を覚えた。
――――ほこりは見られない。
振り返り、左手に伸びる脇道の先を、じっと見つめる。確かに足跡はまったく見られない。けれどそれは、きれいに伸びた道に“ほこりがない”せいだ。常設された照明のせいで見えにくいが、それは繰り返し歩いた跡でも、車輪が往復した跡でもない。よくよく観察しなければ見落とすほどのものだが、それは確かに、何者かによって掃除された跡だった。
俺は道の先を見つめながら、胸ポケットに入っている通信機に手をかける。
「――こちらカイン」
『ヤァ、どうだイ?』
ツェレン隊長の声が胸元の通信機から聞こえる。
「現在地、旧歌舞伎町2丁目4番。南方面に、何者かに清掃された痕跡あり。調査します」
『フゥン、了解。こっちもチョット、掃除してから行くヨ』
「承知しました」
通信を切り、南方面へと歩いていく。掃除された痕跡は、歩いてすぐの交差点の角、10階建ての建造物のそばで消えていた。正確には、建造物の周辺のほこりさえも消えていた。薄暗い建造物の中へと足を踏み入れる。床には、小さな机やイスの骨組みが転がっていた。そこに混ざって、いくつもの足跡が見える。ぐるり、その場を見渡す。すでに機能を停止したエレベーターがあった。そばには外れた扉があり、その奥に階段が見える。目を凝らすと、うっすらと足跡が見える。転がった家具をまたぎながら足跡に沿って近付き、ほこりをかぶった階段を上る。6階まで登ったところで、ほこりの量が激減する。扉が外れた入り口から先へと、ほこりのない床が続いている。狭い廊下へと足を踏み入れる。歪んだ扉、外れた扉、閉まったままの扉。慎重に部屋の中を見ていく。突き当りの開けたピロティまで来たところで、ほこりの量が増え、足跡は完全に消えた。
もう、観察は十分だろう。俺は、床へと向けていた目を閉じて、ため息をつく――次の瞬間。左手で腰のホルダーから銃を抜き出し、構えながら腰を落として背後へと振り返る。頭上に人影を確認しながら、かかとを床に打ち付けて蒸気を吹き出し、勢いよく前進する。俺へと被さってきた人影の背後に回り込み、それの脚へと1発撃ち込む――叫び声とともに宙に浮いていた人影の体勢が崩れて、手にしていたナイフとともに床へと落ちる。1人目。
間髪入れず、弾をリロードする音が耳に届く。床へと落ちた人間の襟首を右手で掴み、盾にするように持ち上げながら振り返る。掴んだ人間の左肩を弾が掠めて血が飛び散る。左手に構えた銃で廊下に立つ人影の右肩を撃つ――叫び声とともに人影がその場で崩れ落ちる。2人目。
2人目の叫び声が聞こえるのとほぼ同時に、視界の左端に長剣の切っ先が映る。右手に人間を掴んで振り返った勢いのまま体を前転させて、振り下ろされる切っ先から避ける。体を起こす瞬間に人影の右腕を撃つ――叫び声とともに長剣が大きな音を立てて床に落ちる。3人目。
辺りに、男のうめき声が3つ響く。廊下に倒れ込む男の手にある拳銃へ向けて一発撃ち込み、銃を使えなくする。同時に、床に落ちたナイフを拾い上げ、切っ先を右手で折る。そして、使い物にならなくなったナイフの柄を捨てながら、長剣の刃を右足のかかとで折る。
これで、ここにいるレジスタンスはすべてだろうか。静かに気配を探ってみたものの、周囲に人のそれを感じず、ふっと気を抜いた瞬間――突然、すぐ後ろに気配を感じて血の気が引く。考えるよりも先に銃口を向ける――手首を掴まれて腕をひねられる――左腕を曲げながら体を回転させ右手を背後へと振り下ろす――ガンッと鈍い音とともに腕で防がれる。
「――危ないナ」
「……っ」
「敵味方の気配くらイ、判別できないとだめだヨ?」
ツェレン隊長が、澄ました笑顔でそこに立っていた。顔の横に右腕を立てて、俺の右腕を防いでいる。俺が両腕を引くと、ツェレン隊長はあっさり手を離した。
「まぁデモ、警戒心がないよりはマシだネ。いい動きだったヨ」
「……失礼しました。ありがとうございます」
「ウン。それデ、こっちは3人だったのかナ」
ツェレン隊長は、倒れたレジスタンスに手錠を掛けながら言う。俺も倣って、廊下にいるレジスタンスを縛る。
「はい。そちらは」
「ボクのほうは2人。1人足りないネ」
2人目を縛り終えたツェレン隊長は、顎に人差し指を当てながら首を傾げる。
「どこだと思ウ?」
「わかりかねます」
俺は、レジスタンス3人をそれぞれ家具や柱に縛りながら答える。
「ンー」
考える仕草をしながらも、ツェレン隊長の視線は一点を見つめていた。俺は視線を追う。そこには、扉が壊れたエレベーターの穴があった。
「……エレベーター、ですか」
「正確にハ、その下」
にんまりと口角を上げたツェレン隊長は、エレベーターの穴へと近づき、下を覗き込みながら言う。
「仕事ハ、ここからだヨ」
エレベーターの入り口からロープを下ろし、下降する。第1層の床を突き抜けて、第2層に差し掛かる手前、コンクリートに囲まれた何もない空間に降り立った。壁には、人が1人通れるくらいの穴がぽつぽつと開いている。光源は天井と床にいくつかついていて、肉眼でも周囲の状況は確認できる。
そんな薄暗さのあるその空間の中央に、人影がひとつ、こちらを向いてイスに座っていた。後頭部で一つに結ばれた、腰よりも長く伸びた黒髪。吊り上がった薄茶色の目。空間に溶け込むような灰色の作業着と、黒いロングブーツ。一見ここの作業員と見紛う姿だが、腰に下げた2本のサバイバルナイフが、そうでないことを物語っていた。
「今日は早いじゃないか」
人影が立ち上がりながら口を開く。俺が言葉を返す前に、ツェレン隊長は俺の横を抜け、人影に歩み寄りながら声を掛けた。
「探したヨ。アイシャ・トーゴー?」
「は?」
アイシャ・トーゴーと呼ばれた人物――レジスタンス・トーゴー派の頭首は、顔をしかめた。
「アタシを探すだって? 言っとくけど、アタシはどこにも行っちゃあいないよ」
「ウン。そうみたいだネ」
「何が言いたいんだい。まだ条件を増やす取り引きでもしようとでも?」
歩み寄るツェレン隊長を睨みながら、トーゴーは続ける。
「フン。アンタらはアタシらトーゴー派のやり方が卑劣だって言うけど、アンタらだって大概じゃないか。好きにしな。ちゃんと約束さえ守ってくれるなら、何だってする。でも、もしアイツらに手ぇ出すようなことがあれば、アタシはすぐにでもアンタらをつぶしにかかるよ」
「フゥン?」
あと10歩ほど。それくらいの距離まで近付いて、ツェレン隊長は足を止めた。首を傾げながら、妙に明るい声で、まるで煽るように言う。
「約束、ネ。何のことかナ」
「き、さまっ……!」
瞬間、トーゴーは腰からサバイバルナイフを引き抜いてツェレン隊長に飛び掛かる。俺は右手で腰のホルダーから拳銃を抜き出し、トーゴーの右手に握られたナイフを撃つ。弾き飛ばされたナイフがトーゴーの右手から離れて、コンクリートの床に転がり落ちる。すかさず左手のナイフがツェレン隊長の頭上に振り下ろされる。ほぼ同時にツェレン隊長が体を落として左足を伸ばし、地に着いたトーゴーの足を払う。トーゴーは崩れかけた体勢を戻すように後方へ体を回転させながら、ツェレン隊長との距離を取った。
俺は、2人の様子と会話がかみ合っていないことに、違和感を覚えていた。そもそも、軍と取り引きをしたかのようなトーゴーの口ぶりに、疑問ばかりが浮かんでくる。ツェレン隊長は、いったい何をどこまで知っているのだろう。ツェレン隊長が、取り引きをしたのだろうか。
――君は何か、取り引きをしたとでも言うのかね
ふと、サカイ部長の言葉が脳裏をよぎる。ああ、今こんなことを考えるなんて。今はそうすべきではないと、かぶりを振って思考を止める。
気付けば周囲の小さな穴からゴーストが部屋へ侵入してきていた。一匹がツェレン隊長に噛みつこうとしていて、俺はそれを撃ち落とす。メタエネルギーコアが落下したのを皮切りに、部屋に入ってきたゴーストたちが俺へと注意を向ける。俺は体を低くし、跳躍する構えを取った。
ツェレン隊長とトーゴーへと視線を向ける。ツェレン隊長は腰からクナイを取り出して、トーゴーは床に落ちたサバイバルナイフを拾い直していた。そしてトーゴーが正面から飛び掛かる。ツェレン隊長はクナイで軽く受け流す。
すぐに視線をゴーストへと戻す。上から飛びついてくるゴーストを打ち抜きながら、横から飛んでくるゴーストを跳躍して避ける。もう一歩跳躍して振り返り、正面から追って来る2匹のゴーストの瞳に弾を撃ち込む。地に足が着く感覚を頼りに再度跳躍しながら、左手でもう一丁拳銃を取り出す。進行方向から飛んでくるゴーストの瞳に一発撃ち込みながら、その背後から飛んでくる3匹のゴーストを見遣って右足から滑り込む。すれすれでゴーストたちの背後に回り込み、閉じられた口を割くように撃つ。部屋の対角線にゴーストを5匹視認して、そちらへと駆ける。
横目でちらと、部屋の中央で対峙する2人を見遣る。ツェレン隊長が左手で小さなクナイを飛ばして、トス、トスと床のあちこちに突き刺しながら、右手に握ったクナイでトーゴーのサバイバルナイフを受け流している。ひたすら後退し続けている。たまにトーゴーの腕を蹴り上げて両側からの切っ先を免れながら、ただひたすら後退し続けている。
俺は5匹のゴーストの索敵範囲に滑り込む。5つの赤い目が一斉にこちらを捉える。すぐそばの2匹の目に銃口を突き立てて引き金を引く。メタエネルギーコアが落下するより先に、それぞれの奥に見えるゴーストの瞳へと弾を撃ち込む。カラカラッとメタエネルギーコアが落ちる音とともに、正面で口を大きく開けたゴーストのその口の中へと銃口を突っ込み引き金を引く。
最後のひとつ、カランとメタエネルギーコアが落ちる音を聞いて、俺は部屋の中央を振り返る。いつの間にか、床には無数の小さなクナイが刺さっていた。いや、床だけではない。天井にも、いたるところに小さなクナイが刺さっている。
ヒュンと、空気を切る音がして、視線を戻す。トーゴーのナイフがツェレン隊長の顔へと振り下ろされる瞬間だった。俺はとっさに銃を構える。――ぴた、と、突然トーゴーの動きが止まった。
「それ以上動くト、危ないヨ」
クツクツ。のどの奥で笑いながら、ツェレン隊長が言う。トーゴーと、わずか5センチメートルほどの至近距離で。
「キミがここまで能無しとは思わなかったナ。さすが、易々と騙されるわけダ」
「っ……黙りな」
まるで両腕を宙から吊るされたような体勢で止まったままのトーゴーが、唸るような声を出す。
「……アンタ、ここでアタシを殺しても意味ないんじゃないかい?」
「サァ? ボクには関係ないかナ」
まったく興味のない話題だと言わんばかりに顔から笑みを消して、ツェレン隊長は腕を組み、至近距離のままトーゴーを見つめる。
「それよりモ、キミが一体誰に何を言われてこんなところにいるのか、ボクは知りたくてネ」
「……な、まさかアンタ……!」
状況を察したのか、トーゴーは血の気が引いた顔になり、目を見開いた。唇が震え、絞り出すように言葉を続ける。
「アン、タ……ナオ・ツェレン、かい……」
「ヘェ? その名前は知ってるんだネ」
ツェレン隊長は、左手の人差し指で、トーゴーの顎を持ち上げる。少しでも動けば唇が触れそうなほど、顔と顔の距離が狭まる。気まずさに、俺は視線をそらした。
「どこの情報かナ?」
「……」
「フゥン。まぁ、いくら能無しでもさすがに言えないカ」
「くっ……」
視線を戻すと、ツェレン隊長は2歩ほど下がったところで腕を組み、自身のあごに手を添えながらトーゴーを見つめていた。何か言いた気に口を開こうとするトーゴーを、ツェレン隊長は手で制した。
「アァ、もうあんまりしゃべらないほうがいいヨ。これ以上しゃべるト、体中に張り付いた“糸”のせいで肉が切れちゃうからネ」
言われてトーゴーは、それきり押し黙ってしまう。よくよく見ると、天井や床に刺さったクナイから、四方八方へと透明な糸が伸びていた。そしてことごとく、その透明な糸はトーゴーの体に巻き付いている。動くとどうなるかを想像して、俺は顔をしかめた。そんな様子を察してか、ツェレン隊長はこちらに視線を向けると、にっこりと笑った。
アイシャ・トーゴーと、その他の5人のレジスタンスを連れて、俺とツェレン隊長は政府軍本庁舎に帰還した。一般の処罰とは異なるからと、彼ら6人の顔は布で隠され、裏口から、そのまま治安維持部・部長室へ連行することになった。理由は、その場では訊かなかった。
今回立ち入ったエリアを調査・整理しにロストシティへ戻り、報告書をまとめてサカイ部長に提出し、ようやっとすべての仕事を終えた俺は、部長室横の待機室で一人ぼうっとする。西日が差し込み、天井がまぶしい。宿舎へ戻ろうかと、イスの背にもたれていた体を起こしたところで、ドアノブが回される音が響く。扉へと視線を向けると、ツェレン隊長が立っていた。
「お疲れ様です」
俺は慌てて立ち上がる。少し、気を抜いてしまっていたことが恥ずかしい。
「ウン、お疲れサマ」
ツェレン隊長は俺の態度など気に留めていないようで、すぐそばまで来て、机に寄り掛かった。そのまま、前置きもなく話を始める。
「トーゴーの話で薄々気付いてただろうケド、政府内部でレジスタンスと取り引きしてるヤツがいるみたいなんだよネ。タダ、誰なのカ、その取り引きが何なのカ、何のためなのカ、何一つわからなイ。それで今、サカイサンの息がかかってる諜報部員にトーゴーたちの口を割らせてるんだケド、なかなかしぶといみたいだネ。何にも情報が出てこなイ。もっと簡単に吐くと思ったんだけどナ」
「……そうですか」
今回の任務で俺が選ばれた理由の一つも、サカイ部長の息がかかっているロストシティ治安維持部隊員だから、なのだろう。そして、出動前の、「取り引きをしたとでもいうのかね」というサカイ部長の言葉にも、納得する。少し、罪悪感で胸が痛い。ゆるゆると、視線が足元に落ちる。
「カインクン」
ツェレン隊長に名前を呼ばれて、ハッとして、視線を上げる。ツェレン隊長は俺と目が合うと、クスッと笑った。
「ダイジョウブ。サカイサンはキミがレジスタンスと取り引きしたなんて思ってないヨ。マァ、周りの幹部はうるさかったけどネ。だから、連中を黙らせるのにちょっとだけ情報が必要で、今朝は調べさせてもらったんダ」
「え……」
脳裏に、今朝の一枚の書類を持つサカイ部長の姿が浮かび、驚いて顔を上げる。俺の考えていることを察したように話をしたツェレン隊長を、俺はじっと見た。
「ツェレン隊長が、調査……されたんですか」
「ウン」
笑みを浮かべたままツェレン隊長は、言葉を続ける。
「あとハ、ボクの個人的な興味。ボクの部下になる人がどんな人間か、どんな人間と関わってるのか知りたくてネ」
この人は、戦闘だけでなく調査もできるのだろうか。――驚きのような、疑問のような、若干の恐怖のような感情を覚えて言葉を発せずにいると、ツェレン隊長は右の人差し指を立てて口元に当て、俺の変わりに言葉を発した。
「心配しなくてモ、キミがサカイサンから信頼を得てることはよく分かったヨ。だからと言ってはなんだケド、ボクにとっても信頼に足る人間だと嬉しいナ」
そうして目を細めて、ツェレン隊長は、俺にまっすぐ向き直り、はっきりとした口ぶりで言う。
「これから期待してるヨ、オルティス班長」
期待のこもった言葉を受けて、俺は姿勢を正す。視線を正面から受け止める。
「……ご期待に沿えるよう、尽力いたします」
そうして俺は、深く、ツェレン隊長へ頭を下げた。
[/font]