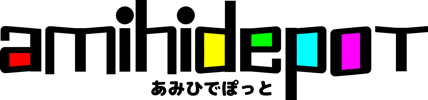パフェ専用の長いスプーンを右手で持ったまま、冬美は幸せそうな笑顔で、右頬を二度たたいた。
『おいしい!』
俺は「そっか」とだけ、唇を動かした。彼氏としては、もっと何かしらの反応をするべきなのかもしれないけれど、他に良い反応の見当が俺にはつかなかった。
俺の短い返答に気を悪くするわけでもなく、冬美はニコニコしながらチョコレートパフェをつつき続けた。そして、一口食べるたびに、このチョコは濃厚だの、下のコーンフレークは重みがあるだのと、逐一“両手”で説明してくれた。スプーンを握りしめたままの右手と、ひらひらと動き続ける左手を目で追いながら、俺は冬美の話題の引き出しの多さに感心した。
『あなたも食べる?』
冬美の両手がそう動いた次の瞬間には、チョコクリームとバニラアイスの載ったスプーンが俺の口の前に来ていた。俺は黙って、差し出されたそれを食べる。
『おいしい?』
『うん、おいしい』
『よかった! もう一口食べる?』
もう一口、と差し出された二口目に、俺は黙って首を横に振った。冬美は頷いてから、俺に差し出してくれた一口を自分の口に入れる。そして、パフェを食べながら――パフェがなくなるまで、昨日見た映画の舞台がとてもきれいだったこと、そして今度、その舞台になった場所へ遊びに行きたいのだということを、忙しなく両手を動かして熱く語ってくれた。
俺の彼女の菅野(すがの)冬美は、耳が聞こえない。先天性のものらしく、いわゆる“音”を聞いたことはないらしい。補聴器を着けてはいるけれど、以前「振動を感じるだけ」と言っていた。
冬美と初めて会ったのは三年前。聴覚障害者の祖父が参加した聴覚障害者団体の親睦旅行に、俺が祖父の同伴者として参加したときだった。参加者は年配の人が多くて、その中に、偶然にも同い年の二十歳過ぎの人――冬美がいた。彼女の同伴者は彼女の母親で、同い年だから話が合うだろうといって、俺と彼女を引き合わせてくれた。
ありがたいことに、彼女は口話(相手の口の動きから言葉を読み取り、自身も言葉を発して行う会話)が可能で、当時、手話をほとんど覚えていなかった俺とも、そつなく会話することができた。しかも彼女は相当の“おしゃべり”で、一泊二日の旅行が終わる頃には、半ば彼女のペースに巻かれる形で随分と親しくなっていた。
旅行団体が解散するとき、冬美が連絡先を教えてくれて、それから何度か遊んで、出会って一年後、俺は冬美と付き合うことになった。
ブラックコーヒーを飲みながら店内を観察していると、パフェを食べ終えたらしい冬美がテーブルをトントンと軽くたたいて、俺の視線を自分へと向けさせた。俺の視線を確認してから、冬美の両手が動く。
『今度、遊びに行きたい』
『映画の舞台になっていたところ?』
先ほどまでの会話の記憶を引きずり出しながら、俺は首を傾げて、両手を動かした。
『うん。隣の市だから、車で行きたい』
『誰の?』
『あなたの』
『俺の? 何で』
『だめ?』
『いや、いいけど……』
付き合うようになってからまだ一度も、冬美を俺の車に乗せたことがなかった。だから、冬美からドライブデートをしたいと申し出されて、驚いた。そして、少しだけ、初めてのことに恥ずかしくもなった。
『ただね』
冬美は、広げた右手を前後にひっくり返した。
『運転してるあなたと、話せなくなるのは、寂しい』
「あー……」
すんなり納得できてしまい、声が出る。耳が聞こえない冬美にとって、両手は「口」だ。その両手がハンドルに取られれば、それは俺の口がふさがったのと同義になる。横顔では、口話も難しい。それならと、俺は親指を曲げて、人差し指と中指を絡めた。
『電車は?』
『それは、ドライブではないよ?』
冬美はあくまでもドライブがしたいのだと、俺は理解した。冬美の「ドライブをしたい」という希望と「話したい」という希望。どちらも叶えられる方法は、しばらく考えてみたけれど、出てこなかった。右手の親指と人差し指を横に伸ばしたあと、人差し指と中指を伸ばして振り払った。
『ムリだよ、やっぱり。安全運転をするなら、両手は、ハンドルに取られる。きみを見るのも、難しい』
『なるほど……』
冬美は、顎の前で親指と人差し指を二度着けて、肩を落とす。そしてすぐに、頬を膨らまして、右手の人差し指と中指で、自身の鼻を軽くたたいた。
『嫉妬する! あなたの車のハンドルに!』
「……ぷっ、……あははっ」
思わず吹き出してしまう。表情が、その発想が、とても可笑しかった。そして何より、可愛いと思ってしまった。
『何、それ。何でハンドルに嫉妬するの?』
『だって、わたしの大好きな人の両手を、少しの間だけでも、独り占めする、でしょう?』
『……確かに、そうだね』
笑って頷きながら両手でそれぞれ親指と人差し指を二度着けると、冬美もにっこり笑った。
『これからは、ドライブするときは、ハンドルに嫉妬することにする。そうしたら、なにもしない時間がなくなるね!』
自分でもしっくりきた表現だったのか、冬美は満足気な顔で頷いた。
『その分、街に着いたら、たくさん話してね?』
『うん、話そう。たくさん』
俺たちには、手を繋いだまま話したり、手さげかばんを持ったまま話すことができない。だからこそ、今こうして両手が自由に使える時間は、こうも饒舌なのかもしれなかった。