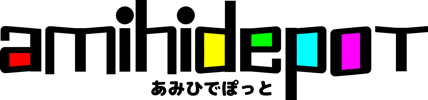[font]
駅前を歩いていて、突然声が耳に届いた。
「篠田さん!」
私の苗字。そして、どこかで聞いた声。呼ばれた気がして振り返ると、そこには、嬉しそうな笑顔で私の背後に立つ、きれいな顔立ちの、私より少し背が高い、小柄な男性がいた。
「すみません。見かけたのが嬉しくてつい。……あっ、覚えてませんか? 僕、ヘアサロン『パレット』の小田です」
「ああ」
覚えてる。いや、思い出したと言った方がいいかもしれない。私がよく通うヘアサロンのヘアスタイリスト、小田さん。確か、中高生の担当についてることが多かったはず。三十路の私の担当ではない。なのに、なぜ私を覚えているのだろうか。
「あの、よかったら連絡先交換してくれませんか?」
「はい?」
小田さんの手元にはスマートフォン。視線は手元に落ちていて、何やら操作した後に、「お願いします」と笑顔でこちらへ顔を上げた。
「いや、なぜ?」
「なぜって……お話したいんですけど。だめですか?」
小さく首をすくめ、しゅんと眉尻を下げて悲しい顔をする小田さん。いや、意味が分からない。担当でもない私の連絡先を、なぜ欲するのか。しかも「お話したい」って、どういうことだ。
「あの、私と話したいと思われる理由が、わかりかねるのですが」
「あっ……」
小田さんは急にぽっと頬を赤らめて、両手でスマホを握ったまま顔をそらす。その仕草に、私は“身構えていた感情”が少し外れる。この人は、私の苦手な“男性”とはちょっと違うかもしれない。
「えっと……」
もごもごと口を動かす小田さんを、上から下までさらっと観察する。ダボついた桜色のパーカー。フードだけ出した黒のジャケット。細い足のラインがわかる紺のスキニージーンズ。赤と白のスニーカー――威圧感のないシンプルな服装だ。体格はひょろっとした感じで、背丈も”ちょうどよく”、多分160センチ台。ブリーチされたふわふわの明るいミディアムショート。うん、かわいい。嫌いではない。
「……篠田さん、僕のタイプなんです」
「あ、ごめんなさい」
突然告白されて現実に戻される。そして、気づいたら脊髄反射で断っていた。
「私、男の人に恋できないんです」
***1話***
私の右手には、「小田 琴(おだ こと)」と書かれたヘアサロンの名刺が握られている。ついさっき、せめて受け取ってほしいといわれて、駅前で小田さんに手渡されたのだ。連絡先は、結局交換しなかった。まあ、あんなふうに断ったのだから普通は無理だろう。それでも名刺を手渡してきたのは、なかなかな勇気だと思う。そういえば、小田さんとヘアサロンでエンカウントしたのは何回だっけ。
「それで? その小田さんって人、連絡するん?」
「や、無理でしょ。私から振ったのに」
「そうよなー」
駅中のカフェでコーヒーを一杯買って、私は友人の日野 明日香(ひの あすか)と喋っていた。小学校からの幼なじみで、なんだかんだ地元に残って生活してる、独身女友達。
「けど、もったいないなあ。亜子、コクられたん初めてじゃろ?」
「まあ、そうね」
「あんたが男嫌いじゃなきゃよかったんになー」
「……そうね」
そう。私は男嫌い。特に、いかにも男性というような雰囲気の、背が高いとか体が大きいとか、威圧感や圧迫感を感じる人が、大の苦手だった。しかも、生まれてこの方本気で好きになったことがあるのは――自覚ある恋心を向けた人たちは、ことごとく女。年上の、頼れる女性だった。ただ、私が女性を好きだということは、身近な人には言っていない。目の前に座っている数少ない友人の明日香にも、言っていない。
自分が女性にばかり恋心を抱いていると自覚したのは最近のことで、それまで自分は、ノンケだと思っていた。なんなら、いわゆる“普通の腐女子”だと思っていた。男同士の恋愛に興奮する女。それがまさか、自分自身が同性愛者だとは、思いもしなかった。漫画や小説の中の彼らと同じような悩みを抱えるようになるとは、思いもしなかった。
「そういやさ、」明日香はタピオカミルクティーを飲みながら言う。「来週先輩帰ってくるん、楽しみじゃね」
「ああ……うん」
言われて私は、覚えている限りの先輩の姿を思い浮かべた。――榎本かずは先輩。八重歯がかわいくて、目はちょっと伏し目がちのたれ目で、身長は私よりほんの少し高くて、華奢で、ぱっつん前髪のさらさら茶髪ロングヘアで、胸がCカップの、先輩。小学校からの知り合いで、中学の時に漫画研究部で一緒になってから仲良くなって、高校も一緒に行きたくてランクを落として受験して追いかけた、憧れの先輩。教室へ遊びに行くとほかの先輩たちに私を自慢してくれて、あんまり笑わないクールな感じだけど私をからかうときはいつもニヤニヤ笑ってて、ちょっと悪ぶって私の肩に腕を回して話しかけてくれる、“憧れ”の先輩。今なら、はっきり言える。私は、かずは先輩に、恋をしている。昔も、今も、ずっと、変わらず。
お互い、大学は別のところに行って、帰省した時に会ったのが最後だった。もう、10年会ってない。私が電話番号を変えたことが原因で、連絡も、つい先日まで取れていなかった。それが来週の日曜日、やっと再開できるのだ。この駅で、待ち合わせ。何を着よう、アクセサリーはどうしよう、化粧はどうしよう、髪型はどうしよう。考えると、それだけで楽しくて、私の顔は締まりなく、緩んでしまう。
「うん……楽しみ、とっても」
かずは先輩の笑顔を思い浮かべながら、私はコーヒーに口を付けて、自然と目を細めて、つぶやいた。
土曜日。明日先輩に会う前に髪をきれいにしようと、いつものヘアサロンを予約した。残念ながらこの日、私の担当である白崎さんがお休み中らしく、予約した後にSNSで直接連絡が来た。
『篠田さんごめんなさい! 今週いっぱい、私、新婚旅行で不在なんです……。よろしければ、私よりも若いセンスで、篠田さんの好みに合う髪型が得意そうな腕のいい子がいるので、その子に担当してもらおうと思うんですけど、いかがですか? それか、男とか女とか、希望ありますか?』
『わざわざありがとうございます。白崎さんの紹介でしたら、どなたでも大丈夫です』
『ありがとうございます~! それでは、本人にも篠田さんのこと伝えておきますね!』
そんなやり取りがあった後。ヘアサロンに着いた私は、唖然とした。
「篠田さん、いらっしゃいませ! お待ちしてました」
「……どうも」
私を待っていたのは、先週の土曜日、駅前で会った小田さんだった。確かに、性別のこととかは言及しなかったけれども。よりによって、小田さんだなんて。いやでも、白崎さんの紹介なのだ。技術やセンスは、きっと間違いないのだろう。
「……今日は、休みじゃないんですね」
「先週ちょっと駅前に用事があって、あの日だけお休みをもらってたんです。ほんとに偶然なんですよ?」
私の荷物をロッカーに片付けながら、小田さんは困ったように笑う。うん、やっぱりこう見るとかわいい。こんな目で見るのは失礼だろうと思うけれど、なんとも受け受けしい、「男に抱かれそうな顔」だ。
「では、こちらへどうぞ」
イスへと案内されて、腰を下ろす。足置きへ両足を乗せると、イスがくるっと回転して、鏡越しに、小田さんと目が合う。ふわっと柔らかい笑みを浮かべて、可愛らしく小首を傾げながら、小田さんが口を開いた。
「今日はどうされますか? いつもはカラーもされるみたいですけど、今日はカットだけのご予約ですよね」
「はい。カットだけで大丈夫です」
「わかりました! それと、白崎から聞いているのですが、いつもカットはお任せなんですね。本日は、何かご希望のヘアスタイルがありますか?」
「いえ……お任せできるのなら、お願いします」
私の答えがそんなに意外だったのか、小田さんは目を点にして、私の顔を鏡越しにまじまじと見た。
「い、いいんですか?」
「ええ、別に」
私は思わず、振り返って顔を見上げる。何がそんなに意外なのだろうか。私を見下ろして直に目が合った小田さんは、「あっ」と小さく声を上げて顔をそらした。
「い、え……今日、初めてカットさせていただくので、お任せしていただけると思ってなくて……。う、嬉しいです」
頬を赤らめて、小田さんはこちらに顔を向ける。うん、やっぱりかわいい。これで攻めだったらびっくりだなってくらい、かわいい。いやいや、そうじゃなくて。いつもは男性を見たって、こんな想像しないのに。なんだっけ、ああ、私の髪型の話だった。
「……いえ。私も、あんまり似合う髪型とかわかってないので、自分で希望を言えないだけです。小田さんは、白崎さんが紹介してくださった方ですし、信頼できますよ」
私は鏡に向き直って、髪を結んでいたゴムを解く。下りた髪をとくように、小田さんの手が耳の後ろに入る。少し、気持ちいい。
「はは、ありがとうございます。……そうですね。このままロングでいくのと、ショートにするかだけ、決めましょうか」
「んー……じゃあ、ショートで」
「わかりました! それじゃあ、ばっさりいきましょう」
私の髪をといていた手を止めて、小田さんはメガネ受けを私の前に差し出してくれる。私がメガネをメガネ受けに置いた後、イスが回転する。そのまま、シャンプー台に案内されて、再度腰を下ろす。ひざ掛けが置かれて、「下げますね」という声の後に、背もたれがゆっくりと後ろに倒れていく。「失礼します」の言葉と同時にそっとガーゼを顔の上に載せられて、視界が遮られる。
「それでは、シャンプーしていきますね」
「はい」
シャワーからお湯の出る音がする。しばらくして、髪にお湯が掛かっていく。
「篠田さんのシャンプー、ほんとに久しぶりです」
「……そうなんですか?」
「あれ、覚えてないですか? ちょっと残念だなあ。僕ばっかり覚えてて恥ずかしいです」
笑い交じりのその声と、シャワーの温もりが重なって、すでに心地いい。ガーゼの下で、私は目を閉じる。
「篠田さん、かゆいところはありませんか?」
「はい」
「ありがとうございます」
だんだんと髪全体にお湯が掛かって、頭皮まで濡れてくる。ぬるさが、温かさに変っていく。
「6年前、まだ専門を出たばっかりで、初めてシャンプーをさせてもらったお客様が、篠田さんだったんです。あまりにも緊張でガチガチだったのが、篠田さんに伝わってしまって。あの時、僕、篠田さんに『緊張しすぎで、気持ちよくないです』って言われたんですよ。いや、もうほんと、恥ずかしくて」
小田さんは、言いながら軽く笑う。私はそんなことを言った覚えがないのだけれど、でも、小田さんが嘘を言っているわけではないだろうし。事実なら、とんでもなく恥ずかしいことだ。なんてことを言ったんだ、6年前の私は。
「それで、すごく凹んだんですけど、でも、切り替えなくちゃって。その後丁寧に洗うのを心掛けたら、篠田さん、『とても気持ちいいです』って言ってくださって……、ありがとうございました。ほんとに、救われました」
小田さんの声音は、とても嬉しそうだった。
「あの時から、緊張したときは、篠田さんのこと思い出すようにしたんです。そうすれば、緊張せずにシャンプーできたんで。なので、篠田さんは僕の恩人なんですよ」
「恩人だなんて……」
それは、さすがに言いすぎだ。多分、6年前の、24歳の私は、まだ世間を知らないガキも同然だった。ただ目の前でおどおどしている男の子を見て、くだらない世話を焼いたに過ぎないだろう。
「大げさじゃないですよ。あれから僕、シャンプーだけじゃなくて、自分の技術に自信が持てるようになったんです。あれから、篠田さんの担当になれたらって思ってたんですけど、先に白崎がついてしまったので、シャンプーも、カットもする機会がなくなってしまって。なので、今日はほんとに嬉しいです」
「……そうですか」
なるほどこの人は、私の知らないところで、6年間、私を見ていたということか。私は何も、覚えていないけれど。
それからしばらく、言葉はなくて。気が付いたら、指圧が気持ち良くて、うとうとしてしまった。おぼろげに、頭にタオルを巻かれる感覚があって、「失礼します」の言葉と同時に、顔の上のガーゼが持ち上げられる。意識がフッと、現実に引き戻された。
「お疲れ様でした。起しますね」
背もたれが起き上がる。何度か目を瞬かせている間に、ひざ掛けがスッと除けられて、もとの席へと案内される。また腰を下ろして、イスが回転して、今度は首の周りにタオルが巻かれる。次いでクロスを被せられ、鏡越しに、小田さんと目が合う。
「それじゃあ、カットしていきますね」
「はい」
私の頭に巻かれていたタオルを取って、小田さんは髪をといていく。人に髪を触られるのが心地よくて、私は黙って目を閉じた。
ブォーと、熱風が頭に掛かる。いつの間にか寝落ちていたらしい。鏡を見ると、肩下まであった髪が、顎の上まで短くなっている。本当に、ばっさりいったようだ。
「篠田さん、おはようございます」
「……すみません、寝てしまって」
「いえ! お疲れなんですね。後でマッサージさせてください」
「ありがとうございます」
メガネがないから、詳しくは分からない。でも、今までになく、結構短くなってしまったようだ。
カチッとドライヤーのスイッチを切る音がして、「整えていきますね」という小田さんの声が耳元で聞こえる。私は小さく、「はい」とだけ返した。
ひたすら、静かに、ハサミの音が響く。髪を引っ張り伸ばして切って、引っ張り伸ばして切って。心地よさに、また目を閉じる。
「明日は何かご予定があるんですか?」
髪を切る手は止まらず、小田さんから質問される。私は閉じていた目を開けて、鏡越しに小田さんを見つめた。
「……好きな人に会うんです」
「へえ、それは楽しみですね!」
告白してきた人に対して、いじわるのつもりで言ったのだけれど……。私の予想に反して、小田さんの反応は、とても明るかった。メガネがないせいで、小田さんがどんな顔をしているかは見えない。
「じゃあ、デートですか?」
「いえ……そういうわけではないです。随分と久しぶりに会うので」
「そうなんですか。いっぱい話せるといいですね!」
「はい」
いっぱい、話したいことがある。大学での生活。社会人になってからのこと。先輩と連絡できなかった間のこと。どう切り出そうか、なんと言って話そうか。あれこれ想像するだけで、あっという間に時間が過ぎてしまう。
ハサミの音が止まって、頭全体にくしがはいる。クリームの付いた手でくしゃくしゃと髪を握られて、頭が一層軽くなった。
「はい、お疲れ様でした~」
私はメガネに手を伸ばす。小田さんが鏡越しに大きな手鏡を持ってくれる。なるほどばっさり、後ろ髪が耳の下までしかない。前髪は作らず長いままで、サイドだけ顎下まである。襟足もがっつり切られていて、首元が涼しい。全体をクリームでくしゃくしゃに波打たせているから、雰囲気はとても軽め。もともと細い毛なのもあって、悪くない感じだ。お気に入りのメガネにも、雰囲気が合っている。
「どうですか? 僕イチオシの、篠田さんに似合うヘアスタイルだと思うんですけど」
「はい、ありがとうございます。気に入りました」
「ほんとですかっ? わぁ、ありがとうございます~! 頑張って良かったです」
小田さんは照れ臭そうにはにかんだ。ああ、本当に。男なのにこんなにかわいくていいのだろうか。下心のある私の視線は気にせず、小田さんは鏡を下ろすと、「それじゃあ」と両手を握る。
「マッサージして終わりますね」
「ああ……お願いします」
そういえばそんな話だったと、ちょっと前の会話を思い出す。大きな手が両肩に載せられて、ゆっくりと、肩甲骨の間に指が入る。気持ちよさに身を委ねて、私はもうしばらく、目を閉じることにした。
[/font]