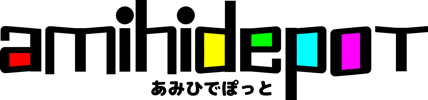[font]
花柄の白いフレアチュールスカート、薄手で桜色のオーバーニット、タートルネックの白いシャツ、グレーの三つ編みヘアバンド、紺のタッセルピアス、お気に入りのメガネ。愛用の、白と紺のチェック柄のショルダーバッグで、完璧。
「よし」
先輩に、かわいいって、言ってもらえたら、嬉しいな、……なんて。
***2話***
スマートフォン片手に、駅の南口に立つ。土曜日の13時。周囲の人の往来は相変わらず激しくて、この中に先輩がいても見つけられないんじゃないかと不安になる。なんなら、私を見つけてもらえないんじゃないだろうか、忘れられてしまうんじゃないだろうか、と。
「ふぅ……」
ため息。きっとこれは恋煩いだ。先輩を待つときは、いつだってそうだった。高校時代、登校時間の待ち合わせのときも、下校時間の待ち合わせのときも。まだかなと思うたびに、今日はもしかしてと不安になって、そわそわして。それで、私を呼ぶ声が聞こえたら、いつだって胸が高鳴った。
「篠田!」
「っ!」
がばっと、顔を上げる。声のした方を向いて、思わず涙しそうになる。――かわいい八重歯も、ぱっつん前髪も、肩まで伸びたさらさらな茶髪も。その華奢な体も、伏し目がちなたれ目も変わらない――榎本かずは先輩が、ちゃんと、そこにいた。
「先輩、お久しぶりです……!」
「うん、久しぶりー。変わらないね篠田」
「ええ、先輩も変わらないですよ」
どうしようもなく、顔が緩んでしまう。先輩は相変わらず軽い笑顔で、飄々としていた。ああ、このさばさばした感じが、たまらなくかっこいい。
「篠田、もう昼食べた?」
「いえ、まだです。先輩は?」
「うん、あたしもまだ。何食べる?」
「先輩の好きなのでいいですよ」
「えー、じゃあそこのカフェ入る?」
「はい」
こうやって並んで歩くだけで、嬉しい。10年ぶりなのに、何も変わらず会話できていることが、嬉しい。どうしようもなく、心臓がどきどきしてるのが分かる。胸に手を置いて、ひとつ、深呼吸をした。そのまま横目で、かずは先輩をちらと見やる。春らしい、薄手の黄色いカーディガン。白い開襟シャツ。膝丈の黄緑色のプリーツスカートに、茶色いパンプス。清楚な感じ。すごく、好き。
カフェに入って、二人してコーヒーとサンドイッチを頼んで、奥の席に座る。向かい合う形になって、正面から、ばっちり目が合う。テーブルに頬杖をついて、先輩が口を動かした。
「で。篠田ぁ」
目を細めて、にやにやと笑うその顔に、私の耳が一瞬で赤くなるのがわかる。ああ、どうしようもなく、私は、この人の、この表情が、声が、大好きだ。
「はい……」
「何で電話番号消したん?」
「え、と。それは、間違って……」
「ホント?」
「ほ、ほんとです。あの時は、ほんと、同級生との連絡断ちたくて……それで、多分、うっかり先輩のも、一緒に……ごめんなさい……」
「ふぅん? まあ、いーけどさ」
先輩は、テーブルに置かれたトレーからサンドイッチを取って、頬杖をついたまま一口、かぶりつく。ああ、食べるしぐさもかわいいな。
「りっちーに聞いたらまだ篠田ここにいるって言うからさ、びっくりしたじゃん。りっちーが連絡先教えてくれなかったら会えなかったんだよ? また後でりっちーにお礼言っときな?」
「はい、律子先輩にも、ほんと、お世話になりました……」
りっちーとは、荒木 律子(あらき りつこ)先輩のこと。中学時代、いつもかずは先輩と一緒にいた先輩だ。高校は別々だったけど、休日はよく、一緒に遊んでたらしい。私は、律子先輩が苦手で、あんまり一緒にいた記憶がないけれど、中学の時、かずは先輩と同様にお世話になっていたから、連絡先だけは交換していた。
「んで?」ぺろりとサンドイッチを平らげたかずは先輩は、頬杖をつきなおして、首を傾げる。「あれからどうしてたん?」
「えっと……どうしてた、とは」
「大学とか、就職とかさ」
「ああ」
それは、私も聞きたかったことだ。
「私は、一浪して、Y大出て、今、地元誌の編集してます」
「Y大の何学部?」
「文学部です……」
「ふぅん。篠田らしいね」
言って、先輩はコーヒーをすする。私も、一口サンドイッチを食べる。
「……先輩は、どうしてるんですか?」
高校を出て、T大薬学部に進学したかずは先輩。いつ勉強したのか分からないくらい、いつも飄々としていて、よく遊んでいた、謎の多い先輩。塾に行くこともなく、いつも部活終わりの私と一緒に下校してくれた、優しい先輩。うちの高校から史上初、T大に行ったことで一躍有名になった、頭のいい先輩。
「ん、製薬会社勤務」
「あ……研究所に入ったんじゃないんですね」
「なんで?」
「え……先輩、研究者の白衣に憧れて薬学部に進学した、って言ってたので……」
「そんなこと言ったっけ?」
「はい……」
「ははっ。それ冗談だよ」
「そうですよね……」
冗談なのは、分かっていた。 けれど、かずは先輩が言うと、こうも真実味を帯びてしまうのは、なぜだろう。
「まあ、でも、製薬会社でも白衣は着てるよ。ん? ってことは有言実行? わーすごいあたし天才? かっこいい?」
「あはは。先輩さすがです」
冗談で言ってのける自信過剰な発言も、かずは先輩が言うと様になって。それも憧れの要因だったりする。本当に、非の打ち所がない人だ。
「そーいやさ、篠田、仲いい子いたじゃん」
ふと話が切り替わって、かずは先輩の視線が宙を見る。先輩の言う「仲いい子」という単語に、私は血の気が引いた。
「なんだっけ、しの、しの……」
「……篠原、ですか」
「そーそー、篠原さん。元気にしてる?」
「……ええ、と」
篠原あやの。私が高校時代、3年の2学期“まで”仲が良かった子。絶縁して、今は何も知らない人。――実は、一番、恋していた人。
「……高校卒業するときに、縁、切れてしまって」
「あれ、そーなの?」
「はい。先輩の電話番号を間違って消してしまったのも、それが原因で」
「ふぅん? なんかあった?」
「……まあ、いろいろと」
かずは先輩に隠し事はできない。けれど、先輩が卒業したあとのことを、どこまで説明すればいいのだろう。正直なところ、何も言いたくはない。先輩には、何も関係ないのだから。
「ふぅん、いろいろねー。あんな仲良かったのにね、そっか」
「……はい」
「あんな仲良かった」と評するくらいには、先輩の目には、仲良く見えていたのだろう。事実、絶縁するまでは、本当に仲が良かった。でも、今ではもう、名前と、最後に言われた言葉しか、記憶にない。顔も、声も思い出せない。
「あの。先輩は、篠原のこと、覚えてるんですね」
「んー、そんなに? あたしが卒業したあと、篠田がぼっちにならないかって心配してたからさ、いっつも一緒にいる子がいてよかったなーって、安心してたくらいで。あたしはあの子のこと良く知らないし」
「ああ……そう、なんですね」
「あたし、別に部活もしてなかったから、後輩とかいないし」
スッと、かずは先輩の右手が伸びてきて、思わず私は、ギュッと目を閉じる。私の頭に、先輩の手が触れる。
「だからさ、篠田はトクベツなんだよ」
「……はい……」
30歳にもなって、頭を撫でられながら、トクベツだと言われて。恐る恐る開けた目に映ったのは、先輩の細まった目と、八重歯の見えるニヤついた口元。この人のことが好きだと、勘違いしてしまう。いや、勘違いなどではなくて本当に、好きだ。ただ、でも――口が裂けても、そうだとは、言えないだろう。私は女で、先輩も女。同性で、ただ仲がいいだけの、先輩と後輩なのだから。
このまま死ぬまで抱え続けるだろう気持ちにいたたまれず、かずは先輩の顔から視線をそらして、ふと、頬杖をついている先輩の左手に目が留まる。薬指の、指輪。
「………………あの、先輩」
「うん?」
左手の薬指には、どんな意味があったっけ。今の今まで舞い上がっていた感情が、一気に冷めていくのを感じる。見てしまったものを否定したい気持ちと、事実を確かめたい気持ちが、私を揺さぶる。
「その、左手の指輪って……」
「ああ、これ?」
聞きたくない、知りたくない。ただのオシャレだと言ってほしい。私を驚かせようとしただけだと言ってほしい。そう思うのに、耳を塞ぐことは許されなくて。
「ごめん。言うの忘れてたけど、あたし結婚したんだ、2年前に」
現実は、想像するよりも残酷だ。
あれから、どんな顔をして会話したか、はっきり覚えていない。ただ、笑って「おめでとうございます」と言った。「ほんとは結婚式にも呼びたかったんだけどね」と言われて、「先輩のウェディングドレス姿、見たかったです」と返した。覚えているのは、それくらい。先輩が言うことに、調子を合わせて笑って、笑って、笑ったような気がする。心の準備をする余裕など与えられず、眼の前に大きな壁を突きつけられたような感じ。叶うなんてこれっぽっちも思っていなかった恋だけれど、いつか風化して消えていくのを望んでいた恋だけれど、やっぱり勘違いだったって笑い話にできると信じていた恋だけれど――こうも、あっけなく終わるとは、思わなかった。
かずは先輩と別れた後、私はその場で、泣いた。先輩の目を気にして笑わなくていい安心感と、人知れず恋心を拒絶された絶望感で、涙があふれた。それでも周囲の目は気になって、家へと向かいながら涙を拭い続けた。ただ、一向に止まることはなくて、とうとう帰宅するまで、涙が止まらなかった。
自室に戻った後、私は疲れ切ってベッドに崩れ伏した。何も、する気が起きない。ぼんやりと自分のカバンを眺めていると、ふと、名刺が目に留まる。――「小田 琴」と書かれた名刺を取り出して、それから、スマートフォンを取り出す。――SNSに連絡先を登録して、メッセージウィンドウを開く。
『来週の土曜日、13時半から、カラーできますか』
今はただ、気分を変えたくて。そのメッセージを、私は彼に、送信した。
次の土曜日。ヘアサロン『パレット』で私を待っていたのは、白崎さんだった。
「篠田さん、お待ちしてました!」
「あれ……えっと」
「あっ、もしかして小田がよかったですか?」
「あ、いえ……お久しぶりです」
「ああ! はい、お久しぶりです!」
白崎菜々さん。ベリーショートくらいに短い髪と、大振りのピアス、おしゃれな帽子がトレードマークのスタイリストさん。身長142センチととても小柄ながら、いつもパワフルで、はつらつとした人だ。
お互い慣れたもので、私は持っていた荷物を白崎さんに渡して、白崎さんは私の荷物をクローゼットに片付ける。
「それで。篠田さん、やっぱり小田が良かったですか?」
「えっ」
「そうですよね、わざわざ小田に直接連絡くださったんですし。それなのに小田ったら、自分は担当じゃないし、指名料をもらうのも申し訳ないからって、奥に引っ込んじゃって」
「そう、なんですね」
白崎さんの言う通り、確かに、小田さんがカラーをしてくれるのを期待している自分がいた。けれど、それはこっちの勝手な希望で、私の担当は白崎さんなのだから、別に白崎さんでも、構わない。
「でも、いいですよ。私の担当は白崎さんですし、無理に小田さんにお願いもできないですから」
「よくないですよ」
荷物を仕舞ってレジカウンターから出てきた白崎さんは、私を席へ案内しながら言う。
「先週、なにか理由があって、私ではなく小田に連絡をくださったんじゃないんですか? 私は確かに篠田さんの担当ですけど、それ以前に、まずは、篠田さんがうちを利用して、心も体も癒やされて帰ってくださるのが一番です。担当替えであれば、指名料もいただきませんし、小田のほうが良ければ――そりゃあもちろん、私の担当から外れるのは寂しいですけど――今すぐにでも、担当替えだってできますから。遠慮なく言ってください」
明るい笑顔ではっきりと言う姿が、自身に溢れていて、たくましい。かっこいい人とは、こういう人のことを言うのだろう。たとえこれが仕事柄作っている姿だとしても、他人に“そう思わせる”ことは、芯に強さがないと、できないと思う。
「……ありがとうございます。では、」白崎さんの笑顔に後押しされて、私の口から本音が漏れる。「小田さんに、担当替え、お願いできますか」
「はい!」
白崎さんは、イスに腰を下ろした私へ、鏡越しに、とてもかわいい笑顔で答えてくれる。そうして、「小田を説得してきますね」と言って、レジカウンターの奥のスタッフルームへと消えていった。広い店の中に一人、取り残される。静かな、時間。
ふと、鏡の中の自分を見ながら思う。――なぜ、小田さんをお願いしたのだろう。確かにこの髪型は気に入っている。けれど、髪を切ったところで、かずは先輩はすでに、手の届かないところに行ってしまっていた。もう、何も変えられない。私が変わることもない。むなしさが胸いっぱいに広がって、どうしようもない。かといって、この髪型にしてくれた小田さんに対して、八つ当たりするのも違うだろう。小田さんに、私は何を言いたいのだろう。何も、話せることなんてないじゃないか。
「篠田さんっ」
声を掛けられて、ハッとする。鏡越しに、私の背後に小田さんが立っていた。ずっと鏡の中の自分を見ていたはずなのに、いつの間にか、視線が足元へと落ちていたようだ。
「あの、僕に担当させてもらっ、あの、ああありがとうございますっ」
「……ふっ」
美容師はみんな、心に余裕があると思っていた。だから、こんなにもあがっている小田さんがおかしくて、思わず吹き出してしまう。顔は真っ赤で、目がうるんでいて、両手を胸元でぎゅっと握っていて。まるで、女の子だ。
「わっ、笑わないでくださいよ~……僕、ほんとに驚いたんですからね?」
「そうなんですか?」
鏡越しではなく、直接見ようと、私は背後を振り返る。鏡越しと変わらない、顔が真っ赤な小田さんが、そこに立っていた。小田さんは私と目が合ったことに緊張が増したのか、目をぎゅっと閉じた。
「そ、そうですよ! 今日は白崎さんがあっ違、白崎がいますから、僕が担当する理由なんてないじゃないですか! なのに、指名を、しかも担当替えだなんて。嬉しいですけど、びっくりです!」
「そう、ですね」
自分でも、よくわからない。ただ、漠然と、小田さんと話したいと思ったから、指名したんだと思う。指名料をもらうのを気にしているようだったから、いっそのこと担当替えをしたんだと思う。それで話せるなら、それでいいと思った。
「あっ、すみません僕の話をしてしまって。本日はカラーでしたよね!」
「ああ、はい」
仕事モードに切り替えたのか、パッと明るい笑顔になって、小田さんは鏡越しに私の顔を見る。私も、鏡へと向き直った。
「何色がいいですか? 何か、ご希望の色とかありますか?」
「いえ、特には……お任せで」
「そうですか。何か、染めたい理由とかありますか?」
「……ちょっと、気分変えたくて」
「そうですか~」
深く、訊ねられるだろうと思った。けれど、小田さんはにっこり笑って。
「じゃあ、パッと気分の変わる髪色にしましょう! ちょっと待っててくださいね。カラー表持ってきます」
小田さんは一瞬、部屋の奥に消えて、手に本を持って、すぐに戻ってきた。私の前に本を広げて、細かく色の分かれたサンプルを見せてくれる。
「大体のお客様が希望されるカラーだと、ここからここまでの明るいレッドとかイエロー辺りなんですけど、篠田さんの好み的にはどうですか?」
「ううん……こういう色だと、派手過ぎる印象ですね」
「なるほど。明るさはどれくらいがいいですか?」
「んー……できれば、明るいほうがいいです。明度は上げて、彩度は抑えたいです」
「うーん。じゃあ、こっちのグリーンとかブルー系はどうですか?」
パラパラとページをめくって、別のサンプルを見せてくれる。
「これくらいの。例えばこのグリーンアッシュとか。マットな感じで、しかも透け感があって明るく見えて、軽い印象も受けますし、レッドやイエロー系よりも落ち着いた印象になると思います」
指差された先のサンプル。モスグリーンのような、苔色のような、それでいて透けたような印象を受ける髪色。
「……きれいですね」
「ですよね。これ、篠田さんにすごく似合うと思います」
すごく、好きな色だ。サンプルを見ただけなのに、心が、ぐっと惹きつけられるような、そんな気持ちになる。迷うことなく、私は頷いた。
「じゃあ、これで」
小田さんは、私の顔を見て、にっこり笑う。
「はい! それじゃあこれにしましょう。一度、シャンプーしますね」
染まり上がった私の髪は、本当に、きらきらしていた。今まで染めたことのない髪色で、自分でも、雰囲気がこれまでと違うのが分かる。
「篠田さんの髪、ほんとに綺麗ですよね。カラーしたのに全然傷まないですし」
「そうなんですか?」
「そうですよ! やわらかくて細くて自然なウェーブが掛かってて。それでいてカラーして傷まないんですから、ほんとに綺麗な髪です」
ドライヤーで髪を乾かしながら、小田さんは私の髪を褒めてくれる。そういえば、以前、白崎さんも同じことを言っていた気がする。
「……ありがとうございます。本当に、好きな色です」
「えへへ。僕の染めた色で喜んでもらえて、ほんとに嬉しいです」
鏡越しに照れた小田さんを見遣る。その笑顔は、仕事の笑顔だろうか。それとも、本心なのだろうか。どちらでも構わないけれど、――今この瞬間、小田さんの笑顔を見ていると、とても安心できる自分がいたのは、嘘ではなかった。
[/font]