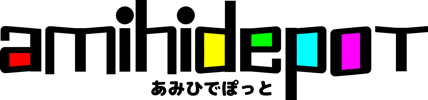[font]
『お話させてもらえませんか?』
そんなSNSのメッセージが小田さんから届いたのは、髪を染めてから三週間後。5月が始まったばかりの、日曜日の夜のことだった。
***3話***
大型連休。5月3日、月曜日の、昼下がり。駅中のコーヒーショップにて。今、私の目の前には、小田 琴という名前の、27歳の男が座っている。かれこれ10分、ずっと、黙ったまま。
「……」
「……」
小田さんが昨日の夜、話したいとSNSで連絡してきて、特に用事のなかった私は、何も考えず了承した。とはいえ、私からは何も話すことがなくて、小田さんからの言葉をずっと待っているのだけれど。緊張しているのか、小田さんはずっとコーヒーを両手で持ったまま、黙っている。
「……」
「……」
「……はあ」
「ご、ごめんなさい……」
「いえ」
「……」
店に入って10分。もう、ずっとこんな感じだ。こちらを見つめては、両目をつむって、縮こまって。深呼吸をして、コーヒーを飲んで、もう一度こちらを見つめる。口を開きかけて、声が出なくて、うつむいて、ため息をついて、もう一度顔を上げる。いつもの私なら、こんな状況、途中で投げ出しているところだ。それでも、小田さんが私に何かを伝えようと必死なのが伝わってきたから、私はむげにできないで、10分間、ここにいた。
「……し、しの、ださん」
「はい」
やっと一言。名前を呼ばれる。なるべく優しく応えようとしたのだけれど、声が冷たくなってしまった。小田さんの肩がビクッと跳ね上がる。
「う……すみません」
「ああ、いえ、すみません、こちらこそ」
怖がらせてしまったことが申し訳なくて、視線を逸らす。さて、あとどれくらい待てば、本題に入るのだろう。
「……やっぱり、こんな、」
小田さんがぽつぽつと話し始めて、私は慌てて視線を戻す。小田さんは、両手で持ったコーヒーを見つめたまま、神妙な面持ちで言葉を紡ぐ。
「こんな。男らしくない男じゃ、ダメ、ですよね」
「そんなことありません」
脊髄反射で、思わず私は否定した。小田さんの顔が上がって、驚いたその目と、視線が合う。私の口は、止まらなかった。
「私、いわゆる『男らしい男』が苦手で、生理的に受け付けないんです。なんとか仕事上の付き合いはできるんですけどそれも結構精一杯で、いつも精神的にすごく疲れます。背の高い人とかガタイのいい人とかは本当にダメで。見た目だけで威圧感ばかり感じてしまって……ああ、相手はもちろん、そんなつもり一切ないんでしょうけど……。なので私は、小田さんのような柔らかい雰囲気の方相手だと、『男性だから』と身構えたりせず関われるので、すごく落ち着きますよ。だから、ダメなんかじゃないです。そんなことありません」
「……」
「あ……」ぽかんと私を見つめる小田さんの視線にハッとして、脊髄反射で否定した自分自身に驚いて、私は慌てて繕う。「す、すみません。小田さんの話ですよね。ごめんなさい、私の話をしてしまっ――」
ぽろっと、小田さんの目から涙がこぼれて、私は言葉を失った。涙がこぼれたことに、今度は小田さん自身が驚いた様子で、「すいません」と言いながら、慌てて涙を拭う。
「す、すいませっ……嫌われたんじゃないって安心したら、なんか、急に、すいませんっ……」
「あ、ああ、目、傷付きますよ。そんなこすったら」
「うっ……すいません……」
流れ出したら涙が止まらなくなったのか、小田さんは服の袖で目をこすり続ける。ミニタオルを差し出すと、また「すいません」と言いながらそれを受け取って、両目を押さえた。しばらく鼻をすすった後、顔を上げて、赤くはれた目をこちらに向ける。そして、困ったように笑った。
「えへへ……よかったです。嫌われたんじゃなくて」
「……嫌いませんよ。小田さん、いい人ですし」
「でも、一応男です」
「そうですね」
「えへへ……」
笑ながら、もう一度だけ、目を拭いて。小田さんは、今度はまっすぐ、私を見た。
「篠田さん。僕と、付き合ってほしいです」
「……、それは」
「でも、その前に、僕のこと、知ってほしいんです」
「……はい?」
その目は、とても真剣だった。私は、受け止めきれず、視線をテーブルに落とす。逃げてはいけないのに、逃げてしまう。
「僕。“一応”男ですけど、ほんとは、女の子の体になりたいと思ってました」
「……?」
突然のカミングアウトに、私は逃げてしまった視線を目の前の男の人に戻す。いや、このカミングアウトは別に、突然でもないだろう。出会ってこれまでの小田さんの、外見を、仕草を、言動を思い返せば、不思議ではなかった。きっと、小田さんは“これ”を伝えるために、今、私の前に座っている。
「変なこと、言ってるかもしれません。でも、僕にとっては、大事なことです。きっと、篠田さんが、『男性に恋できない』って、『男らしい男が苦手だ』っていうのと、同じように。……僕は、僕は確かに、心も、体も男です。でも、できることなら、女の子みたいに、かわいい体になりたかった。男だから、かわいい服もなかなか着られなくて、でも、女装家だとは、言われたくなくて。心まで、女の子にはなりたくなくて。だから、今まで、男でも変に言われないくらいの、かわいい服を選んで、着てました」
自分の服をギュッと掴んで、唇をグッと結んで、小田さんは少し俯く。
「……僕、こんなですけど、ゲイじゃないです。バイセクシュアルでもないです。かわいいとは言われたいですけど――体だけ女の子になりたい願望がありますけど――別に、男が好きなわけじゃないです。服も、髪も、顔も、着飾ったり、染めたり、化粧したりして、ただ、可愛くなりたいだけなんです。男を好きになりたいわけでも、心まで女の子になりたいわけでもないんです」
不安そうに、こちらへと視線を向ける。
「僕、今まで、誰かを好きになったこと、ないんです。僕のこと、好きって言ってくれる人は、いました。僕が“ああなりたい”って思うようなかわいい子に告白されて、付き合ったことは、3回、あります。でも、いざ、付き合って、『ほんとは、体だけ女の子になりたかった』って、『女の子の服が着たい』って言うと、やっぱりおかしいみたいで、ちょっと引かれて。そこから先、うまく付き合えなくて。そうやって……3人とも、別れました」
私は、黙って話を聞くことしかできず、向けられた視線を、受け止めた。いや、正しくは、不安に揺れる小田さんの瞳が、私に何かを訴えていて、まるで縋られているようで、目をそらせなかった。
しばらく黙って見つめ合っていると、小田さんは困ったように小さく笑って、視線を、冷めきったコーヒーへと落とした。
「……おかしい、ですよね。僕の性って、やっぱり、ずれてる。でも、僕は、自分の『かわいい』の部分を、否定したくなかったんです。だから、全身、自由におしゃれできるんじゃないかって、スタイリストを目指しました。おしゃれで、自分の持ってるもの、全部表現できるし。何より、隠さなくていいし。我慢したり、無理にごまかしたりしなくていいし」
小田さんはひとつ深呼吸をして、視線を上げる。再度私を見つめる瞳はすごくまっすぐで、強い意志が感じられた。真剣そのものだけれど、そこに威圧感やとげとげしさはない。私は、今度は逃げることなく、その視線を受け止めた。
「僕を好きだと言ってくれても、それはきっと見た目だけだったから。だから、専門に入るとき、もう誰に告白されても、付き合わないようにしようって決めました。その代わり、僕が『好き』って思った人には、僕のことちゃんと話そうって、話したうえで僕を受け入れてもらえたら、そしたら付き合おうって、決めました。専門在学中には、『好き』って思う人、いなくて。それで、卒業して、就職して、6年前、篠田さんとお話したとき、初めて、『好き』って、思ったんです」
言って、小田さんはにっこり笑う。その笑顔が私に向けられたものだということが、私には信じられない。私はそんな魅力的な人間ではないし、見た目をきれいに見せることも、かわいく見せることも下手だ。なのにどうして、と思う。
「篠田さんは、あまり、外見にこだわらないですよね」
「……え、ええ」
突然話を振られて、一瞬返答に迷う。小田さんは、小さく笑みを浮かべたまま、冷めきったコーヒーを両手で持って、その中へ視線を落とす。
「シャンプーしながら僕とお話してくださるとき、篠田さんはいつも、僕の見た目よりも、内面のことを見てくれました。もちろん、見た目のことも褒めてくださってましたけど、それだけじゃないというか、それよりも、内面のことを、『かわいい』って言ってくださったんです。覚えて、ないでしょうけど」
「……すみません」
申し訳なくて、ぽろっと言葉がこぼれる。小田さんは慌てて、パタパタと両手を振った。
「あっ、いえ! 別に、篠田さんが僕のことを覚えてないのは、そんなに、気にしてません。ちょっと寂しいけど、大したことじゃないです」
言ってまた、小田さんは視線をコーヒーに落とす。
「白崎さんが篠田さんの担当に付くまでの――僕がシャンプーさせてもらった1年の間でしたけど、篠田さんとたくさんお話するうちに、篠田さんのこと、好きになったんです。僕が『ほんとはもっとかわいくなりたい』って言ったら、『中身が十分かわいいんだから、自信持てばいい』って言ってくれたり。『身長が伸びて悲しい』って言ったら、『背が伸びてもかわいくいられるんだから頑張ってる証拠。胸を張っていい。そうやって努力してる姿が何よりもかわいい』って言ってくれたり。あまり着飾らない篠田さんが僕のピアスを見て、『真似したら、内面もかわいくなれるかな』って、真似してくれたり……。ほんとに、一つひとつ、篠田さんにとっては何気ないことだったかもしれないですけど、僕にとってはすごく嬉しいことで、大切なことでした。僕がそう在りたいと思った姿をまるっと受け入れてくれたことが嬉しくて――なんでもはっきり、僕に意見を言ってくれた篠田さんが、かっこよくて、好きになったんです」
言われながら、私は少しずつ、思い出していた。まだ接客が不慣れで、自信なさげで、若くて華奢な男の子。白崎さんのそばで熱心に技術の勉強をして、掃除と洗濯とシャンプーをしていた男の子。私の言葉に泣きそうになって、そのあと「ありがとうございます」と笑顔を見せてくれた男の子。話をするたび、「他のお客様には言えないですけど」と言って、自身の内面について話してくれた、女の子みたいな男の子。「篠田さんって、どんな人がタイプですか?」と質問されて、答えられないまま、忘れてしまっていた男の子――――。
「――ああ……」
すっかり忘れていた。あんなにいろいろと話したのに、白崎さんが私の担当についてからは、まったく話さなくなって。小田さんも担当を持つようになったのを知って、なんとなく心が疎遠になってしまって、意図して意識しないようにしていた。そんなことを今更になって思い出して、驚きと、申し訳なさで、私は右手で額を押さえる。
「……突然、こんな話をして……重い、ですよね」
小田さんは一人、力なくうつむいて、首を振って、また顔を上げる。
「ううん。でも、それだけ、僕は真剣に話してます。軽い気持ちで、付き合ったり、したくないんです。ちゃんと、篠田さんに、分かってもらいたいんです」
「……そう」
私は、何と返したらいいのか分からなくて、口ごもってしまう。額を押さえていた右手と視線が、ゆるゆるとテーブルの上に落ちる。
「篠田さん」
小田さんにしてははっきりとした強めの口調で、私の名前を呼ばれる。視線は手元に落としたまま、耳だけ傾けた。
「僕は、自分はかわいく在りたいですけど、他人の姿まで、かわいいのを強要したりはしません。僕が僕から『かわいい』を奪われたくないのと同じように、他人の“その人らしさ”を奪いたくは、ないですから。だから、篠田さんが、どう在りたいと思っても、僕はそれを受け入れます。篠田さんが、以前、僕の在り方を受け入れてくれたように」
そうは言っても、私は――女の人にしか、恋をしたことがない。こんなふうに告白されても、小田さんに恋心を抱ける自信がない。まっすぐ向き合える自信が、ない。だから、顔を上げられない。
「以前、篠田さん、『男性に恋ができない』って言われてましたけど。僕みたいな“女の子みたいな男”は、難しいですか? 無理なら、諦めます。これ以上迫るのは、失礼だと思いますから。でも、チャンスがあるなら、お願いします」
正直なところ、女と男のどちらが好きなのか、私は自分が分からない。これまで恋をしたことがあるのは確かに女性ばかりで、男性は誰もが怖かった。でも、怖いと感じるようになったのは中学のときからで、怖いと思うようになったのは、兄弟家族や同級生など、身近な男性から受けたもろもろが原因で、本当は怖くない人だってたくさんいるんじゃないかと、どこかに私が安心して接することができる男性がいるんじゃないかと、信じたい気持ちもあった。
――一度、この気持ちを信じてみてもいいかもしれない。
私は、ぐっと視線を、顔を上げる。小田さんは不安の混じった、けれど真剣な眼差しを私に向けていた。目が合うと、ふわっと柔らかい笑みを浮かべて、すぐに自信なさげに眉尻が下がる。
小田さんの顔を見ながら、私は自分の気持ちを整理した。――自分は男のまま『かわいい』で在りたいとはっきり言った小田さん。私のことをかっこいいと評して、私のことを好きだと言った小田さん。私はこの人のように、自分の在り方を、自分の気持ちを、はっきりと言葉にできない。だから、こうもまっすぐなこの人が、とても眩しくて、すてきだと思えて、敵わないと思えて――なんだか、とてもうらやましく思えた。
私は、テーブルの上に置いた自分の両手を見つめて、手を握って、開いた。この手で、この人の気持ちを受け止めてみようと、両手を小田さんの前へ差し出す。
「……付き合って、みましょうか」
小田さんは、一度目を見開いて、それから、今にも泣き出しそうになりながら笑って、私の手を取る。
「はい!」
小田 琴、27歳。女の子のようにかわいくなりたい男の子――この人と付き合えば、私は、何か変われるだろうか。
[/font]