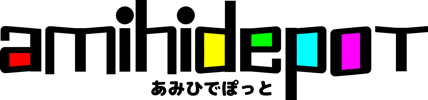[font]
メガシティ・トーキョーの地下に埋もれたロストシティ。その下層にあるトンネル内を、カインは歩き続けていた。トンネル内の電灯は、電力の供給が断たれてから200年が過ぎているにもかかわらず、ちらちらと発光している。この現象は、ロストシティに未だ存在し続けている多量のメタエネルギーの影響だ。電灯に限らず、都市崩壊以前に存在していた文明機械の一部は、今もなお、メタエネルギーの影響で作動し続けている。そして、メタエネルギーによって生まれた疑似生命体のゴーストも、活動が止まることはなかった。
「ぜんっぜん気配がねぇなー。もう歩いて3時間は経つってのに」
カインの左隣を歩く金髪赤目の青年――同僚のダズ・エンデリオンが、退屈そうに伸びをしながら言葉をこぼす。カインは薄暗いトンネルの先を見つめたまま「ああ」と短く返した。
「レジスタンスの活動を確認したのはC区だろ?居なかったし、それらしい痕跡もなかったじゃん。もう帰ろーぜ?」
「E区でマザーゴーストの生体反応があった。あと10分も歩けば着くだろう」
「はぁ……」
ダズは心底面倒だとため息をつく。仕事なのだから至極当然だと、カインはつぶやくように返した。そこからはお互い黙って、歩き続ける。カインの右足から発せられるカシャンカシャンという金属音が、トンネルの中で反響した。
マザーゴーストとは、自動車や電車といった大型の文明機械が、メタエネルギーによって疑似生命体になったものの総称だ。文明機械そのものが変容しているため、人的被害だけでなく、古代遺産保護の観点からも討伐を必要とする。また、標準的なゴーストのメタエネルギーコアは1センチ程度であるのに対し、マザーゴーストのメタエネルギーコアは1メートルを超えるものがほとんどで、メタエネルギー回収の観点からも、見過ごすことはできなかった。
カインがあと10分と言ってから10分。ちょうど目的のE区に差し掛かったところで、カインとダズは足を止める。二人の視線の先には、ふわふわと漂う蒸気の塊があった。あれこそがゴースト。メタエネルギーの結晶が蒸気をまとい、疑似的な生命を得た姿だ。蒸気の塊の中央に大きな口を持ち、その背面には、鈍く発光する赤い単眼が付いている。まだこちらには気付いていないようで、その漂う姿に生命体特有の意思は感じなかった。
「この奥だ」
言いながら、カインは腰のホルダーから抜いた二丁の拳銃を構える。
「見りゃわかるっての」
楽しみを見つけたようににやりと笑みを浮かべながら、ダズは腰から抜いた二振りの長剣を構える。
意思を持たず漂うゴーストの眼を狙い、カインは引き金を引く。パンッと弾ける音が、戦闘の合図だった。
***
「――?」
どこかで何かの破裂音がして、あたしは採掘の手を止めて顔を上げた。もしかして、軍に存在を気付かれた?それなら、ここから早く立ち去らないと……。ピッケルをベルトに掛け、腰から下げた袋にメタエネルギーの結晶を放り込んで立ち上がる。まだ視界に人影は見えない。十分に逃げる余裕はある。そう判断して、都市崩壊以前に非常口として使われていた細い道へと急いだ。
――ニーナ・ユウザキ、19歳。長く伸ばした夕日のような赤髪は、サイドを三つ編みにして、後頭部の高い位置で一つに束ねている。透き通る空のような瞳からは、何者にも負けない強い意志が感じられた。左肩から右脇へと下げた大型のマシンガンは、戦場に立つ覚悟の現れのようにも見て取れる。メガシティ・トーキョーで活動するレジスタンスの長を務める“じいちゃん”に育てられた、生まれも育ちもスラム街の少女。上流・中流階級の女性のような“品”は持ち合わせていないが、たくましく生き抜く強さと、負けん気だけは人一倍だった。昨年、成人の18歳を迎えてからは、必然的にレジスタンスの一員として活動するようになり、たびたび一人でロストシティに潜り込んでいた。
(それが今日で終わりとか、勘弁だよマジで)
細い階段を上りながら、あたしはひとり思う。ロストシティ潜入は常に、ゴーストに襲われる危険と隣り合わせにある。そして軍に見つかれば、“危険区域への不法侵入”という名目でC級犯罪人として捕らえられてしまう。それらを防ぐために、レジスタンスは基本的に二人以上で行動するのだけれど、あたしはそれを良しとしなかった。
(自分の行動に対しての責任は、自分で取る。誰の手も煩わせない)
生きるも死ぬも、捕まるも捕まらないも、結果のすべては自分次第。他人の結果が自分のせいになることも、自分の結果が他人のせいになることも、あたしは嫌だった。それが、あたしが常に一人で行動したいと考える理由のひとつだった。
細い階段を上り切り、大きなトンネルの途中に出る。すると、パンパンと連続した破裂音が聞こえてきて、スッと血の気が引くのを感じた。音から逃げてきたはずなのに、なぜ下層のトンネルにいたときよりも音が大きく感じるのか。そもそもどこから聞こえているのか。誰が何をしているのか。混乱しそうになる思考を落ち着けようと、胸に手を当てて、ひとつ、大きく深呼吸をする。
「……ふぅ」
響く破裂音に、静かに耳を澄ませる。どうやら、ひび割れたコンクリート壁を挟んで、今いる場所と隣り合う空間で銃声が響いているようだ。下層のトンネルでも聞こえたということは、今いる場所の下側の空間から聞こえているのかもしれない。また、銃声とともに、微かに金属の擦れる音、金属がぶつかり合う音も聞こえる。あちらの人数は、二人らしい。
(見つかると、分が悪いよね……)
二対一では、さすがにまずい。とにかく、今いるトンネルではないという事実に、少しだけ胸をなでおろした。きっと、ゴーストと対峙しているのだろう。であれば、このまま大きな音を立てずトンネルを抜ければ、気付かれずにロストシティから脱出できるはずだ。よし、と一人頷いて一歩踏み出す。そう、踏み出したはずだった。
「――っえ?」
がくんと体が落ちる感覚。同時に、今まで立っていた場所が大きく揺れて、崩れ落ちる感覚があった。原因を考える余裕なんてあるわけもなく、あたしは真下へと落ちていった。
***
カインは、両手に持った二丁の拳銃で、確実にゴーストを仕留めていた。にもかかわらず、一向に減る気配がない。それどころか、増え続けている。ああ、それもそうかと一つの結論に至ると同時に、ダズの張り上げる声が聞こえた。
「どんだけ出てくんだよこいつら!」
「マザーが吐き出してるんだろう」
「マジかよ!」
「初耳みたいに言うな」
マザーゴーストの持つメタエネルギーコアは巨大だ。周囲に生命活動を感知すれば、自己防衛のために、自らメタエネルギーを分離させてゴーストを生むこともある。奥が薄暗くて見えないが、多分、すぐそこにいるのだろう。それなら、周囲を漂うゴーストを潰し続けていても、無駄に時間を浪費するだけだ。
「ターゲットを奥にいるマザーへ変える」
両手に持っていた拳銃の弾が切れて、その場に放り投げる。同時に、腰の背面のホルダーから新しい拳銃を二丁取り出した。
「お前はゴーストを頼む」
「ふつー援護って逆……!」
自分へ覆いかぶさるように飛んでくるゴーストを払おうと、片足を軸に回転しながら、ダズは苦い声を出す。近距離戦闘型の自分が飛び込み、遠距離戦闘型のカインが援護に回るべきではないのか。しかしその言葉が聞き入れられるよりも先に、カインはマザーゴーストのいる奥へと駆けて行く。追いかけようにも、ゴーストたちが邪魔して身動きが取れない。ダズは、せめて自分が倒れてしまわないようにするのが精いっぱいだった。
カインは、左足に履いたマシンブーツ(メタエネルギーを内蔵した金属製のブーツ)と右足の義足で、前方へと跳躍するように駆ける。地面にかかとが着くたび、バシュン!と大きな音とともに蒸気が噴出されて、体が前に押し出される。メタエネルギーによって生み出した蒸気を圧縮し、かかと裏から噴出させることで、瞬間的に加速するのだ。カインの義手・義足はチタンで作られているとはいえ、それでも生身の人間のそれよりは重い。しかしその重さを感じさせない動きを、メタエネルギーによって引き出していた。
大きく十歩ほど近付いたところで、ゆらりと視線の先の影が揺れる。視界が無数の蒸気の塊でさえぎられていく。ゴーストが自分を取り囲むようにうごめいているのがわかる。影の中うごめいているマザーゴーストが、周囲のメタエネルギーをすべて吸収しているのだろう、見回す限りの電灯はすべて消えていた。
――グオォッ
何かが吠えるような音が反響する。実際には吠えたわけではなく、何かの扉が開いて、空気が大きくうねる音だった。空気が、トンネル全体がビリビリと揺れる。天上のコンクリートがパラパラと落ちてきた。
風を切って噛みつこうと襲い掛かってくるゴーストを拳銃で打ち抜きながら、意識は前方の暗がりにいるマザーゴーストへと集中させる。マザーゴーストは箱型をしていて、ガラス窓のような部分からうっすらと光が漏れていた。光は次第に強くなり、それが都市崩壊以前に作られた“電車”だと認識できるまでになる。電車の前方には、無数の歪んだ牙が生えた口のような割れ目があった。
――ギィ
マザーゴーストが体をきしませながら、足元のレールの上を動く。前方――カインへと少しずつ動き出す。
「……?」
マザーゴーストが体をきしませながら、震える。違う、空間全体が揺れる。車体で支えられていたのだろう、トンネルの天井が大きくひび割れ、メキメキと妙な音を立てた。
(――まずい、このままだと)
天井に押し潰される。そう感じたカインは、後方へと大きく跳躍した。
時間を置かず、天井が目の前で大きく崩れ落ちる。蒸気に混じって砂ぼこりが舞い上がり、一気に視界が悪くなった。
「――きゃあ!」
「……?」
カインの目の前に見えていたマザーゴーストは、瓦礫の奥に隠れてしまう。周りを漂っていたゴーストたちも、天井が崩れ落ちた衝撃で消えてしまった。そして、その代わりに聞こえてきたのは、女の声だった。
「いっ……たぁ……」
カインは、顔が見えるよりも先に、声のした方へ銃口を向ける。ここには自分とダズ以外にいるはずがない。いるとすれば、それは侵入者にほかならない。
「何をしている」
少しずつ視界が晴れて、声の主が見えてくる。天井とともに落ちてきたであろうその人影は、赤髪の少女だった。カインの声に気付いた少女は、後頭部をさすっていた手を止め、カインを見上げる。透き通るような青い目を見開き、次の瞬間にはその場を飛び退いて、カインの脇をすり抜けていた。
「……ターゲット確認」
カインはわずかに目を細めて呟くと、逃げ出した少女の後を追った。
***
紫色の長い前髪から覗く金色の目と、目が合ってしまった。やばい、マズい、逃げないと。今のあたしにはそれしか考えられない。とにかく逃げる。捕まったら、すべてが終わってしまう。途中、金髪の誰かがゴーストと戦っていた。それも構わず素通りする。とにかく、今は逃げないと。
ステップを踏むように、マシンブーツのかかとに付いたレバーを地面へ打ち付ける。プシュッと圧が抜ける音がして、足裏から蒸気が出る。ふわりと浮く感覚になり、地面を蹴れば前方へと体が滑っていく。――ホバー走行。あたしのマシンブーツに備えられた、特殊機能だ。
トンネルに残っている線路の上を時速30キロメールくらいで滑走する。これくらいのスピードならすぐに巻けるんじゃないか。首だけ振り返って、後から着いて来ていないことを確認する。
「っえ、ええ!?」
見えたものに驚いて、変な声が出た。紫頭のそいつは着いて来ていた、ほんの2、3メートル後ろを。そんなまさか、嘘だ。そんなはずはない。だって人間はそんなに早く走れない。走れるのは多分、馬とかなんか、そういう動物か、もしくはメタエネルギーを積んだマシンでしかない。でもバイクとかそんなマシンに乗ってる様子はない。ただ、まるで一歩一歩、跳躍するような、軽やかな動きで近付いてきて――紫頭の右手が、あたしの左腕をグイと掴んだ。
「ちょっ……きゃあ!」
あたしを追い越すように紫頭が前へと飛び出るものだから、あたしは前のめりになってしまう。そのまま一回転して背中から落下する。強い衝撃を覚悟して、反射的に目を閉じて体をこわばらせた。
(……あれ?)
痛くない。背中から確実に落ちたのに、痛みを伴う衝撃はなかった。ただ、きつく体が締め付けられる感覚がある。目を開けて、体を締め付ける正体を確認しようと視線を落としたところで、カシャンッという金属音が耳に届いた。同時に、ひんやりしたものが右手首にまとわりつく。
「……15時41分、ロストシティ不法侵入者を現行犯逮捕」
耳元で低くささやく声が聞こえて、驚いて肩が跳ねる。あたしの頭の中で、急いで状況処理が始まる。逮捕?つまり、ああそう。あたしは捕まったのか。あたしのレジスタンス人生もこれで終わり……ってやだやだ、そんなのはいやだ。隙を見て逃げなくては。というかなぜ耳元から声が聞こえた?耳元?さっきからあたしの体を締め付けているのは、何。腕?腕だ。そう、人の腕だ。つまり、捕まってるからとにかく逃げないと――――。
「逃げようと思うな。諦めろ」
「っな、……るさい!」
またも耳元から声が聞こえて、思考を見透かしたような言葉にかっとなる。振り向きざまに肘鉄を食らわせようとしたところで、背後から抱きしめられて身動きが取れないことを悟った。振り返った目の前に、紫頭の顔がある。金色の瞳があたしをじっと見ている。顔が、近い。よくわからない驚きのようなものがのどでつっかえて、思わず悲鳴に似た声が出る。
「ひっ……!?」
「うるさい、叫ぶな」
紫頭はそう言って、あたしの体を起こす。同時に腕から解放されて、なるほど、あたしが背中から落ちたときにこいつがクッションになってくれたのだと理解する。
(あたし一応犯罪者だけど、かばってくれた……?いや、まさか、ね)
なかなかおかしなことを考えるものだと自嘲して、地面に座り込んだまま、右手首に感じるひんやりの原因を見つめる。あたしの右手首には、しっかり手錠が付いていた。見ただけで、捕まったのだという実感がわいてきて、ゆううつなため息が出る。
うつむいたままでいると、視界が不意に暗くなる。視線をずらすと、紫頭のものであろう足が見えた。上から淡々とした声が降ってくる。
「名前は」
「……」
「……名前は」
「…………」
「……名前」
「ニーナ! ニーナ・ユウザキ!!」
黙っていようかとも思ったけれど、イライラのほうが勝ってしまった。紫頭を見上げて睨みつけながら、怒鳴るように名乗った。これで気が済んだか軍人め。
「ニーナ。なぜここにいる」
「な、ぜ……」
「取り調べだ、答えろ。なぜここにいる」
思わず視線が泳ぐ。そんなの、メタエネルギーの採掘に決まってる。でも多分、それを言ったら、不法侵入以上の罪を告白することになる。言えない。国の財産くすめ取ってたとか、そんなこと言えない。
「…………」
「……メタエネルギーの採掘だろう、レジスタンス」
「っ!」
言うも何も、ばれていた。いたたまれず、目をそらす。顔をそむける。なんで、わかってたならなんで聞いた。この軍人、性格悪いんじゃないか。
「これからお前を連行する」
ぐいと左の二の腕を掴まれて、無理やり立たされる。妙に痛くて顔をしかめる。あたしの腕を掴んだその手は、不思議な姿をしていた。思わず思ったことが口をついて出る。
「……義手?」
「ああ」
「えっ、あ……へぇ……」
まさか呟きに答えが返ってくるとは思わず、言葉に詰まる。よく見るとこの紫頭、右半分が義手義足だった。そして左足はよくよく見るとマシンブーツを履いている。なるほどそれで追い付かれたわけだ。マシンブーツは扱いが難しいから、使う人が多くない。だから、まさか履いているとは思わなかった。背丈は、180センチメートルあるだろうか。なかなか高い。体は結構がっしりしている。軍人だからこんなものか。頭はぼさぼさ、手入れがされてなくて無造作に伸ばした感じ。左半分はきちんと制服を着ているところを見ると、まじめではありそう。右側のコートの袖がないのは、義手を動かす邪魔にならないように、だろう。右足は、膝より上まで義足のようだ。さび付いていない銀色の光沢はなかなか珍しい。アルミじゃ柔らかすぎるし、手も足もチタン製だろうか。
じろじろと観察している間、紫頭は逃げてきた方をじっと見つめていた。そういえば、金髪頭の誰かを素通りした気がする。あれも軍人だったんだろうか。そんなことを思っていると、紫頭がこちらを振り向かずに、一歩二歩、後ずさってくる。三歩四歩、歩みが速くなり、こちらを振り返る。流れるようにあたしの手を取り、さっきはめられたばかりの手錠を突然外された。
「へ?」
「逃げるぞ」
「え、ちょ」
言うが早いか、紫頭は走り出す。理由を聞こうと口を開きかけて、背後から迫ってくる轟音に気付いた。何かが、こちらに近付いてくる。その正体は一部発光していて、すべてが見えなくても理解できた。
「うっそ……マザー!?」
マザーゴースト。巨大だった。電車型。体をきしませながらレールの上を走っている。命の危険を感じて、もつれそうになる足を必死に動かす。すぐにホバー走行に切り替えて、少し先を走る紫頭まで追い付いた。
「ちょっとなんでマザーがいんの!?」
「お前がマザーのいるところに落ちてきたんだ」
「マジで!?」
ぼんやり憶測だけだった情報がつながっていく。ひっきりなしに続いていた銃声、崩れ落ちたトンネルの床、二人(多分)の軍人。あたしは今まで、痕跡が見つかって捕まることはなかった。そうやって、一人でやってこれたのだ。なのになぜ、さっき捕まったのか。ああ、そうだ、マザーゴースト、こいつのせいだ。運悪く、こいつのいるところに居合わせてしまったのだ。運がなかったあたし自身に、嫌気がさして、小さく呻く。
「うぅ……!」
「状況を悔やんでる暇はないぞ」
「勝手に人の思考読まないでくれる!?」
左隣から飛んできた声に、思わずきつい視線を向ける。紫頭の視線は、こちらに向いていたわけではない。顔を見られていたわけではないだろう。でも、声一つで、あたしの思考を読まれてしまった。なんだこいつ、見透かされていることに腹が立つ。
もやもやした感情が腹の中で渦巻いている間も、マザーゴーストは壁を崩しながら、土煙を上げながら、周囲に蒸気をまといながら追いかけてくる。とにかく必死に逃げるので精一杯だ。こっちは多分、時速40キロメートルくらいは出してる気がする。それでも、ギリギリ。どれくらい走ればいいのか途方に暮れそうなところで、また左隣から声が飛んでくる。
「曲がれるか」
「は!?」
「前」
「今度は!」
何。そう言おうとして、前に視線を戻して、目を見開く。行き止まりだ。まずい。あたしのホバー走行は直線には有利だけれど、急に止まったり曲がったりするのは苦手だ。小回りが利かない。
「左だ」
「くっ……!」
紫頭は軽々と跳躍して、左側にぽっかりと開いている穴に向かって曲がる。あたしは姿勢を低くして、担いでいたマシンガンを地面に突き付ける。ギィイッと金属の擦れる音が響く。時速40キロメートルで動いていたあたしの体がゆっくり壁に近付く。マシンブーツが壁に着く。瞬時にかかとのレバーを地面に打ち付けて、強く蒸気を噴出させる。
「やっ……!」
勢いよく壁を伝って滑る。無事に体勢を整えて、ぽっかりと開いている穴へと飛び込む。真後ろで、マザーゴーストが壁に衝突する音が響く。落下に備えてかかとのレバーを引き上げる。足裏から出る蒸気の量が増える。足裏にできた空気の層の力で、マシンブーツの重量に反して、音もなく着地する。
「ふぅー……」
線路が何本も通っている、とても広い空間に出た。危機は脱したようで、全身から緊張が抜ける。ぐるりと周囲を見渡すと、メタエネルギーが多いのだろう、トンネル内に設置されたあらゆる電灯が煌々と照っていた。
「来るぞ」
声がして、我に返って、声の聞こえた正面へと顔を戻す。待っていたのだろうか。あたしの正面に、紫頭が立っていた。
「何、来るって」
あたしの言葉に、紫頭は言葉で答えず、くいと顎で指す。背後――飛び込んできた穴を見上げる。ガラガラと音を立てながら、穴を押し広げながら、マザーゴーストがこちらへと迫ってくる。
「う、そ……」
18歳で成人を迎えてから、これまで何度もロストシティに潜り込んできた。そのたびに、ゴーストと戦ってきた。けれど、マザーゴーストとは、さすがに戦ったことがなかった。だって、危険なのだ。マザーゴーストは、噛みつかれて怪我をする程度の普通のゴーストとはわけが違う。文字通り、人を食べる――――。
目の前の現実に、めまいがして、ふらっと後ろに一歩下がる。もう一歩下がりかけたところで、背中を支えるものを感じた。
「……え?」
「倒れるなら後にしろ。まずはあれを討伐するのが先だ」
「……」
あたしの背中を支えるものは、紫頭の右手だった。あたしの左側に立つ紫頭は、穴から落下してくるマザーゴーストをじっと見つめている。マザーゴーストが地面に落ちると、広い空間全体が大きく揺れた。耳鳴りがして、思わず目を閉じて耳をふさぐ。
「ニーナ」
名前を呼ばれるのと同時にぐいと左肩を掴まれ、目を開けて、顔を上げる。紫頭の金色の目が、あたしの目をじっと見ていた。
「え、と」
「お前のそれは銃か」
「あ……うん、えっと」
“それ”と言われて、一瞬考えて、理解する。あたしが下げているマシンガンのことを尋ねられているのだ。両耳に当てていた手を下ろして、あたしはマシンガンを持ち上げる。
「これ。一応ただのマシンガンだけど、メタエネルギー使って、火と、電気と、氷の効果、弾に乗せられる」
「援護できるか」
「わかんない。けど、やってみる」
あたしの言葉に無表情のままうなずいて、紫頭はマザーゴーストめがけて跳躍する。マザーゴーストは、横倒しになった自分の体を起こそうとうごめいている。あたしは、マザーゴーストに向けてマシンガンを構えた。さっきまで、ものすごくマザーゴーストが怖かったはずなのに、いつの間にか恐怖は消えていた。いや、消えたわけじゃない。ただ、それよりも強い味方を得た気持ちだった。
(今は、とにかく、生き残ることを考えなきゃ)
マシンガンの背部のレバーを強く引っ張る。ガシャンと大きな音を立てて、蒸気が吹き上がる。レバーの横にあるダイヤルを“氷”に合わせる。引き金を引く。ダダダダッと四連続、それが三回、12発の弾が発射されて、マザーゴーストの車体の周囲に刺さる。弾が刺さった場所から氷が広がっていく。マザーゴーストの体の動きが減っていく。
「よっし!」
目に見えた効果に一人で小さくうなずく。身動きが取れなければこっちのほうが有利だ。少し余裕が出たと思った瞬間、マザーゴーストの口がグパァと開いて、ゴーストたちが飛び出てくる。その光景に思わず後退りそうになるのをぐっと堪えて、もう一度マシンガンを構える。ダイヤルを“無”に戻して、12発の弾をマザーゴーストの車体に撃ち込む。弾の軌道を縫うように紫頭へと襲いかかるゴーストたちを、紫頭が素早く、そして確実に撃ち落としていく。その光景に、感嘆の声が出る。
「すごい……」
文字通りの精密射撃。言葉でしか聞いたことがなかった。まとう蒸気を失ったゴーストの核――メタエネルギーコアがカラカラと落ちていく。タンッと、紫頭がマザーゴーストの目の前に着地する。マザーゴーストの口が再度大きく開く。見計らって、紫頭が口の中へ飛び込んだ。そう、飛び込んだ。思いがけない行動を目にして、何が起きたのか理解できない。何、自分から飛び込んだ?
「え、ちょ……ねぇ!」
思わず数歩駆け寄って、マザーゴーストに食べられてしまった紫頭に向けて声を投げかける。もちろん返事は聞こえない。ゴーストたちもコアだけになってしまって、辺りにはマザーゴーストのうめき声だけが響いている。
「うそ……」
なんで?なんで彼は自ら食われに行ったのだろう。いなくなってしまった、目の前で。あたしを一瞬でも捕まえた彼が、マザーゴーストに食われてしまった。食われたら生きては帰れないといわれている、あのマザーゴーストに。どうしよう、どうして?疑問と、さっきまで忘れていた恐怖心が、頭の中をめぐる。足がすくんでしまう。嫌、だめだ。こんなところで死んでたまるもんか。気のせいかもしれないけれど、だって紫頭はあたしを助けてくれた――――。
「っ、こいつ!」
キッとマザーゴーストをにらみつけて、マシンガンを構えなおす。こいつに一発、でかいのをぶち込んでやろう。そうすれば、もしかしたら倒せるかもしれない。やったことはないけれど、できることに賭けるしかない。強く背部のレバーを引く。ダイヤルを“火”に合わせる。引き金を、引こうとした瞬間だった。
――ベキベキベキ……
マザーゴーストが妙な音を立てて震えだした。開いた口から、蒸気が溢れ出る。震えは次第に大きくなり、ガタガタと空間を揺らし始めた。足裏から小さな振動を感じる。無意識のうちに一歩後退りしたところで、口から灰色の塊が、蒸気とともに飛び出してきた。飛び出してきたものが何かを確認しようと、目を凝らして、蒸気が薄れるのを待つ。それが見えてくると、不思議と胸の奥に安堵が広がってきた。
(ああ、よかった……)
灰色の塊は、紫頭と、金髪の誰かだった。紫頭は金髪の誰かを地面に寝かせて、膝をついたまま見下ろしている。
「ダズ、わかるか」
「……ゲホッ、ゲホッ」
金髪の誰かはダズという名前なのだと、その時初めて理解する。紫頭とダズの背後に見えるマザーゴーストへ視線を向ける。内側から光を発していた車体からは、いつの間にか光が消えていた。どうやら機能停止したらしい。何がきっかけだったかはわからないけれど、無事に倒せたみたいだ。
「あー……俺、ゲホッ……生きてるか……?」
「ああ。保護装置は正常に作動している、身体欠損は見られない」
「へへっ……さすが、技術部せっゲホッ……装、置……」
紫頭とダズは、あたしの存在を忘れたかのように話している。ちょっと話の内容は気になる。保護装置とは何だろう。技術部とは軍の部署の話だろうか。レジスタンスが有利に動くためには聞いていたほうがいい話だろうか。
「……あり、がとな、カイン。よく中にいるって……わかったな……」
「状況からして当然だろう。それに、これはお前一人にマザーを任せてレジスタンスを追った俺の責任だ」
「ははっ……よく、わかってんじゃねーか……」
紫頭は、カインという名前らしい。そして、なるほどカインはダズにマザーゴースト討伐を任せて、あたしを追いかけてきたわけだ。
(……ん?なるほど……?)
会話に聞こえた言葉へ納得して、それから首をかしげる。一気に血の気が引いていくのを感じる。そう、あたしは、追われている身だった。一度、一瞬でも逮捕された身だった。
(――逃げないと!!)
慌てて軍人二人に背を向ける。背を向けて、駆けだそうとして、足が止まる。ここが今どこかわからない。どうやって外に出たらいい?ルートは?逃げ道は?この空間のどこかに「非常口」はない?高い天井を見渡してもそれらしいものはない。視線を下にずらして、右手側――身長より高い大きな段差の奥側に階段のようなものを見つける。あれしかないと別のあたしが言って、迷わず駆け出す。一瞬、左手首に冷たいものが触れるのを感じた。
大きな段差の上に飛び乗って、そのまま階段の入り口まで滑走する。滑走しながら、首だけ後ろを振り返る。――――ほんの少しだけ目を見開いた、右手を伸ばしたカインの顔が、小さく見えた。
「じゃあねー、軍人さん!」
そう明るい声で言い残して、あたしは階段を駆け上った。
***
初めて、レジスタンスを取り逃がした。一度は捕まえたはずのレジスタンスを、逃してしまった。カインにとって、この2年間で初めてのことだった。活動報告を受けたレジスタンスの逮捕率が100%というカインの伝説は、この瞬間、崩れてしまった。
「あーあ、逃したかぁ」
「……ああ」
ダズの声よりも、カインは、自分の右手の指先に意識を向けていた。確かに一瞬だけ、レジスタンスの少女の手首に触れた。けれど、なぜか掴めなかった。
「追いかけねーの?」
目立った外傷はないけれど少しすす汚れてしまったダズが、起き上がってきて、右横に立つ。ぽんと、カインの右肩に手を載せた。
「……ああ、そうだな」
今から追いかけても、間に合わないだろう。カインはそう、ぼんやりと考える。なぜ、彼女を捕まえられなかったのだろう。まさか、捕まえる気がなかったのだろうか。
「ま、レジスタンスを見つけたことは報告しないでおこうぜ。今回は、マザー討伐の任務で一件落着ってことで」
「ああ……」
カインは、ぐっと右手を握りしめる。触れたのに、確かに一瞬触れたのに、捕まえることができなかった。なぜ、すぐに手錠をかけ直さなかったのだろう。
「……なぜだろうな」
「あん?どうした?」
「いや、なんでもない」
カインは首を横に振り、マザーゴーストの前に立って、腰から下げたメタエネルギー回収装置を地面に刺すように置く。ゆっくりと、マザーゴーストから黒い液体のようなものが流れ出てきて、メタエネルギー回収装置に集まっていく。
「じゃ、俺たちも帰ろーぜ?」
「そうだな」
マザーゴーストから流れ出たメタエネルギーをすべて回収し終えると、メタエネルギーが回収装置の中で固形に変化し、カランッと音を立てる。メタエネルギー回収装置を腰に戻して、カインは軍の施設への帰路についた。
(――次に会ったら、必ず、捕まえてやる)
逃した悔しさを確かめるように、カインはもう一度だけ、右手を強く、握りしめた。
[/font]